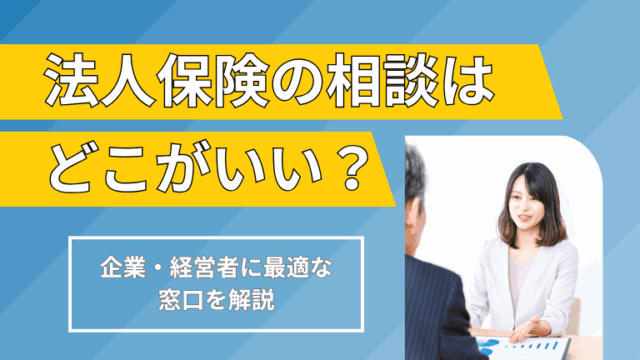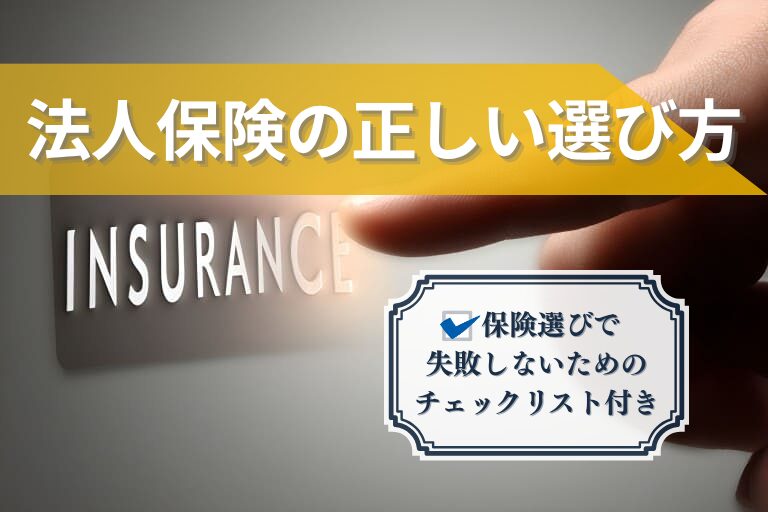法人保険とは、法人が契約者となる保険契約を指します。経営者個人の保障や従業員の福利厚生、企業の事業保障や資金準備などに活用されます。
保険料を経費として計上できる点も特徴で、節税(課税の繰延)目的で法人保険に加入する企業も少なくありません。
ただし、法人保険の保険料を経費として処理するときは、注意すべきルールもあります。適切に経費計上しなければ、税務調査で指摘され、追徴課税の対象になるかもしれません。
本記事では「法人保険は経費にできるのか?」と疑問を抱く経営者や経理担当者に向けて、保険料の経理処理に関する基本知識や注意点についてわかりやすく解説します。
法人保険は経費にできる!経理処理の基本

法人保険の保険料は経費として計上可能です。また、法人税法上の「損金」に算入できます。
- 経費
- 会計上の概念で、収益を得るために支出した費用を指す。
- 損金
- 税法上の概念で、費用のうち所得計算時に控除できるものを指す。
ただし、法人保険の経費・損金処理は、保険の種類や契約形態によってルールが異なるため注意が必要です。
法人保険の経理処理は「税法上の損金になる範囲」で経費となる
経費と損金は本来別の概念であり、必ずしも「経費=損金」とはなりません。
しかし、法人保険における保険料の経理処理は、単年度で見る限り「経費=損金」と考えて差し支えありません。法人税法において損金とみなされる範囲で、会計上も経費計上します。
ポイントとなるのは、法人税法では損金算入の取扱いが細かく定められており、場合によっては保険料を支払った年に全額損金算入ができないことです。損金算入できない分は、一旦資産として計上する必要があります。
税務上の損金算入ができない場合は、会計上も同じように経費計上できません。つまり、保険料の経理処理を行うときは「税法上の損金算入ルールの把握」が必須と考えましょう。
法人保険の損金算入ルール(2019年税制改正以降)
法人保険の損金算入ルールは非常に複雑です。「貯蓄性はあるか」「保険の種類は何か」など、さまざまな条件で算入方法が変わります。
以下は、重要な部分に絞って損金算入ルールをまとめたものです。
| 法人保険の種類 | 損金算入ルール | 備考 |
|---|---|---|
| 掛け捨て型の定期保険や医療保険など (解約返戻金なし) |
全額損金 | 解約返戻金がない(あっても低い)場合、貯蓄性がないため全額損金算入。 |
| 貯蓄型の定期保険や医療保険など (解約返戻金あり) |
最高解約返戻率にもとづいて一部損金算入・一部資産計上(表②参照) | 解約返戻率が高いほど貯蓄性があるとみなされ、損金算入が規制される。 ※「30万円特例」の例外あり(表②補足参照)。 |
| 終身保険 (法人受取) |
全額資産(損金不算入) | 貯蓄性が高いため損金算入が規制される。 |
| 養老保険 (死亡・満期とも法人受取) |
全額資産(損金不算入) | 満期・死亡保険金を法人が受け取るため、貯蓄性が高く全額が損金算入の対象外となる。 |
| 養老保険 (死亡保険金は遺族受取・満期保険金は法人受取) |
50%損金、50%資産 | 「死亡保険金=福利厚生」「満期保険金=会社の貯蓄」と半々の性質を持つため、1/2のみ損金算入。 |
| 養老保険 (死亡・満期とも被保険者または遺族が受取) |
全額損金算入(給与扱) | 「法人から個人への利益移転」であり、給与とみなされる。個人の課税対象となり、会社側も源泉徴収を行う。 |
| 最高解約返戻率 | 損金算入割合 | 資産計上割合 |
|---|---|---|
| 50%以下 | 100% | 0% |
| 50%超70%以下 | 50% | 50% |
| 70%超85%以下 | 40% | 60% |
| 85%超 | 10% | 90% |
契約開始から一定期間、表の割合に従って保険料の一部を資産計上し、残りを損金算入。資産計上した分は、保険期間の後半に按分して損金算入する。
最高解約返戻率が70%以下で、被保険者1人あたりの年間保険料が総額30万円以下の場合、例外として全額損金算入が可能(30万円特例)。
基本的に、法人が高額な解約返戻金や満期保険金を受け取れる保険(貯蓄性がある法人保険)は、資産計上が必要になります。
ただし、資産計上した分は将来的に損金として算入し直すため、最終的には「総支払保険料=損金算入額」となるよう調整されます。
保険の種類ごとの具体的な経費処理

法人保険の経理処理は、保険のタイプによって、「経費化するタイミング」が異なります。ここでは、各タイプの具体的な経費処理を解説します。
1. 掛け捨て型の定期保険や医療保険など(解約返戻金なし)
このタイプの法人保険は、支払った保険料の全額が経費・損金となります。
保険料支払い期間(資産計上なし)
支払った保険料は、すべて経費(借方)で計上します。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 支払保険料 〇〇〇円 | 現金預金 〇〇〇円 |
2. 貯蓄型の定期保険や医療保険など(解約返戻金あり)
このタイプの法人保険は、最高解約返戻率に応じて、保険料の一部が資産となり、後で経費化されます。
保険料支払い期間(資産計上期間)
保険料の一部を経費として、残りを資産として計上します。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 支払保険料 〇〇〇円 保険積立金 〇〇〇円 |
現金預金 〇〇〇円 |
取り崩し期間
保険料の支払いが終わった後、資産計上した部分を少しずつ経費に振り替えます。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 支払保険料 〇〇〇円 | 保険積立金 〇〇〇円 |
3. 終身保険(法人受取)
このタイプの法人保険は、支払った保険料は経費にならず、全額が資産として計上されます。
保険料支払い期間(資産計上期間)
支払った保険料の全額を資産として計上します。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 保険積立金 〇〇〇円 | 現金預金 〇〇〇円 |
取り崩し期間
解約や満期を迎えた時に、資産として計上していた分を費用に振り替えます。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 現金預金 〇〇〇円 雑損失 〇〇〇円 |
保険積立金 〇〇〇円 雑収入 〇〇〇円 |
4. 養老保険(死亡・満期とも法人受取)
このタイプの法人保険は、終身保険と同様に、支払った保険料は全額が資産として計上されます。
保険料支払い期間(資産計上期間)
支払った保険料の全額を資産として計上します。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 保険積立金 〇〇〇円 | 現金預金 〇〇〇円 |
取り崩し期間
満期を迎えた時に、資産として計上していた分と受け取った満期保険金を相殺し、差額を費用(雑損失)または収益(雑収入)として計上します。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 保険積立金 〇〇〇円 | 現金預金 〇〇〇円 雑収入 〇〇〇円 |
5. 養老保険(ハーフタックス)
このタイプの法人保険は、支払った保険料は半分が経費、半分が資産となります。
保険料支払い期間(資産計上期間)
保険料を半分ずつ、経費と資産として計上します。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 支払保険料 〇〇〇円 保険積立金 〇〇〇円 |
現金預金 〇〇〇円 |
取り崩し期間
資産計上した部分は、将来(通常は保険期間の後半)に、費用に振り替えます。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 支払保険料 〇〇〇円 | 保険積立金 〇〇〇円 |
6. 養老保険(死亡・満期とも被保険者または遺族が受取)
このタイプの法人保険は、法人が支払う保険料が、従業員への給与とみなされます。
保険料支払い期間(資産計上なし)
支払った保険料の全額を給与として経費計上します。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 給与 〇〇〇円 | 現金預金 〇〇〇円 |
法人保険における経理処理の注意点

法人保険の経理処理を行う際は、以下の点に特に注意しましょう。
1. 税務調査に備えて資料を保管する
法人保険は損金算入ルールが複雑なため、税務調査で処理方法を厳しくチェックされることがあります。万が一、法人保険の経理処理に誤りがあると、追徴課税の対象になる可能性もあります。
契約時の保険証券や設計書、保険料の支払明細、会計処理の根拠などをしっかり保管し、いつでも説明できるように準備しておきましょう。
2. 勘定科目は自社のルールに従う
法人保険の会計処理で使う勘定科目は、会社が定めた経理規程や、利用している会計ソフトの仕様によって異なります。
「保険積立金」や「長期前払費用」など、本記事で提示した勘定科目はあくまで一例です。実際に法人保険の経理処理を行う際は、自社のルールに合わせて適切な科目を選んでください。
3. 経理担当者の引き継ぎを明確にする
貯蓄性のある法人保険は、保険料の支払い期間と、資産を取り崩す期間が数十年単位に及ぶことがあります。経理担当者が代わった場合、過去にどのような処理をしていたかを正確に引き継がなければ、処理の継続性が失われるリスクがあります。
処理方法をマニュアル化したり、会計データの備考欄に情報を残したりして、誰が見ても分かるようにしておくことが大切です。
まとめ

法人保険の保険料は、税制上の損金算入ルールに合わせて経費計上が可能です。
2019年の税制改正により「最高解約返戻率」などを基準とした厳密なルールが定められたため、正しく処理する必要があります。
仕訳や資産計上の方法を正しく理解し、税理士など専門家のアドバイスをもらいながら、会社の状況に応じた法人保険の経費計上を実施しましょう。
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス

- 法人保険を経営に活用したい
- いま加入している保険を見直したい
- 退職金制度や福利厚生を導入したい
- 事業承継や相続について考えたい
- 税金対策や財務戦略を相談したい
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて
"無料"で貴社に最適な保険プランを提案します。