物件を一棟まるごと購入するのではなく、小口に分けて出資する「不動産小口化商品」という投資方法があります。少額から不動産投資に参加できるほか、法人が活用すれば節税対策にもつながります。
この記事では、不動産小口化商品の仕組みや、法人での活用方法、節税につながるポイント、導入前に確認しておきたい注意点までを分かりやすく解説。
「法人の節税方法を探している」「不動産小口化商品を法人でどう活かせばいいのか?」と悩んでいる方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
不動産小口化商品とは?
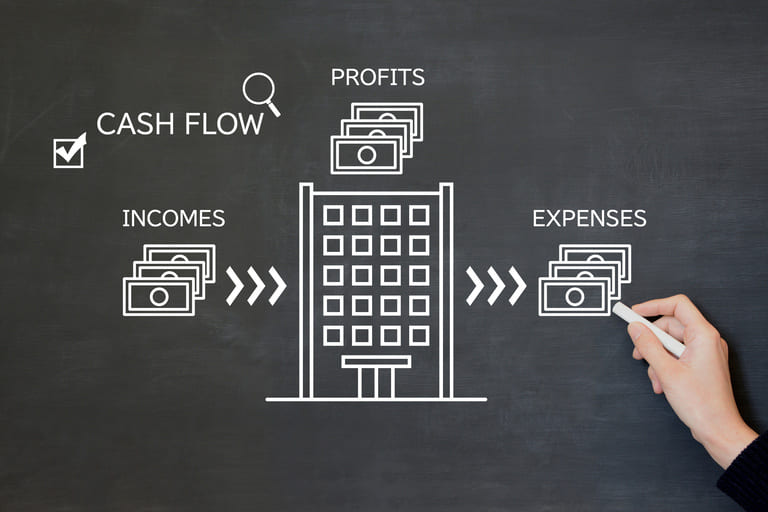
不動産小口化商品は、ひとつの不動産を小口に分けて販売する投資商品です。1口あたり数万円〜数百万円から出資可能で、運用や管理は事業者に任せられます。
投資家は出資額に応じた収益分配を受け取れるため、自己管理不要で実物不動産に投資できる手軽さが特徴です。
不動産小口化商品なら少ない負担で投資できるため、多額の資金や運用負担を避けたい法人にとって魅力的な選択肢となります。
不動産小口化商品の種類
不動産小口化商品には、契約形式の違いによって以下の3タイプに分かれます。
匿名組合型
匿名組合型は、事業者と「出資契約」を結び、収益の一部を分配金として受け取る形式です。不動産の所有権は事業者側にあり、投資家は運営に関与しません。
1口1万〜10万円程度から始められるため参入しやすい反面、所有権を得られないため減価償却はできません。また、事業者が破綻しても出資金は保証されないため注意が必要です。
任意組合型
任意組合型は、投資家が不動産を共同で所有し、登記上の共有名義者となる形式です。共有名義者が構成する任意組合から、事業者に管理運営を委託します。
投資家それぞれが出資割合に応じた所有権を持つため、減価償却の計上が可能であり、法人の節税対策としても活用できます。また、事業者が破綻しても出資者の所有権は守られます。
出資額は1口100万円以上が主流で、中長期の運用に向いている契約形式です。
賃貸型
賃貸型は、出資者が不動産を共同で所有し、物件を事業者に貸し出す形式です。事業者から支払われる賃借料や売却時の利益が、出資割合に応じて配当されます。
出資額は1口100万円程度からで、基本的に長期運用が前提となります。相続対策や安定的収益の確保を目的とする法人に適していますが、事業者の破綻リスクや運営の難しさから、取り扱い件数は少なくなっています。
法人が不動産小口化商品を活用するメリット

法人が不動産小口化商品を活用することで、節税対策や資産運用の幅を広げられます。
ここでは、不動産小口化商品を導入する法人にとってのメリットを紹介します。
減価償却による節税ができる
建物部分に対応する出資額を減価償却資産として経費処理することで、法人税の節税につながります。
たとえば、1,000万円の商品で建物部分が700万円に相当する場合、この金額を耐用年数に応じて分割償却できます。
ただし、前述の通り匿名組合型は減価償却の対象外である点に注意が必要です。
少額で不動産投資ができる
通常、不動産投資には数千万円単位の資金が必要ですが、不動産小口化商品なら1口100万円前後から投資可能です。
都心の商業施設や人気エリアのマンションなど、通常なら保有が難しい物件にも無理なく投資できます。
資金に余裕がない法人でも参入しやすく、気軽に不動産投資を始められる利点があります。
リスク分散が可能
不動産小口化商品を活用すれば、資金を複数の物件に分けられるため、リスクを最小限に抑えられます。
仮に5,000万円を1つの物件に全額投資してしまうと、事故や災害などで価値が毀損された場合に損失が大きくなります。一方、10件の不動産小口化商品に500万円ずつ投資すれば、リスク分散が可能です。
さらに地域・業種の異なる物件へ分散投資すれば、より堅実に資産を運用できます。
相続・事業承継対策にも応用できる
不動産小口化商品は現金よりも相続税評価額が低く、評価額の引き下げにより節税効果を得られる場合があります。
さらに、「小規模宅地等の特例」という制度も利用可能なので、物件によってはより大幅な節税も期待できます※。
加えて、共有化されているため後継者への分割もしやすく、承継トラブルの防止にもつながる点も魅力です。
※法人名義の場合、小規模宅地の特例は原則として適用されないため、法人ではなく個人が相続する場合に限られます
不動産小口化商品による法人の節税方法4選
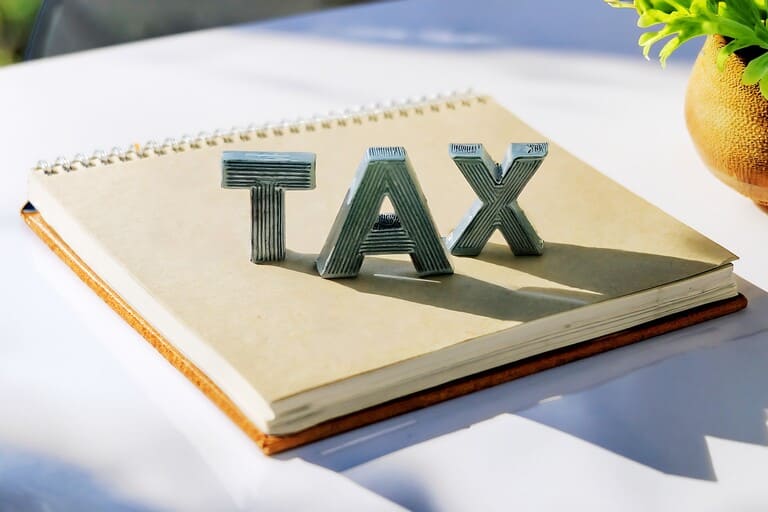
不動産小口化商品は、資産運用と節税対策を両立できる注目の選択肢であり、経営戦略の一環として導入するケースも少なくありません。
ここでは、不動産小口化商品を活用した法人向け節税アイデアを4つご紹介します。
節税方法① 決算前の利益を調整して法人税を軽減する
決算前に出資すれば、減価償却費として計上し課税所得を調整できます。
1口あたりの出資額もそれほど高くないため、年度末に想定以上の利益が出てしまった場合など「決算直前の節税対策」として使い勝手が良い方法です。
節税方法② 役員報酬や退職金と組み合わせて節税効果を高める
役員報酬や退職金は、損金として計上できます。不動産小口化商品と合わせて活用することで、節税と将来の資金準備を同時に進めることが可能です。
退職金資金の積立先として不動産小口化商品に投資すれば、減価償却による法人税の軽減を受けられます。将来の支出に備えつつ、当面の税負担を軽減可能です。
節税方法③ 社長個人と法人の両方で商品を使い分ける
不動産小口化商品は、法人だけでなく社長個人でも活用できる節税商品です。法人では減価償却を活かして利益を調整し節税を図る一方、個人では相続対策として評価額を抑える効果が期待できます。
法人と個人の両方で使い分けることで、包括的な資産戦略を実現できます。
節税方法④ 事業承継前に不動産小口化商品を活用して資産を移す
不動産小口化商品は分割しやすく、相続税評価も抑えられるため、事業承継時の資産移転や贈与計画にも効果的です。
事業承継においては、節税を意識しながら資産をスムーズに移転するための対策が欠かせません。法人の資産承継戦略としても、不動産小口化商品は有効な選択肢の1つです。
節税目的で導入する際の注意点

不動産小口化商品は、手軽に不動産投資を始められる手段ですが、事前に知っておくべき注意点も存在します。
ここでは、特に注意したい3つのポイントを紹介します。
土地部分は減価償却できない
一般的な不動産と同様、不動産小口化商品の減価償却は建物部分に限定されます。
土地は時間が経っても価値が下がるとは限らず、立地や需要によっては価格が上昇することもあります。たとえば、東京の駅近の土地は数年で価格が上がるケースもあり、「古くなるから安くなる」という前提が通用しません。
減価償却による節税効果を重視するのであれば、契約時に土地・建物の割合を確認し、土地割合が大きすぎないかチェックしましょう。
匿名組合型の節税効果は限定的
先にも解説しましたが、不動産小口化商品には3つの契約形式があり、そのうち匿名組合型は投資家に所有権がありません。そのため減価償却ができず、所得区分も雑所得なので、節税効果は限定的です。
| 契約形式 | 所有権 | 減価償却 | 課税区分 | 節税効果 |
|---|---|---|---|---|
| 匿名組合型 | なし | 不可 | 雑所得または配当所得 | 小さい |
| 任意組合型 | あり | 可能 | 不動産所得 | 大きい |
| 賃貸型 | あり | 可能 | 不動産所得 | 大きい |
資金の一時的な運用や雑所得の分散など、キャッシュマネジメントの一環としては有効な部分もありますが、節税を重視するなら他の契約形式の商品を選びましょう。
信頼できる業者選びが重要
どれだけ魅力的な商品でも、運用する会社の信頼性が低ければ、資産が危険にさらされる可能性があります。過去には、事業者の破綻により出資金が戻らなかった例もあります。
安心して投資するためには、次のような観点で業者を見極めましょう。
- 上場企業、またはそのグループ会社としての実績がある
- 有名な企業や金融機関が出資元にある
- 長期的に安定した財務状況が続いている
- 小口化商品やクラウドファンディングでの運用実績が豊富
- 元本割れやトラブルの報告が少ない
実際の運用実績や経営状態をしっかり確認しながら、自分の資産を任せられる会社かどうかを冷静に判断しましょう。
まとめ

今回は、不動産小口化商品を法人で活用することによる節税効果について解説してきました。
減価償却による法人税の圧縮や、資産の分散投資、相続・事業承継対策など、法人にとってさまざまなメリットがあります。ただし、契約形態によって税務上の扱いが異なる点や、信頼できる事業者選びの重要性など、注意すべき点も少なくありません。
導入を検討する際は、FPや税理士などの専門家と相談しながら、無理のない範囲で活用しましょう。
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス

- 法人保険を経営に活用したい
- いま加入している保険を見直したい
- 退職金制度や福利厚生を導入したい
- 事業承継や相続について考えたい
- 税金対策や財務戦略を相談したい
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて
"無料"で貴社に最適な保険プランを提案します。




















