消費税は、売上が増えるほど納税額も増えるため、経営者にとっては思った以上に大きな負担になります。
特に中小企業や、個人事業主から法人化したばかりの方にとっては、インボイス制度への対応などから「消費税の節税」を考える場面が増えてきたのではないでしょうか。
この記事では、消費税が法人経営に与える影響や節税の必要性を整理したうえで、具体的な消費税対策を解説します。
簡易課税制度の活用や、法人成りによる免税期間の使い方、外注費や派遣社員の活用法まで、法人の消費税の節税につながる考え方をわかりやすく紹介していきます。
消費税節税を考えるべき理由

消費税は、会社の経営や資金の流れに直接影響する重要な税金です。特に中小企業では、対策次第で負担の程度が大きく変わります。
以下の3つの理由から、法人にとって消費税の節税対策は重要です。
- 消費税は法人経営に与えるインパクトが大きい
- インボイス制度の開始で節税対策がより重要に
- 法人税と異なり、見落とされがちなポイントが多い
ここからは、それぞれの理由について、具体的な例も交えてわかりやすく解説していきます。
消費税は法人経営に与えるインパクトが大きい
消費税は、商品やサービスを売ったときに取引相手から預かる税金です。売上が増えれば、預かる消費税も増えます。
たとえば、年間売上が1億円の法人なら、単純計算で約1,000万円の消費税を預かります。このお金は法人の利益ではなく、後から国に納付します。
納税まで手元にお金が残っていても、うっかり使ってしまうと、納税時に資金不足になりかねません。資金繰りが悪化すれば、法人の経営全体が立ち行かなくなる可能性もあります。
このように、消費税は売上やお金の管理に大きく影響します。だからこそ、法人として節税や資金計画をしっかり立てて、消費税の節税対策を考えることが重要です。
インボイス制度の開始で節税対策がより重要に
2023年10月から始まったインボイス制度では、仕入れや外注に関する取引で「インボイス(適格請求書)」を保存しておくことが求められるようになりました。インボイスがない取引は、支払った消費税を差し引けません。
この変更によって、インボイスを発行できない免税事業者との取引が敬遠されるケースも出てきています。そのため、売上が1,000万円未満の小規模事業者でも、今後の取引を見据えて課税事業者として登録する動きが増えています。
課税事業者になることで増える税負担を、節税対策でいかに軽減するかが経営課題として重要です。
法人税と異なり、見落とされがちなポイントが多い
消費税には、法人税とは違う独自のルールがたくさんあります。課税・非課税といった取引の区別をきちんと理解しないと、控除できるはずの税金を取り逃がしてしまうかもしれません。
たとえば、医療費のような非課税取引にかかる支出は、たとえ消費税を払っていても控除の対象外です。法人がこのルールを知らずにいると、結果的に損をしてしまいます。
また、業種ごとに決まった割合(みなし仕入率)で消費税を計算する「簡易課税制度」というものがあります。実際の経費が少ない業種の法人なら、この節税につながる制度で納税額の軽減が可能です。
こうした細かい制度を理解しないと、受けられる控除を見逃したり、余計な税金を払ったりする羽目になりかねません。消費税は法人にとってルールが複雑だからこそ、しっかり節税対策を考える価値があります。
法人が実践できる消費税節税方法7選

法人で事業を続けていると、毎年の消費税の負担は意外に大きく感じるものです。工夫次第で負担を抑えられることもあるため、節税の選択肢を知っておくことは大切です。
ここでは、比較的取り入れやすく、法人でも実践しやすい消費税の節税方法を7つご紹介します。
①簡易課税制度を検討する
売上が5,000万円以下の中小企業は、「簡易課税制度」を使うことで消費税を抑えられる可能性があります。
簡易課税制度では、実際の仕入額ではなく、売上に対してあらかじめ決められた「みなし仕入率」で仕入税額を計算します。たとえば、サービス業ではみなし仕入率が50%とされているため、売上の半分を仕入れと見なして税額を計算できます。
例:みなし仕入率が50%の場合
売上にかかる消費税が500万円、仕入れにかかる消費税が200万円の場合、通常は差額の300万円を納めますが、簡易課税制度では「500万円-(500万円×50%)=250万円」となります。
支出の少ない業種や時期によっては、大きな節税効果が期待できます。ただし、設備投資などで支出が多いときは、通常の方法のほうが有利になるケースもあるので、状況に応じて使い分けましょう。
②法人成りによる免税期間を活用する
個人事業主から法人に切り替えると、条件を満たすことで最長2年間は消費税の納税が免除されます。
この制度の対象となるには、次の3つの条件がそろっていることが必要です。
- 法人設立時の資本金が1,000万円以下である
- インボイス発行事業者として登録していない
- 消費税課税事業者選択届出書を提出していない
これらの条件に当てはまれば、法人設立直後の期間、消費税の支払いが不要になります。
創業初期は、売上が不安定だったり、出費がかさんだりと、何かと資金に余裕がない時期です。そうした中でこの免税措置をうまく活用できれば、手元の資金を事業に集中させやすくなります。
③外注費をうまく使う
外注先に仕事を依頼すると、消費税の負担を軽くできる場合があります。
給料には消費税がかかりませんが、外注費にはかかるため、その分は「課税仕入れ」として控除できます。たとえば11万円を支払った場合、うち1万円が控除の対象になります。
一方、同じ業務を社員に任せて給料として支払った場合、消費税分の控除はできません。つまり、外注に切り替えることで、課税仕入れとして処理できる分が増え、納税額を抑えられるというわけです。
外注費をうまく活用すれば、業務の効率化とあわせて、消費税の節税にもつながる可能性があります。
④人材派遣の活用で課税対象をコントロールする
正社員に支払う給料には消費税がかかりません。このため、給料にかかる費用は、消費税の控除対象にならず、節税効果がありません。
一方、人材派遣を利用すると、派遣会社に支払う費用に消費税が含まれるため、その分を控除できます。同じ金額を支出しても、税務上の扱いが変わるのがポイントです。
人材派遣なら、社会保険の手続きなども派遣会社が対応するため、手間も省けます。短期間の業務や専門職の起用など、柔軟な活用がしやすい点も魅力です。
コストを抑えながら業務をまわしたいときに、有効な選択肢になるでしょう。
⑤仮決算で中間納付額を調整する
法人は、前年の税額が一定金額を超えた場合、中間申告をする必要があります。このとき、仮決算での納付を選択することで、中間納付額を調整できる可能性があります。
中間申告とは、事業年度の途中で税の一部を納付する制度で、言い換えれば「税の前払制度」です。納付方法には「予定納税」と「仮決算」の2つがあります。
予定納税は前年の納税額の半分を納めますが、仮決算は期の前半6ヶ月間の売上から中間納付額を計算します。
つまり、当期前半の売上が低調だった場合、仮決算によって中間納付額を下げられる可能性があるということです。
最終的な納税額は事業年度の終わりに確定するため、トータルでの納税額は変わりませんが、期中の資金繰りが楽になるというメリットがあります。
※仮決算で算出した納税額が予定納税での税額を超える場合、仮決算は選択できません。
⑥課税売上割合を意識した仕入れを行う
法人が支払った仕入れや経費の消費税は、原則として後から差し引いて納税額を減らす「仕入税額控除」ができます。ただし、すべての支払消費税を控除できるわけではなく、課税売上割合に応じて控除できる範囲が制限されてしまいます。
課税売上割合が95%以上であれば、支払った消費税は原則すべて控除できます。逆に言えば、それを下回ると一部しか控除できません。
そのため、課税売上割合が95%を下回らないよう、売上と仕入れのタイミングや内容を工夫することが、消費税の節税につながります。
また、非課税売上が単発的に多くなってしまった年でも、一定の条件を満たせば「課税売上割合に準ずる割合」という特例により、過去の課税売上割合に近い数値に申告できる場合があります。
⑦設備投資のタイミングを調整する
前に説明した「課税売上割合」の仕組みをふまえると、設備投資のタイミングが節税に大きく影響することがわかります。
課税売上割合が95%以上であれば、設備購入時に支払った消費税は原則すべて控除できるため、税負担を抑えることが可能です。
とくに、大口の設備投資を検討する場合は、課税売上割合が高い時期を狙って購入すると、節税効果を最大化できます。
少し時期を調整するだけでも、手元に残る資金に大きな違いが出るため、売上や非課税取引の見込みを意識して、計画的にタイミングを決めましょう。
消費税の節税を成功させるためのポイントと注意点
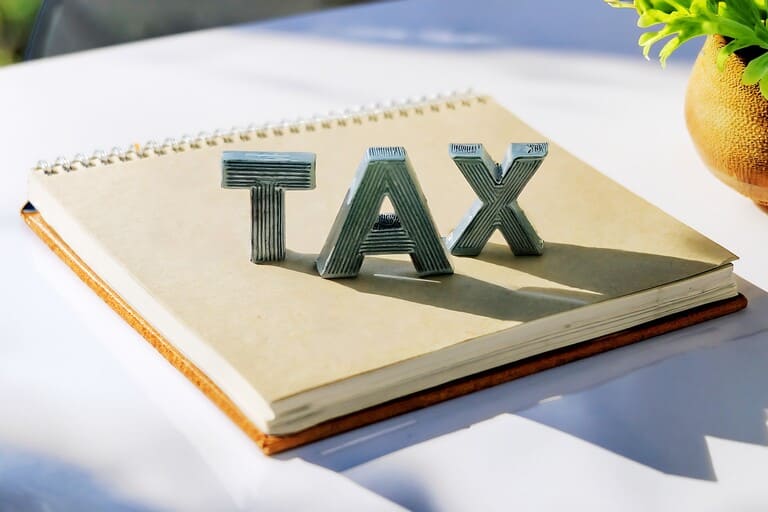
消費税は法人経営において無視できない負担ですが、正しい知識と対策があれば節税が可能です。
ここでは、消費税の節税を成功させるために押さえておきたいポイントと、見落としがちな注意点について解説します。
制度変更や法改正の動向を常にチェックする
消費税の制度は、数年おきに見直されており、ルールが変わることで節税の方法や納税額も影響を受けます。無駄な出費を避けるためにも、最新の情報を把握しておくことが大切です。
最近では、インボイス制度の導入により、仕入税額控除の条件が変更されました。さらに、課税・非課税の範囲が見直されることもあります。
制度改正に気づかずに従来の処理を続けてしまうと、本来なら控除できた税額を失ったり、場合によっては追徴課税を受けるリスクも出てきます。
日ごろから税務署や国税庁の情報を確認するほか、必要に応じて専門家に相談できる体制を整えておくと安心です。
一時的な節税ではなく中長期的な視点で考える
節税を考えるときに忘れてはならないのが、中長期の視点です。目の前の税額を減らすことだけにとらわれていると、将来的に思わぬ負担が生じることもあります。
たとえば、法人を新たに設立すると、初年度と2年目は消費税の納税義務が免除されます。免税期間中はキャッシュが手元に残りやすい点がメリットですが、3年目以降は一気に納税額が増え、経営上の大きな負担になるかもしれません。
また、設備投資の時期によっても納税額が大きく変動します。ある年度に利益と投資が集中すると、節税にはなるものの、翌年の経営バランスを崩してしまう可能性もあります。
事業の将来性や制度の変化も見据えながら、長期的にバランスの取れた節税戦略を立てることが大切です。
グレーな節税はリスクが高い
消費税には細かいルールが多く、ケースバイケースで判断が分かれるケースもあります。「おそらく大丈夫」といった曖昧な判断で処理を進めると、後になって問題になるかもしれません。
本来課税対象となるサービスを非課税として処理したり、私的な支出を経費として申告して仕入税額控除を受けるといった行為は、税務調査で指摘されるリスクがあります。
税理士など専門家の意見を聞き、制度の正しい理解と確実な対応を取ることが、余計なトラブルを避けるためには大切です。
まとめ

今回は、法人が実践できる消費税の節税対策について、具体的な方法と注意点をご紹介しました。
簡易課税制度や法人成りによる免税期間の活用、外注費や派遣社員の使い方など、工夫次第で節税につながる選択肢は多くあります。
ただし、制度は複雑で変更も多いため、自己判断はリスクをともないます。自社の状況にあった方法を選ぶためにも、税理士などの専門家に相談しながら、計画的に進めることをおすすめします。
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス

- 法人保険を経営に活用したい
- いま加入している保険を見直したい
- 退職金制度や福利厚生を導入したい
- 事業承継や相続について考えたい
- 税金対策や財務戦略を相談したい
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて
"無料"で貴社に最適な保険プランを提案します。




















