
法人経営において、節税は避けられない課題の1つです。どうやって税金を減らすか、日々頭を悩ませている経営者は多いでしょう。
法人にかかる税金を節税すれば、その分を企業の成長や防衛に資金を回せます。適切な節税対策を講じ、資金を有効活用することが大切です。
そこで本記事では、法人にかかる税と代表的な節税方法、最新の税制改正情報まで詳しく解説します。
仕組みから具体的な対策まで知りたい方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
法人が支払う税とは?

法人が支払う税としては、主に2つが挙げられます。
- 法人税
- 消費税
どちらも決算に伴って納めるため、合わせて仕組みを理解しておきましょう。
①法人税
法人税とは、企業の利益に対して課される税金を指します。
申告および納税は事業年度ごとに行い、決算日の翌日から2か月以内が期限です。
課税所得は「益金 – 損金」に基づいて算出され、そこに税率を掛け、控除額を差し引いた金額が税額となります。
税率は原則として23.2%ですが、資本金1億円以下の中小法人に対しては、課税所得800万円以下の部分に軽減税率が適用されます。
さらに、法人に課される税金は法人税だけでなく、地方法人税や法人住民税など複数存在します。これらを合計したものを実効税率と呼び、地域差はあるもののおおむね30%程度です。
| 税目 | 税の区分 | 税率 |
|---|---|---|
| 法人税 | 国税 | 23.20% ※中小法人は年800万円以下の部分まで15% |
| 地方法人税 | 国税 | 2.39% ※法人税額に10.3%を掛けた金額(23.2% × 10.3%) |
| 法人住民税(法人税割) | 地方税 | 自治体による |
| 法人事業税 | 地方税 | 自治体による |
| 特別法人事業税 | 地方税 | 自治体による |
※税率はいずれも2025年時点のものです。
②消費税
消費税は、商品やサービスの取引に対して課される税金であり、法人も事業活動を通じて納税義務を負います。
原則として、基準期間(2期前)の課税売上高が1,000万円を超える法人が課税事業者に該当します。さらに、特定期間(1期前の前半6か月)の課税売上高が1,000万円を超える場合も、課税事業者として扱われます。
納税額は、売上時に受け取った消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を差し引いた金額です。
法人税と同様、申告と納税は事業年度ごとに行い、決算日の翌日から2か月以内が期限となります。
税率は原則10%(軽減税率8%)ですが、輸出取引など一部の取引は非課税または免税として扱われます。
法人税の節税対策5つ

法人税の対策方法には様々なものがあり、経営状況や事業内容によって適切なものは異なります。
ここでは、主な対策方法として以下の4つを紹介します。
- 経費計上を活用する
- 減価償却を活用する
- 役員報酬と退職金を活用する
- 法人向けの税制優遇措置を活用する
- 中小法人向けの税制優遇措置を活用する
①経費計上を活用する
会社の事業運営に関わる支出を経費計上し、課税所得を減らすことで法人税を軽減できます。
以下は、経費精算で使える勘定科目の一例です。
- 福利厚生費(従業員の健康診断や社内イベントの費用)
- 研修費(従業員のスキルアップのための費用)
- 交際費(取引先との飲食費や贈答品費用)
- 旅費交通費(移動費、宿泊代、日当など)
- 会議費(社内会議や取引先との打ち合わせにかかった費用)
- 消耗品費(10万円未満の備品や什器など)
- 減価償却費※後述
- 人件費※後述
- 保険料※後述
1つひとつの金額が少なくても、漏れなく適切に計上することが大切です。
②減価償却を活用する
減価償却とは、建物や機械など「時間経過によって価値が減る資産」を、使用可能期間(法定耐用年数)に分割して経費計上する制度です。
例えば、500万円の資産で法定耐用年数が10年の場合、年50万円を10年間計上します。
高額かつ法定耐用年数が短い資産を購入すれば、当面の課税所得を大幅に減らせます。
また、以下のように特例を使えば、より柔軟に経費計上が可能です。
- 少額減価償却資産…10万円以上30万円未満の資産を一括償却(年間最大300万円)
- 特別償却・即時償却…特定の企業や設備投資について、初年度に30%もしくは全額を償却
③人件費を活用する
人件費は、人を雇うことで生じる費用全般を指します。具体的には、給与や役員報酬、退職金などです。
活用方法としては、以下のような例が挙げられます。
- 決算賞与の支給…決算月の売上状況に応じて支給し、所得税額を減額
- 退職金の支給、役員報酬の増額…高額な損金計上により所得税額を減額
- 従業員給与の増額…一定の増額で税額控除(賃上げ促進税制)
適切な範囲で人件費を増やせば、節税だけでなく役員や従業員のモチベーションアップも可能です。
④保険を活用する
法人保険の保険料や一定の共済掛金は、一部~全額を損金として計上できます。
- 法人保険(生命保険、損害保険、第三分野の保険)…10%~全額を損金計上(保険の種類や加入状況によって異なる)
- 中小企業倒産防止共済(セーフティ共済)、中小企業倒産防止共済など…全額損金計上
ただし、保険や共済の目的はあくまで保障なので、損金計上による税効果は副次的なものと考えましょう。
⑤中小法人向けの税制優遇措置を活用する
中小法人(資本金1億円以下の法人)には様々な優遇措置があるため、自社に適用できるものは積極的に活用しましょう。
以下は、主な税制優遇措置の一例です(ここまでに紹介したものも一部含みます)。
- 法人税率の軽減…中小法人は年800万円以下の部分まで15%
- 欠損金の繰越…赤字を最大10年まで繰り越せる
- 研究開発税制(中小企業技術基盤強化税制)…研究開発費の一定割合を法人税から控除
優遇措置は期限が決まっているものも多いため、常に最新の税制をチェックするようにしましょう。
消費税の節税対策

消費税の節税方法は、新規設立法人や売上が少ない法人に優遇措置があります。
代表的な例として、以下の3つを紹介します。
- 2年間の免税期間を活用する(新規設立法人)
- 簡易課税制度を利用する
- 期末のタイミングで設備投資を行う
①2年間の免税期間を活用する(新規設立法人)
法人を設立した場合、資本金が1,000万円未満であれば設立後2年間は消費税の納税が免除されます。
設立後2期目まで納税が免除されることで、事業が軌道に乗るまでの資金繰りが楽になります。
②簡易課税制度を利用する
簡易課税制度は、基準期間(前々事業年度)の売上高が5,000万円以下の法人が選択できる制度です。
仕入れにかかる消費税の計算を簡素化し、みなし仕入率での申告・納税ができます。
| 業種 | みなし仕入率 |
|---|---|
| 第一種(卸売業) | 90% |
| 第二種(小売業) | 80% |
| 第三種(製造業・建設業など) | 70% |
| 第四種(飲食店・運輸業など) | 60% |
| 第五種(サービス業・コンサル業など) | 50% |
| 第六種(不動産業) | 40% |
仕入れや経費が少ない業種(サービス業・コンサル業など)の場合、実際の仕入れにかかる消費税より控除額が大きくなり、節税につながるケースがあります。
ただし、製造業など仕入れや経費が多い業種は、かえって不利になる可能性もあります。また、一度選択すると2年間は変更できない点も注意しましょう。
③設備投資で消費税の還付を受ける
多額の設備投資により、預かった消費税より支払った消費税を多くすることで還付を受けるというテクニックがあります。
例えば、受け取った消費税が300万円、支払った200万円の場合、差し引き100万円の納税が必要です。
ここで1,500万円の設備投資を行えば、支払った税額は「200万円+150万円=350万円」となるため、受け取った消費税との差額50万円が還付されます。
ただし、簡易課税制度を選択している場合は支払った消費税のほうが多くなるため、この方法は使えません。
法人が節税相談するならどこがいい?
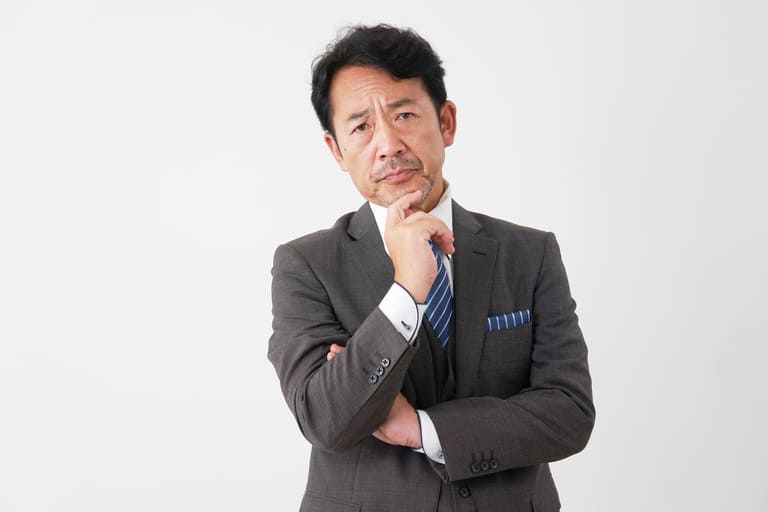
法人の節税対策は、事業内容や経営状況によって最適な方法が異なります。
誤った節税対策を行うと、税務調査の対象となるリスクや、資金繰りの悪化を招く可能性があります。
そのため、適切な節税対策を講じるためには、専門家に相談するのが最も確実な方法です。
ここでは、法人が節税について相談できる代表的な専門家を紹介します。
税理士
税理士は、法人税や消費税などの税務に関するプロフェッショナルです。
具体的な節税対策のアドバイスや、税務書類の作成、税務代理などを依頼できます。
節税をしつつ、違法にならない適切な税務処理をしてほしい場合は、税理士への相談が適しています。
ファイナンシャルプランナー
法人専門のファイナンシャルプランナーは、財務や資産運用、事業承継、相続対策などを総合的にアドバイスする専門家です。
法人の財務戦略やオーナー経営者のライフプランに沿った提案ができます。
ただし、節税については一般論の説明までしかできず、税理士のように具体的な対策や税務代理はできません。
節税や税務などピンポイントで頼りたいなら税理士、財務や個人資産に関する幅広い相談はファイナンシャルプランナーを活用するとよいでしょう。
まとめ

法人経営において、節税は企業の資金繰りや成長に大きく影響する重要な課題です。適切な節税対策を講じることで、納税額を最適化し、浮いた資金を事業拡大やリスク管理に活用できます。
経費計上や減価償却など様々な対策がありますが、自社の状況に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。また、誤った節税対策は税務調査のリスクを高めるため、税理士やファイナンシャルプランナーといった専門家に相談することが、安全かつ効果的な節税のカギとなります。
節税は単なるコスト削減ではなく、企業の健全な財務戦略の一環です。自社の状況に合わせた最適な節税対策を実践し、企業の成長と安定経営を実現しましょう。
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス

- 法人保険を経営に活用したい
- いま加入している保険を見直したい
- 退職金制度や福利厚生を導入したい
- 事業承継や相続について考えたい
- 税金対策や財務戦略を相談したい
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて
"無料"で貴社に最適な保険プランを提案します。



















