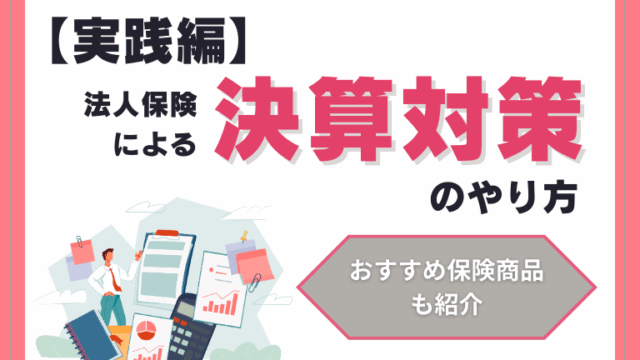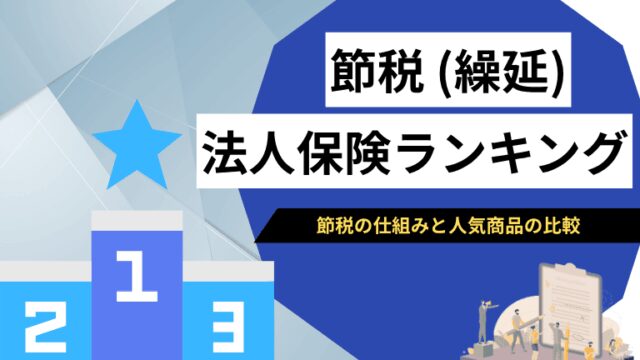法人保険の経理処理は複雑で、契約形態によっては保険料が給与扱いになる可能性があります。
給与扱いは企業側と個人側(被保険者である役員や従業員)の両方にデメリットがあるため、注意が必要です。
この記事では、法人保険が給与扱いになるケースと具体的なデメリットを解説します。
給与課税を避けるための対策をお伝えするので、法人保険を契約する前にぜひご確認ください。
法人保険の保険料が給与扱いになるケース

法人保険の保険料は、保険の種類や契約形態によって経理処理が変わります。
基本的には「資産計上」か「損金算入」かの2種類に分けられ、さらに税務上の取り扱いによって「保険積立金」や「給与」などの勘定科目に分類されます。
| 経理処理の分類 | 勘定科目 |
|---|---|
| 資産計上 | 保険積立金、長期前払費用 |
| 損金算入 | 支払保険料、福利厚生費、給与 |
給与扱いになり得る法人保険は、主に定期保険(定期生命保険)と養老保険です。
これらの経理処理パターンをおおまかに分類すると、以下のようになります。
法人保険の税務上の取り扱いパターン
横スクロールできます →
| 保険の種類 | 受取人 | 法人側の処理(保険料支払時) | 個人側の課税関係(保険料支払時) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 定期保険 (死亡保障のみ) | 被保険者またはその遺族 | 全額損金(給与) | 給与所得として課税 | 福利厚生要件を満たさない場合。 |
| 全額損金(福利厚生費) | 非課税 | 全従業員対象など福利厚生要件を満たす場合。 | ||
| 養老保険 (死亡・満期あり) | 死亡:遺族生存(満期):被保険者 | 全額損金(給与) | 給与所得として課税 | いわゆる「総合福祉団体定期保険」で、福利厚生の要件を満たさない場合。 |
| 死亡:法人生存(満期):被保険者 | 保険料の1/2が損金(給与)保険料の1/2が資産計上 | 生存保険金相当額が給与所得として課税 | いわゆる「ハーフタックス」で、満期保険金部分が個人に給与課税。 |
上記表から「法人保険の保険料が給与扱いになり得るケース」を抜き出すと、以下の2つが挙げられます。
- 定期保険で受取人が被保険者および遺族の場合
- 養老保険で受取人に被保険者および遺族がいる場合
①定期保険で受取人が被保険者および遺族の場合
定期保険の場合、被保険者またはその遺族が保険金受取人だと給与扱いになります。
保険金が直接被保険者(またはその遺族)に支払われるということは、「個人の利益のために企業がコスト(保険料)を負担している」とみなされます。
言い換えれば、企業から個人へ資産を譲渡しており、給与と同じ性質を持つため全額給与扱いとなります。
ただし、後述する福利厚生要件を満たす場合、福利厚生費として処理されるため、給与扱いにはなりません。
②養老保険で受取人に被保険者および遺族がいる場合
養老保険の場合、死亡保険金と満期保険金(生存保険金)があり、それぞれの受取人が誰になるかがポイントです。
死亡保険金・満期保険金の両方で受取人が被保険者(遺族)の場合、必ず個人側が受取人となるため、保険料全額が給与扱いとなります。
一方、死亡保険金が法人、満期保険金が被保険者の受取となっている場合、半額のみ給与扱いとなります。これは、「死亡・満期保険金のうち片方しか受け取れない=受取割合が2分の1」とみなせるためです。
【例外】実質的に給与や退職金の補填とみなされるケースに注意
ここまで解説した①②のケースにあてはまらなくても、実質的な給与や退職金の補填とみなされると給与扱いとなり得ます。
具体的には、「法人契約の生命保険を個人に低額または無償で譲渡する場合」や、「保険料が役員の貢献度や報酬体系と著しく乖離している場合」などのケースです。
例えば、年収600万円の役員に対して、年1,000万円の保険料を掛けていれば、報酬体系とのバランスが崩れているといえます。
このように「特定個人への利益供与」が認められる場合、税務調査で経理処理が否認され、給与扱いとなる可能性があります。
法人保険を給与扱いで計上するデメリット

法人保険の保険料が給与扱いになると、具体的にどのようなデメリットがあるのでしょうか?
ここでは「個人」と「法人」の視点から、それぞれのデメリットについて見てみましょう。
個人側:税金や社会保険料の算定対象となる
法人保険が給与扱いになると、保険料が所得税・住民税や社会保険料の算定対象になり、手取り額が減少します。
例えば会社が年間100万円の保険料を支払っていた場合、課税所得に100万円が上乗せされます。つまり、給与額は変わらないのに控除額が増えてしまうのです。
手取り額は日々の生活に直結するため、給与扱いにすることで家計が苦しくなる可能性があります。
法人側:社会保険料の会社負担分が増える
企業側にとっても、給与扱いは費用面の負担が生じます。なぜなら、社会保険料は企業も半額負担する義務があるためです。
1人あたりの課税所得が年間100万円増えれば、社会保険料の負担額は10万円前後増加します。これが10人、50人と増えれば、決して無視できない負担です。
給与自体は損金算入できますが、人が増えれば増えるほど企業側の負担も増加してしまいます。
給与課税を避けるための対策
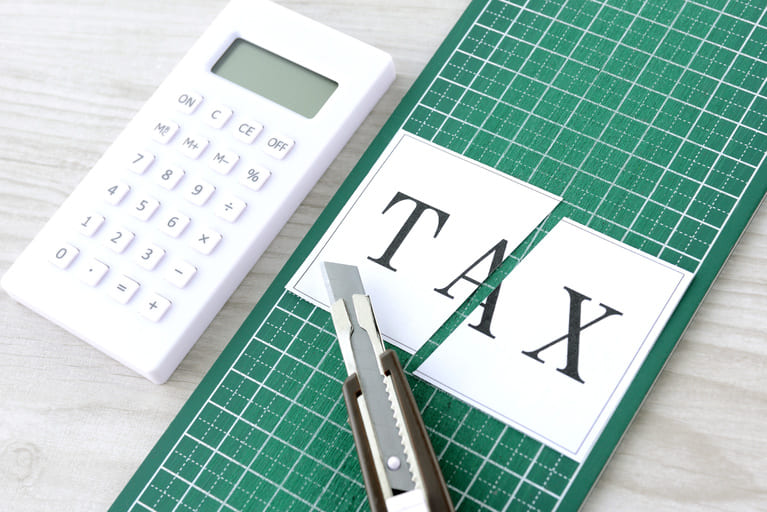
給与課税を避けるための対策はいくつかあります。
対策をしっかりと実践して、正しく節税しながら税務リスクを回避しましょう。
福利厚生費の要件を満たす
法人保険では以下のような福利厚生費の要件を満たすことで、給与扱いを回避できます。
- 全役員・全従業員を保険の対象者にする(パート・アルバイトは除いても可)
- 役職を限定したり役職ごとに支払い金額を変えたりしない
- 新規入社の従業員は入社後に加入し、退職者は退職時に契約を解約する
- 持病などで加入できない人は他の保険商品で代用する
- 福利厚生規定を整備する
福利厚生規定には、法人保険における労使間のトラブルを避けるためのルールを規定します。具体的には、被保険者の範囲や保険金額、退職時の取扱いなどです。
節税目的のみで契約しない
税務調査で「実質的な給与」とみなされないように、節税目的以外での契約態様を整えることが重要です。
役員死亡時の事業資金を確保するためなど、「なぜこの保険が必要なのか」を明確に説明できるようにしましょう。
そもそも、法人保険による節税は副次的な効果であり、本来の目的ではありません。事業保障や資産形成など、保険本来の機能を活用した制度を設計しましょう。
給与扱いを避けるためのプラン設計は「専門家に相談」がおすすめ
給与扱いを避けるためのプラン設計は、専門家へ相談するのがおすすめです。
法人保険に関する税務は非常に複雑で、商品選定や税務リスクはきちんと回避する必要があります。
プラン設計を間違うと、節税や福利厚生を正しく活用できません。
自社に最適な法人保険を見極めるためにも、法人分野に強いFPなど、法人保険のプロに相談してみましょう。
まとめ

今回は、法人保険の保険料が給与扱いになるケースとして以下の2つを紹介しました。
- 定期保険で受取人が被保険者および遺族の場合
- 養老保険で受取人に被保険者および遺族がいる場合
会社としては法人保険を給与扱いで計上すると、社会保険料の負担が増加するので注意が必要です。
自社に適した法人保険に加入して正しく活用するためにも、一度専門家に相談することをおすすめします。
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス

- 法人保険を経営に活用したい
- いま加入している保険を見直したい
- 退職金制度や福利厚生を導入したい
- 事業承継や相続について考えたい
- 税金対策や財務戦略を相談したい
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて
"無料"で貴社に最適な保険プランを提案します。