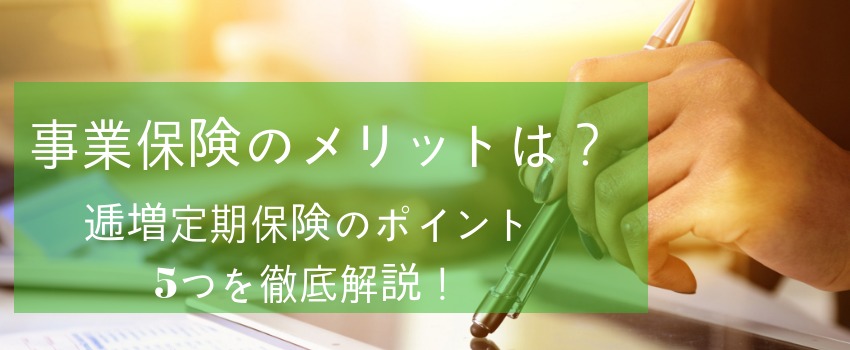退職金の準備や事業承継、節税といった目的で、養老保険を法人で契約するケースが増えてきています。
法人が契約する保険の中でも、養老保険には「万が一への備え」と「将来の資金準備」を同時に進められるという特徴があります。
ただし、契約内容によっては税務処理や経理上の扱いが大きく変わるため、法人としての契約にあたっては、あらかじめ仕組みを理解しておくことが大切です。
この記事では、「退職金の準備や節税を考えて養老保険の法人契約を検討しているけれど、税務処理が複雑で不安…」そんな経営者の方に向けて、法人で養老保険を活用する際の仕組みや契約形態を解説します。
具体的な使い方や注意点を紹介するので、導入前に押さえておきたい基本事項を整理しておきましょう。
養老保険とは?法人契約の仕組みをわかりやすく解説

まずは、法人が契約する養老保険の仕組みと、押さえておきたい基本的なポイントを整理しましょう。
養老保険の基本的な仕組み
養老保険は、「満期まで生きていれば保険金が支払われる」「万が一、途中で亡くなっても保障される」といった仕組みの保険です。老後資金と死亡保障を同時に備えられる点が特徴です。
保険期間は、10年や15年などの「年数指定型」や、60歳・70歳までの「年齢指定型」があり、期間が終わると契約も終了します。
保険金の支払いは以下のどちらかになります。
- 保険期間中に亡くなった場合:死亡保険金
- 満期まで生存していた場合:満期保険金
いずれも、同額が支払われる契約が一般的です。契約によっては、高度障害になった場合にも保険金が支払われることがあります。
途中解約をすると解約返戻金が受け取れますが、多くの場合は支払った保険料の総額より少なくなります。
養老保険は、定期保険と比べて保険料がやや高めですが、法人の資金計画に合わせて老後資金や死亡保障をまとめて準備できるため、経営者にとって有力な選択肢です。
法人契約する場合の構成(契約者・被保険者・受取人)
法人が養老保険を契約する際は、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって、保険料の処理や税金の扱いが大きく変わります。
よく使われる3つのパターンは、以下の通りです。
| 受取人のパターン | 死亡保険金の受取人 | 満期保険金の受取人 | 被保険者 |
|---|---|---|---|
| パターンA | 法人 | 法人 | 全額を資産に計上(経費にならない) |
| パターンB | 遺族 | 法人 | 給与として扱われ、受取人に課税される |
| パターンC | 遺族 | 法人 | 半額を資産、半額を経費に計上(内容により給与課税の可能性あり) |
医療特約や傷害特約が付いている場合、その保険料も給与と判断される可能性があります。
とくに役員を対象とする場合は、「定期同額給与」のルールを守っていないと経費にできなくなるため、注意が必要です。
定期保険との違いと養老保険の特徴
養老保険は、死亡保障と老後資金の準備をセットにした保険です。定期保険や終身保険と比べると、次のような違いがあります。
定期保険との違いは、満期金があるかどうかです。養老保険では満期まで生存すれば保険金を受け取れますが、定期保険は死亡時しか保障されず、満期金はありません。掛け捨てかどうかが大きな違いです。
終身保険との違いは、保障期間です。終身保険は一生涯の保障がありますが、養老保険は一定期間のみ。ただし、満期金を計画的に活用できるというメリットがあります。
法人契約での主な利用目的は次の通りです。
- 役員の退職金準備
- 福利厚生制度としての導入
- 事業承継や資金繰りへの備え
一方で、保険料が高めな点、解約返戻金が少ない点、税制改正の影響を受けやすい点には注意が必要です。
法人が養老保険を活用するメリット

法人が養老保険に加入すると、退職金の準備や人材の確保、万が一の資金調達、税負担の軽減など、経営面で多くの効果が期待できます。
- 役員や従業員の退職金を計画的に準備できる
- 福利厚生として人材の定着・採用につながる
- いざというときに契約者貸付で資金調達できる
- 条件を満たせば保険料の一部を損金処理できる
ここでは、それぞれのメリットをわかりやすく紹介していきます。
役員や従業員の退職金を計画的に準備できる
養老保険を使えば、退職金の支払いに備えて定期的に資金を積み立てられます。毎月の保険料を通じて、満期時には退職金の原資を用意できる仕組みです。
複数の従業員が同時に退職した場合、現金での対応だと資金繰りが苦しくなることもありますが、保険を活用すればまとまった金額を受け取れます。
また、急な退職があった場合でも、解約返戻金を使えばある程度の柔軟な対応が可能です。
退職金にかかる支出を平準化できる点は、企業にとってのリスク軽減につながります。
福利厚生として人材の定着・採用につながる
福利厚生が充実している職場は、優秀な人材が集まりやすく、離職率も下がる傾向にあります。養老保険を使った退職金制度は、その一環として活用できます。
就職先を選ぶ際に「退職金制度あり」と記載されていると、会社に対する信頼感も高まりやすくなります。
働いている従業員にとっても、将来への備えがあるという安心感は日々のモチベーションにもつながります。
制度を通じて「人を大切にする姿勢」が伝わることは、組織づくりにも好影響を与えるでしょう。
いざというときに契約者貸付で資金調達できる
養老保険には「契約者貸付制度」があり、急な出費が必要な場面で保険を解約せずに現金を借りられます。
貸付の上限は、解約返戻金の7割~9割程度が目安です。審査なしで利用でき、金利も一般的なローンより低く設定されています。
たとえば、急に設備が壊れた場合や、一時的な運転資金が必要になったときに、銀行融資より早く現金を用意できる手段として使えます。
ただし、借りたお金を返済しないと保険金が減るため、使う際は返済計画を立てて活用することが大切です。
条件次第で損金算入ができ、節税効果がある
養老保険を法人で契約した場合、保険料のうち一定割合(一般的に50%)を損金として計上できるケースがあります。
この仕組みは、保険料の半分を経費にできることから「ハーフタックスプラン」とも呼ばれ、単に資金を積み立てるよりも税制面で有利な方法とされています。
ただし、全従業員を対象にしていることや、あらかじめ社内規定を整えておくことが条件です。特定の役員や社員だけに適用した場合は、経費として認められない可能性があります。
条件を守ってうまく使えば、福利厚生の充実と節税の両方に役立ちます。会社の資金の使い方としても、選択肢のひとつになるでしょう。
養老保険を法人契約する際に気をつけたいポイント

法人で養老保険に加入する際は、税務上の取り扱いや契約の内容によって、経営への影響が大きく変わってきます。
ここでは、契約時に特に注意したい5つのポイントを紹介します。
法人保険の導入を検討している方は、ここで挙げた内容を参考にして、自社に合った判断材料として役立ててください。
保険の目的や受取人によっては課税されることがある
養老保険では、誰が保険金を受け取るかで税務の取り扱いが変わります。
たとえば、法人が死亡保険金や満期保険金の両方を受け取る場合、保険料は資産として計上され、損金にできるのは契約終了時です。
一方で、受取人が従業員本人や遺族になると、保険料は給与とみなされ課税対象になることがあります。
こうした税務処理のバランスを考えて設計されているのが、前述の「ハーフタックスプラン」です。この方法では、死亡保険金と満期保険金の受取人を分けることで、保険料の一部(通常は2分の1)を損金として扱うことができます。
契約内容によって税負担は大きく変わるため、制度の仕組みをよく理解したうえで、契約前に税理士などに相談しておくと安心です。
経営者のみの加入は給与課税のリスクがある
法人が養老保険を福利厚生として導入する場合、対象が社長や一部の役員に限られていると、福利厚生費とは認められず、保険料全額が給与課税の対象とされる可能性があります。
福利厚生と認められるには、「全従業員を対象とする制度」であることが原則であり、加入の範囲が合理的な基準(年齢・勤続年数など)に基づいている必要があります。
特定の役職者に限定するような設計は、福利厚生とは見なされず、税務署から否認されるリスクがあるため注意が必要です。
途中解約すると損をすることもある
養老保険は、満期まで契約を続けることを前提に設計されています。途中で解約すると、返戻金が払込保険料を下回り、元本割れになる場合があります。
とくに契約から数年以内に解約すると、返戻率が低く、元本割れになる可能性があります。
人事異動や退職などで契約を見直す際は、返戻率や課税リスクといった点にも注意が必要です。
また、返戻金が利益として課税対象になることもあります。もしも資金が必要になった場合は、すぐに解約するのではなく「契約者貸付制度」を活用するのも一つの方法です。
保険契約が資金繰りに与える影響
法人契約の養老保険では、保険料の支払いが会社の資金繰りに影響を与えることがあります。
一時払いの場合はまとまった資金が必要になり、分割払いでも毎年一定の出費が発生します。契約内容によっては、会計処理や税の扱いも異なります。
また、解約返戻金に課税が発生するケースもあるため、キャッシュフローの見通しを立てたうえで、契約方法を慎重に検討することが重要です。
返戻率や契約設計の柔軟性には差がある
養老保険の商品は保険会社ごとに特徴があり、返戻率や設計の柔軟さにも差があります。
たとえば、同じ契約年数でも、ある商品では5年目に返戻率が90%を超えることもあれば、別の商品では時間がかかることもあります。
また、死亡保障と満期金のバランス、特約の有無などにも違いがあります。
福利厚生として導入する場合は、保険料の払込方法や対象者の条件などもチェックしておきましょう。
FAQ(よくある質問)

Q1. 養老保険は法人契約にすると節税になりますか?
A. 一部の契約形態では、保険料のうち一定割合(主に50%)を損金処理できるため、税金の繰延や負担の均一化に役立ちます。ただし、保険金や返戻金の受取時に課税されるため、永久的に税負担をなくせるわけではありません。
Q2. 経営者(社長)だけが加入する養老保険は経費になりますか?
A. 原則として、経営者のみが加入する保険は福利厚生費と認められず、保険料が給与として課税対象となる可能性が高いです。経費処理をするには、全従業員を対象とした制度であることが基本条件です。
Q3. 養老保険を途中解約したらどうなりますか?
A. 途中で解約すると、元本割れする可能性があり、受け取る解約返戻金も課税対象となる場合があります。特に契約初期は返戻率が低いため、損をするリスクがあることを理解したうえで検討する必要があります。急な資金需要がある場合は、まず契約者貸付制度の利用も検討しましょう。
まとめ

今回は、法人契約で活用される養老保険について、その基本的な仕組みや契約パターンごとの違い、具体的な活用例までをご紹介しました。
養老保険は、法人の退職金準備や福利厚生、さらには資金繰り対策としても幅広く活用されていますが、契約内容によって税金の扱いや経理処理が大きく異なる点に注意が必要です。
活用の幅が広い反面、制度の理解があいまいなままだと、思わぬ税務リスクにつながることもあります。導入前には、目的に合った設計になっているか、あらためて確認しておくと安心です。
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス

- 法人保険を経営に活用したい
- いま加入している保険を見直したい
- 退職金制度や福利厚生を導入したい
- 事業承継や相続について考えたい
- 税金対策や財務戦略を相談したい
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて
"無料"で貴社に最適な保険プランを提案します。