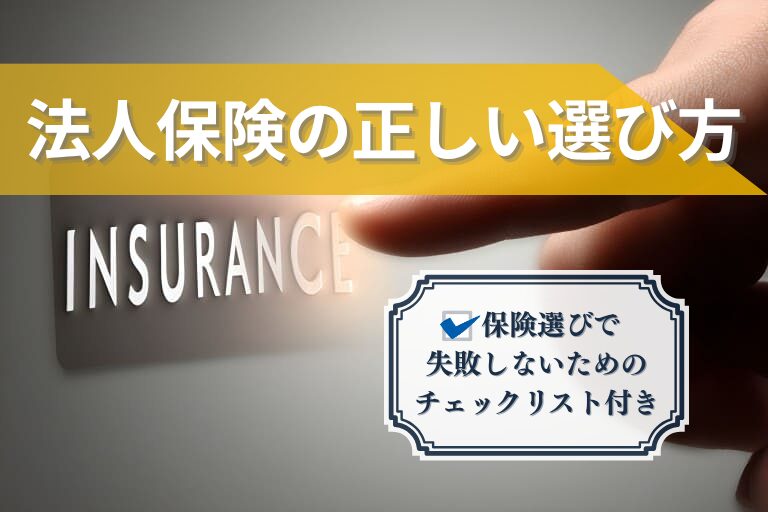役員向け法人保険は、社長・役員の退職金や死亡保障、事業承継まで幅広く活用できる経営支援ツールです。節税・資金準備・リスク対策の3要素を備え、企業にとって重要な選択肢となります。
しかし、損金処理のルールや会計処理の実務、税制対応は複雑で、解約返戻金や益金計上に関する注意が必要です。
本記事では、役員保険の基本的な仕組みやメリット、損金算入や税務処理の留意点、商品タイプとその選び方まで、実務視点で幅広く解説します。
ぜひ最後までお読みいただき、役員向け法人保険の導入・加入前の判断材料としてお役立てください。
役員向け法人保険とは?企業経営における導入目的と役割

役員向け法人保険とは、社長や取締役といった被保険者に対し、法人が契約者および保険料支払い主体となる保険を指します。
役員向け法人保険を導入する主な目的としては、以下の3つが挙げられます。
- 役員の退職金・勇退資金を積み立てる
- 死亡や傷病時の事業保障に使う
- 節税対策(課税の繰延)として活用する
①役員の退職金準備に使う
役員向け法人保険の中でも主流となる導入目的が、退職金準備としての契約です。
会社が解約返戻金や満期保険金のある生命保険に加入し、それらのお金を役員の勇退退職金や死亡退職金として活用します。また、解約せず保険契約を現物支給するケースもあります。
ただし、法人保険を役員退職金に使う場合は以下の点に留意が必要です。
- 返戻率ピークと資金ニーズとの整合性:
返戻率が最大になる時期を退職想定時期に合わせて契約設計し、最大効率で積立効果を得るようにします。 - 損金算入と会計処理:
支払保険料の一部は損金扱いとなりますが、その金額は返戻率区分によって異なります。経理部門での月次処理や税理士との連携が重要です。 - 経営者報酬との調整:
退職金と報酬の適正額は、会社規模や業界内相場も影響します。合理的金額に設定しないと、税務調査で否認されるリスクがあります。 - 賠償責任や健康リスクとの複合設計:
退職金支給のみならず、労災や疾病保障も組み合わせることで、万が一の役員リスクに対して包括的な制度設計が可能になります。
このように、複数の視点から慎重にプラン設計をしなければいけません。
②死亡や傷病時の事業保障に使う
法人保険は、死亡・傷病による役員の不在リスク対策としても有用です。
役員の不在リスクとしては、以下の例が挙げられます。
- キーパーソン不在による事業の停滞や信用低下
- 見舞金や福利費の負担
- 早急な代替人材の登用
- 相続や事業承継に伴う費用や税金資金
これらのリスクに対し、法人保険で対策することで資金面の負担をカバーできます。
実際にどの程度のリスクを想定するのが合理的かは、FPなど法人保険の専門家と相談しつつ検討しましょう。
③節税対策(課税の繰延)として活用する
保険料支払いによる税負担のコントロールも、法人保険のメリットです。
種類や契約内容にもよりますが、法人が支払った保険料は損金算入が可能であり、課税所得を圧縮できます。つまり、保険料を支払うことで当年度の節税が可能です。
保険金や返戻金の受取時には課税されるため、厳密にいえば課税の繰延(先送り)ですが、「貯蓄や保障を行いつつ税負担をコントロールする方法」として多くの企業が活用しています。
役員向け法人保険の損金算入のルール
役員向け法人保険で代表的な「長期平準定期保険」や「逓増定期保険」などは、損金算入ルールについて以下のように定められています。
| 最高解約返戻率 | 資産計上期間 | 資産計上額 | 取崩期間 |
|---|---|---|---|
| 50%以下 | なし | なし | なし |
| 50%超〜70%以下 | 保険期間開始日から40%を経過するまで | 保険料の40% | 保険期間の75%経過後から終了日まで |
| 70%超〜85%以下 | 保険期間開始日から40%を経過するまで | 保険料の60% | 保険期間の75%経過後から終了日まで |
| 85%超 | 次のいずれか長い期間まで ①保険期間開始日から最高解約返戻率となる期間の終了日まで ②①の期間経過後で「(当年の解約返戻金相当額-前年の解約返戻金相当額)÷年換算保険料相当額」が70%を超える期間 |
保険期間開始日から10年経過するまでは「保険料×最高解約返戻率の70%」、11年目以降は「保険料×最高解約返戻率の90%」 | 解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間経過後から保険期間終了日まで |
最高解約返戻率(もっとも解約返戻率が高くなるときの数値)ごとに区分され、50%超から「資産計上期間」が設けられます。期間中、保険料の一部は資産として計上しなければいけません(=課税所得から控除できない)。
資産計上分も、保険期間の後期に設定される「取り崩し期間」で損金に振り替えられますが、解約返戻率が高いほど節税(繰延)しにくくなるのは否定できません。
「貯蓄・保障・節税」の何を重視するかを定め、加入目的と税負担とのバランスを考えましょう。
役員向け法人保険の代表例

役員向けの法人保険は、目的に応じていくつかの「タイプ」が存在します。退職金準備を重視するか、死亡保障・医療保障を重視するかなど、目的によって選ぶべき保険の種類や契約形態は異なります。
3つの代表的な保険タイプを紹介するので、それぞれどのような役員・経営状況に向いているのか確認しましょう。
1. 長期平準定期保険
長期間の保険期間があり、保険金が一定(平準)な法人保険です。
有期型の保険でありながら、100歳まで保障が続く商品もあり、終身保険に近い運用ができます。
解約返戻率が高めに設定されており、貯蓄効果を重視する企業にもおすすめの役員向け法人保険です。
2. 逓増定期保険
保険金が年々増えていき、最大5倍程度になる法人保険です。役員の年齢や職責の上昇に合わせた保障を確保できます。
解約返戻率のピークが早く、5~10年程度で最高となるため、短期的な資産形成に向いています。
反面、タイミングを誤ると返戻金が急減するリスクがあり、解約時期の見極めに注意が必要です。
3. 医療保険・がん保険
役員の入院や手術などに備えられる法人保険です。保険金は見舞金資金や休業補償、当座の経営資金として機能します。
在任中の保障はもちろん、保険料を短期払いで支払い、退職時に役員個人へ名義変更して老後の保障を確保することもできます。ただし、名義変更は退職金もしくは給与として扱われるので、課税対象となる点に注意が必要です※。
※解約返戻金ありの場合は名義変更時の返戻金相当額、解約返戻金なしの場合は入院日額の10倍程度で評価。
4. 役員賠償責任保険(D&O保険)
役員賠償責任保険(D&O保険)は、役員の職務遂行中に発生した賠償責任を補償する法人保険です。
職務遂行上の過失や違法行為などにより、第三者(株主・取引先・従業員など)から損害賠償請求を受けた場合の賠償責任を補償します。訴訟リスクに備えられるほか、役員個人の賠償リスクを対策することで優秀な人材確保にもつながります。
まとめ

役員向け法人保険は、単に役員個人を守るだけでなく、会社経営の未来を支える「経営戦略の一部」として機能します。
退職金の準備や万一の死亡保障、医療・疾病対策、さらには税金対策まで、多くの目的を同時に実現できる強力な手段です。
反面、契約の設計ミスや税務処理の誤りは、会社にも役員個人にも大きなリスクをもたらします。特に損金算入の判断や返戻率のピーク、退職時の支給処理、契約者・受取人の設定などは慎重な検討が必要です。
大切なのは、「誰のために、何の目的で、どのタイミングで使うか」という視点を持ち、保険商品ごとの特徴と制度の仕組みを正しく理解することです。税理士やFPなど専門家の意見を取り入れ、自社に合った保障プランを設計しましょう。
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス

- 法人保険を経営に活用したい
- いま加入している保険を見直したい
- 退職金制度や福利厚生を導入したい
- 事業承継や相続について考えたい
- 税金対策や財務戦略を相談したい
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて
"無料"で貴社に最適な保険プランを提案します。