
事業を運営するうえで、効果的な節税対策を実践し、税金の負担を少しでも減らしたいと考える方は多いでしょう。
「なるべく賢く節税しながら、事業の成長にもつなげたい」という方におすすめなのが、法人化による節税対策です。
個人事業主としての税金の仕組みを見直し、法人化することでどのような節税効果が期待できるのかを理解すれば、事業の将来設計にも役立つはずです。
今回は、法人化による節税効果を、所得税との違いや具体的なメリットを共に詳しく解説します。
ぜひこの記事の内容を節税に役立てていただければ幸いです。
法人化すると節税効果があるといわれる2つの理由
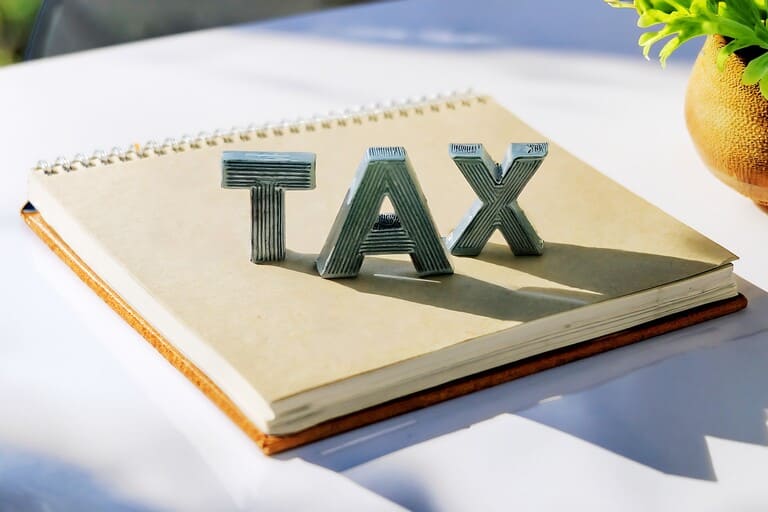
法人化が節税に有効と言われるのは、個人事業主より税制上の優遇を受けられる仕組みがいくつもあるからです。
ここでは、法人化によって得られる主な2つの節税効果について解説します。
理由① 法人化することで税率が下がる場合がある
法人化が節税につながるといわれる理由の1つ目は、所得税よりも法人税の方が税率が低く場合があるからです。
個人事業主は、所得に応じて5%~45%の所得税がかかります。課税所得が4,000万円を超えると税率が45%となり、さらに住民税(10%+5,000円程度)も加わるため、稼いだ金額の半分以上を税金として支払うことになります。
一方、法人になると税金は法人税に変わります。
法人税の場合、税率は原則23.2%、資本金1億円以下の中小法人は所得800万円以下の部分まで15%となります。法人住民税などを含めても、法人の実質的な税負担は30%~35%程度です(自治体により異なる)。
例えば、所得税は課税所得が900万円を超えると43%程度(所得税+住民税)なので、法人のほうが負担は軽くなります。このように、一定の所得を超えた場合は法人化による節税効果が大きくなります。
理由② 経費として認められる範囲が広がる
法人化すると、個人事業主では経費にできない支出も計上できるようになります。法人が損金として認められる費用の例には、以下のようなものがあります。
- 交際費:取引先との飲食や接待にかかる費用
- 社宅費:法人が契約した社宅の家賃(一定割合を経費にできる)
- 一定の生命保険料:法人契約の生命保険の保険料
上記のほか、法人では代表者の給与を経費として計上できるため、課税所得を抑えることが可能です。
また、給与を支払うことで法人の利益を減らす仕組みがあるため、結果的に税負担を軽減できる場合があります。
このように、法人化することで経費の計上範囲が広がり、結果的に法人化による節税効果を最大限に活用しやすくなります。
法人化することで使える4つの節税メリット

法人化すると、個人事業主のままでは利用できない税制上のメリットを受けられます。ここでは、法人化による4つの節税メリットを紹介します。
- 役員報酬を活用して所得税を抑えられる
- 退職金を経費として計上できる
- 赤字を最大10年間繰り越せる
- 消費税の納税タイミングを遅らせられる
法人化を検討している方は、これらのメリットを理解して、自身の事業にとって最適な選択をしましょう。
役員報酬を活用して所得税を抑えられる
法人化して役員報酬を受け取ると、個人事業主よりも所得税の負担を軽くすることができます。
個人事業主の場合、年間の利益全額が課税対象となります。一方、法人化すると、自分自身に役員報酬を支払うことができ、その報酬が法人の経費(損金)となるため、法人の課税所得を減らすことが可能です。
例えば、年間800万円の利益が出た場合を考えてみましょう。
法人化して400万円を役員報酬として受け取ると、法人の課税所得は残りの400万円となり、法人税の負担が軽くなります。
また、役員報酬を受け取った個人側でも給与所得控除が適用されるため、個人として課税される金額も少なくなり、所得税をさらに抑えることができます。
このように、役員報酬を上手く活用することで、法人と個人の両方で所得税の節税が可能になります。
退職金を経費として計上できる
個人事業主は、従業員の給与やボーナスを経費にできますが、退職金は対象外です。
一方、法人では退職金も損金として計上できるため、法人所得を抑えることができ、結果として節税につながります。
例えば、長年事業を続けた後に引退する際、法人化していれば役員である社長自身への退職金支給が可能です。
退職金として支給した分は経費として処理できるため、節税しながら将来の資金を確保しやすくなります。
赤字を最大10年間繰り越せる
個人事業主は、事業が赤字になった場合、その赤字を翌年以降3年間しか繰り越せません。
一方、法人なら最長10年間まで赤字を繰り越せるため、一時的に赤字が発生しても、将来の利益と相殺して税負担を軽減できます。
開業したばかりのころは、設備投資などの影響で赤字になりやすいものです。しかし、法人ならその赤字を翌年以降の利益と相殺できるため、結果的に節税効果が得られます。
この仕組みを活用すれば、長期的な経営の安定にもつながるでしょう。
消費税の納税タイミングを遅らせられる
個人事業主は、売上が1,000万円を超えると消費税の納税義務が発生します。しかし、法人化すると設立後1〜2年間は免税事業者として扱われ、消費税の納税が免除されます。
事業の立ち上げ初期は特に資金が必要になることが多いため、法人化によって消費税の納税タイミングを遅らせられることは、節税と資金繰りの面で大きなメリットとなります。
法人化を検討すべき年収の目安とは?

個人事業主として年収が高くなってきたら、法人化による節税メリットが大きくなります。
それでは、具体的に年収がいくらになったら法人化を考えるべきなのかですが、その答えは個人事業主として所得が900万円~1000万円に達したときです。
所得税と消費税の2つの観点から、法人化による節税メリットが大きくなるからです。それぞれの観点について簡単に解説します。
所得税の観点
課税所得(利益)が900万円を超えると、個人事業主と法人の税率差が顕著になります。
| 個人事業主 | 33%(最大で45%まで上昇) |
|---|---|
| 法人 | 23.2%(資本金1億円以下の場合、800万円以下の部分は15%) |
個人事業主は累進課税のため、課税所得900万円を超えると税率が33%、さらに所得が増えれば最大45%になります。
一方で、法人税率は基本的に23.2%(中小法人は課税所得800万円以下の部分は15%)と一定のため、法人化することで税負担を軽減できる可能性が高くなります。
そのため、課税所得が900万円を超えた時点で、法人化を検討するのが合理的といえるでしょう。
消費税の観点
年収1000万円を超えると消費税の納税義務が発生します。インボイス未登録の場合、法人化することで以下のように、最大4年間の消費税免税期間が得られる可能性があります。
- 個人事業主としての免税期間:2年間
- 法人設立後の免税期間:2年間
そのため、消費税の免税期間を延ばして節税したい場合は、年収1000万円を超えたタイミングで法人化を検討するとよいでしょう。
ただし、すでにインボイス登録をしている場合は、消費税の観点からのメリットはありません。
法人化を決断するポイントまとめ
法人化のタイミングを決めるときは、次のポイントを意識しておくと判断しやすくなります。
| 所得税の節税効果を重視したい場合 | 課税所得が900万円を超えたタイミング |
|---|---|
| 消費税の免税メリットを最大限活用したい場合 | 年収が1000万円を超える前後(※インボイス未登録の場合のみ有効) |
このように、所得税と消費税のどちらをより重視するかによって、法人化を検討する年収の目安は多少前後します。
状況に合わせて判断し、節税しながら事業を安定的に成長させましょう。
法人化でできる具体的な節税対策

法人化することで、具体的にはどのような節税対策が可能になるのでしょうか?ここからは、法人化でできる3つの節税対策を紹介します。
役員報酬を活用する
法人化すると、役員報酬として収入を受け取ることで節税が可能です。
個人事業主の場合、売上から経費を差し引いた金額が「事業所得」として課税されます。
一方、法人化すると給与所得となり、給与所得控除(55万円~195万円)が適用されます。これにより、課税対象額が減り、所得税の負担が軽減されます。
例えば、役員報酬として300万円を受け取る場合、給与所得控除を適用すると、以下のようになります。
| 個人事業主の場合 | 300万円がそのまま課税対象(青色申告特別控除65万円を適用すると、235万円が課税所得) |
|---|---|
| 法人の場合 | 給与所得控除を適用(約98万円)し、課税対象額は約202万円 |
このように、法人化すると課税対象額を抑えられるため、所得税の負担を減らすことができます。
経費の範囲を広げる
法人化すると、経費に計上できる範囲が広がります。代表的なものは以下の通りです。
| 経費の種類 | 詳細 |
|---|---|
| 住居費 | 社宅扱いにすることで、家賃の70%~80%を経費にできる。 |
| 出張手当 | 出張旅費規程を作成すれば、日当を非課税で支給できる。 |
| 車両関連費 | 法人名義なら、車の維持費を経費にしやすい。 |
| 生命保険 | 法人契約にすれば、保険料を全額経費にできる場合がある。 |
例えば、自宅を事務所として使う場合を考えてみましょう。個人事業主のままでは家賃の2~5割しか経費にできませんが、法人化すれば最大8割まで計上することが可能になります。
ただし、どの経費も「事業に必要な支出であること」が前提です。経費として認められるためには、契約書や規程を整えるなど、適切な書類を準備しておくことが大切です。
退職金制度を導入する
法人化すると、役員や従業員に退職金を支給できるようになり、節税効果が期待できます。
退職金は「退職所得」として扱われ、次のような税制上の優遇措置があります。
法人化による退職金の優遇措置
- 退職所得控除が適用され、一定額まで非課税となる。
- 控除後の金額の1/2のみが課税対象となる。
- 退職所得は分離課税のため、高い累進税率の影響を受けにくい。
役員が5年以上勤務した場合を想定すると、まず退職所得控除が適用され、残りの金額の半分だけが課税対象になります。そのため、給与として受け取るよりも税負担が軽減される仕組みです。
ただし、退職金の額が高すぎると、法人の経費(損金)として認められない可能性があります。適正な金額を設定し、税務上の問題がないように注意しましょう。
節税のためだけに法人化すると後悔する?法人化のリスクとは?

法人化にはさまざまなメリットがありますが、節税目的だけで法人化すると、思わぬ負担が増えて後悔することがあります。ここでは、法人化による具体的なリスクについて解説します。
かえって社会保険料や法人住民税の負担が増えてしまう
法人化すると、個人事業主にはなかった固定費が発生します。特に、社会保険料の負担は大きく、一人社長でも加入しなければなりません。</p>
また、法人住民税の均等割は、赤字でも支払わなければならず、利益に関係なく固定費がかかります。
法人化によって発生する主な負担は、以下のとおりです。
| 負担の種類 | 詳細 |
|---|---|
| 社会保険料 | 会社が役員報酬や従業員給与の約15%を負担 |
| 法人住民税 | 赤字でも均等割の支払いが必要(最低7万円〜) |
法人化を検討する際は、これらの固定費を事前に試算し、本当にメリットがあるか慎重に判断しましょう。
お金を自由に使えなくなってしまう
法人化すると、事業で得た利益は会社のものとなり、個人の自由には使えません。
個人事業主であれば、事業の利益をそのまま生活費に充てることができますが、法人では役員報酬として受け取る必要があるからです。
役員報酬は毎月同じ金額の「定期同額給与」とする必要があり、自由に増減することはできません。報酬額を変更できるのは事業年度の開始から3か月以内のタイミングだけなので、計画的に決める必要があります。
このように、法人化すると個人のお金と会社のお金をはっきり分けなければならず、以前より自由度が下がったと感じる場合があります。
役員報酬には節税のメリットもありますが、その反面、自由に使えるお金が減るというデメリットもある点を知っておく必要があります。
手続きや事務作業が増えてしまい負担が大きくなる
法人化すると、税務や経理の手続きが増え、事務作業が増加します。
たとえば、法人税の申告は所得税の確定申告よりも手続きが複雑で、専門的な知識も必要になるため税理士に依頼することが一般的です。
また、決算期のスケジュール管理や定款の変更、各種届出の作成など、法人特有の手続きも出てきます。
事務作業が増えると、本業に集中しづらくなる可能性があるため、法人化を検討する際は、そうした負担が増えることも考慮する必要があります。
まとめ

この記事では、法人化による節税を中心に、メリットとデメリットを解説しました。
個人事業主と法人では税制の仕組みが大きく異なり、法人化すると所得税の負担を軽くできたり、経費として認められる範囲を広げられたりするメリットがあります。
特に、課税所得が一定額を超える場合、所得税よりも法人税のほうが税率が低くなるため、税負担を抑えやすくなります。
ただし、法人化には社会保険料の負担が増える点や事務手続きが複雑になる点など、デメリットも存在します。
節税だけを目的に法人化すると後悔する場合もあるため、事業規模や将来の計画を考えながら慎重に判断することが重要です。
法人化を検討している方は、今回紹介したメリット・デメリットを参考に、自身の事業にとって最適な選択を考えてみてはいかがでしょうか。
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス

- 法人保険を経営に活用したい
- いま加入している保険を見直したい
- 退職金制度や福利厚生を導入したい
- 事業承継や相続について考えたい
- 税金対策や財務戦略を相談したい
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて
"無料"で貴社に最適な保険プランを提案します。



















