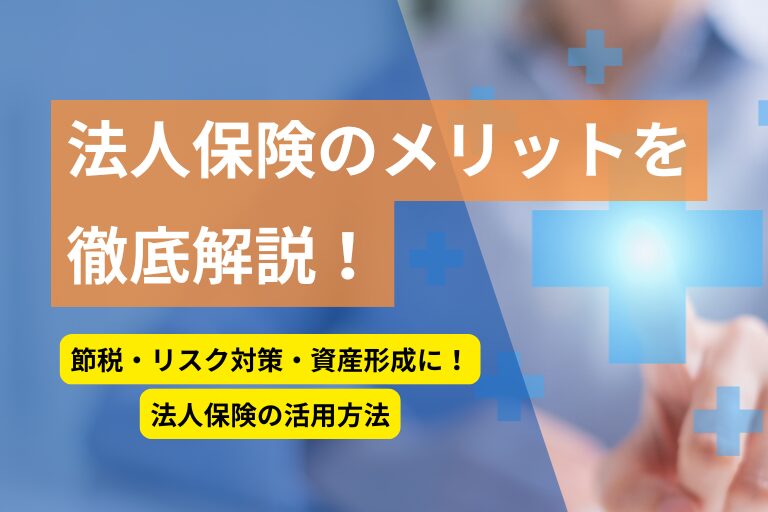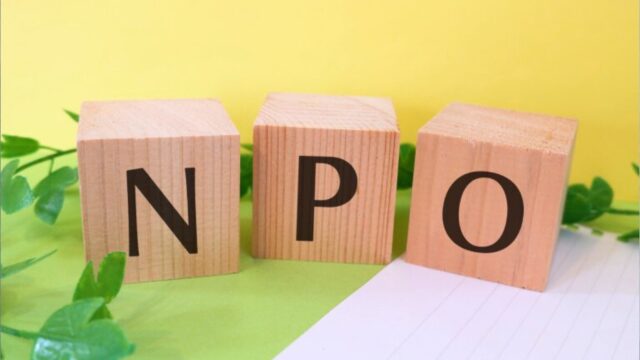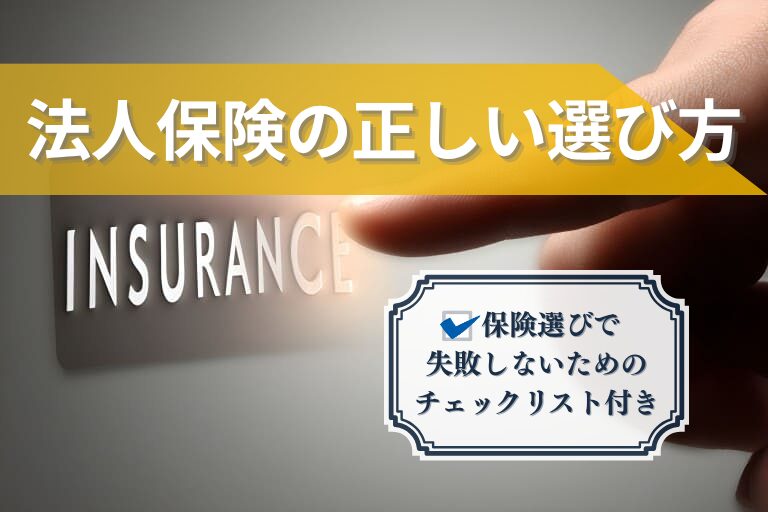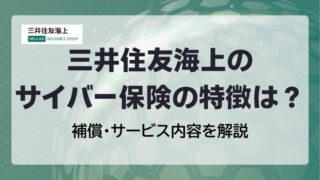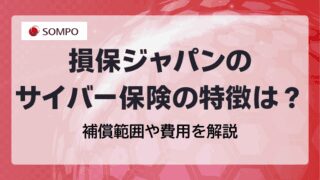法人保険とは、法人契約を結ぶ保険商品の総称で、特に生命保険や医療保険などを指します。
これらの法人保険は、ただリスクに備えるだけでなく、企業の成長や安定を支える経営戦略に役立つメリットがあります。
本記事では、経営戦略ツールとしての法人保険のメリットを徹底解説。税制や類似する金融商品との比較、企業に役立つ使い方をわかりやすくお伝えします。
「自社に法人保険は必要か」「どの種類を選べばよいか」の判断材料として、ぜひご活用ください。
法人保険のメリット6つ

法人保険が経営にもたらす主な価値は次の6つに集約できます。
- 節税(課税の繰延)
- —保険料の一定割合を経費化し、当期法人税を繰り延べてキャッシュを温存。
- 保障機能
- —経営者やキーパーソンの死亡・高度障害リスクに備え、事業継続資金を確保。
- 自己資本強化
- —解約返戻金を内部留保とみなす銀行もあり、自己資本比率の改善に寄与。
- 退職金・福利厚生
- —役員退職慰労金や従業員医療保障を準備し、採用力と定着率を強化。
- 事業承継・相続対策
- —死亡保険金を活用し、株価対策や相続納税資金を確保。
- 契約者貸付制度
- —金融機関の審査より容易に資金調達が可能
これらは単独でも効果がありますが、「節税+保障」「退職金+承継」といった複合設計で相乗効果を生む点が、法人保険ならではの強みです。
メリット① 節税(課税の繰延)でキャッシュを守る
法人保険の最大の魅力は、保険料の一部または全部を損金算入できる点にあります。
法人税率を30%と仮定した場合、単純計算で「600万円×30%=180万円」の税額軽減が可能です。
ただし、将来的に受け取る保険金や解約返戻金※は益金として課税されるため、トータルで課税額を減らす効果はありません。あくまで税負担を先送りする「繰延型」の節税効果となります。
※解約返戻金…解約時に保険会社から払い戻されるお金。
「ただ先送りするだけ?」と思うかもしれませんが、課税を繰り延べることで「貯蓄と税金対策の両立」「利益の平準化」など様々なメリットがあります。
過去の税制改正により、損金算入には一定のルールがありますが、うまく活用すれば強力な法人税対策となり得ます。
メリット② 事業リスクに備える保障機能
経営者や主要メンバーに万一が起きた瞬間、売上がストップしたり借入の一括返済を迫られたり—中小企業ほど「ヒトのリスク=会社存続リスク」が直結します。
こうしたリスクに対し、法人保険に加入しておけば、死亡・高度障害保険金や入院給付金を「緊急時の対策資金」として活用可能です。
商品によっては数億円単位の保険金を設定できるため、当面の運転資金や借入返済など、事業の立て直しまでに必要な資金を余裕を持って確保できます。
メリット③ 解約返戻金で自己資本比率を改善
法人保険の解約返戻金は、貸借対照表上「保険積立金」などの資産として計上でき、金融機関の評価において「疑似的な自己資本」とみなされる場合があります。
自己資本比率が1〜2ポイント上がるだけで、借入の金利優遇や追加融資枠を得られるケースもあるため、財務戦略上の大きなメリットとなります。
また、解約返戻金を事業投資に活用できるよう計画すれば、借入に頼らず設備更新やM&A資金を賄えるため、金利負担を抑えた成長投資が可能です。
メリット④ 退職金や福利厚生の充実
退職金制度や福利厚生として導入しやすい点も、法人保険のメリットの1つです。
退職金原資としての活用方法は最も一般的で、損金算入で税負担を減らしつつ積立ができます。医療保険も同様で、課税を繰り延べつつ役員・従業員に万一があったときの見舞金を確保可能です。
退職金や福利厚生の充実は、従業員満足度(ES)向上や採用力強化、企業の社会的責任(CSR)活動に直結します。自社の信頼性を強化する施策としても、法人保険はメリットの大きい商品の1つです。
メリット⑤ 事業承継・相続対策の準備
法人保険に加入することで、事業承継に伴う金銭的負担を軽減できるメリットもあります。
- 勇退退職金や死亡退職金の支払い
- 自社株の譲渡費用や移転に伴う納税
- 経営者保証債務の返済
- 遺産分割における非後継者への代償交付金
計画的な承継には解約返戻金を、想定外の事態による相続は保険金を活用できるので、あらゆる場面に対応できる引き継ぎ体制を構築できます。
メリット⑥ 契約者貸付制度で資金需要に対応
契約者貸付制度が利用できる点も、法人保険の欠かせないメリットです。
契約者貸付制度とは、解約返戻金の70~90%の金額で融資を受けられる制度のことです。
銀行などの融資と比べると審査に通りやすく、スムーズに借りられる点が特徴です。
契約者貸付制度がある法人保険に加入すれば、法人保険を解約することなく、資金調達の選択肢を増やせます。
法人保険のデメリットや注意点
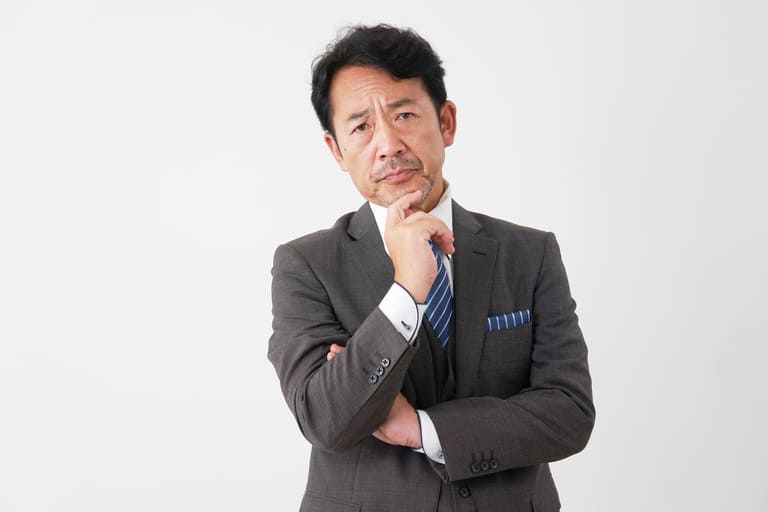
法人保険は多面的に役立つ一方、保険料負担・解約リスク・税務リスクを正しく管理しないと、かえってキャッシュを圧迫したり損金算入が否認されたりする恐れがあります。
経営者が必ず押さえておくべき代表的デメリットとして、以下の3つを知っておきましょう。
- キャッシュフロー悪化リスクと保険料負担率
- 元本割れ・解約タイミングミスの回避策
- 国税庁通達違反による損金否認リスク
デメリット① キャッシュフロー悪化リスクと保険料負担率
法人保険に加入すると、数年から数十年間にわたり保険料を支払う必要があります。
売上が急減した期にも一定額の固定費が発生するため、保険料負担率が高いとキャッシュフローを圧迫しかねません。
そのため、加入する前のシミュレーションが大切であり、事業計画や収支状況、市場予測を織り込んだ財務戦略を立てる必要があります。
また、定期的に見直しを行い、状況に応じて柔軟に運用することが求められます。
デメリット② 元本割れ・解約タイミングミスの回避策
法人保険の解約返戻率※は、それぞれピークを迎えるタイミングが決まっています。
※解約返戻率…支払った保険料総額に対する解約返戻金の割合。
種類にもよりますが、加入後ゆっくりと返戻率があがっていき、一度ピークを迎えるとその後は緩やかに下がっていくケースが基本です。
そのため、解約のタイミングを逃すと解約返戻率がどんどん下がっていき、手元に戻ってくるお金が減ってしまいます。
解約タイミングを見逃さないためには、返戻率の推移から逆算して資金計画を立てることが重要です。
また、急な資金需要には契約者貸付や保険担保融資で凌ぐなど、不測の事態にも冷静に対応するようにしましょう。
デメリット③ 間違った損金算入による否認リスク
2019年に税制通達が改正され、法人保険の損金算入には厳格なルールが定められています。
特に、最高返戻率や保険期間によって資産計上割合が決められ、ルールを無視すると税務調査で否認される恐れがあります。
否認された場合、過少申告加算税や延滞税が加算されるため、税負担が増加してしまいます。また、企業としての信用失墜にもつながりかねません。
保険料の資産計上・損金算入を間違えないよう、税理士など専門家と連携して経理処理を行うことが大切となります。
主な法人保険の種類と特徴

法人保険と一口にいっても、保険期間・返戻率・保障範囲・損金算入割合が大きく異なる複数のタイプがあります。
まずは代表的なタイプとして、以下の5つを押さえましょう。
- 逓増定期保険
- 長期平準定期保険
- 養老保険
- 終身保険
- 第三分野保険(医療・がん等)
どの商品を選ぶかによって、節税インパクトやキャッシュフローへの影響、それに伴う財務戦略まで変わります。自社の資金計画と照らし合わせながら、最適な組み合わせを検討してください。
逓増定期保険
逓増定期保険は、保険期間中に死亡保障額が段階的に増える法人保険です。
契約から一定期間は基準保険金額が保障され、その後逓増(段階的に増加)していき、最大5倍まで増えます。
メリットとしては、段階的に保障額が増えるため、企業の成長段階に合わせた保障を確保しやすい点が挙げられます。
また、解約返戻率のピークが5~10年程度と早めに訪れるため、短期的な資金計画に活用しやすい点もメリットです。
一方、デメリットとして保険料が割高傾向であることが挙げられます。初期の解約返戻率を低くする代わりに保険料を抑えた「低解約返戻金型逓増定期保険」というタイプもあるため、一緒に検討してみましょう。
長期平準定期保険
長期平準定期保険は、保険期間が長期に設定される法人保険です。定期型ではありますが、最大100歳前後まで保障を受けられる商品もあります。
解約返戻率の推移はゆるやかなベルカーブ型で、おおむね10年~30年後とピークも遅めにくることが特徴です。
メリットは保険料が割安なことや、返戻金ピークが遅いので長期的な資金計画に組み込みやすいことが挙げられます。
一方、期間が長い分、保険料支払いの負担も長く続くため、事前のシミュレーションが特に重要となります。
養老保険
養老保険は、被保険者が生きたまま保険期間を終了すれば満期保険金が、万が一死亡してしまったら死亡保険金が支払われる法人保険です。
メリットは、被保険者が死亡しても生存していても保険金を得られる点で、生存退職金・死亡退職金(弔慰金)の両方を準備したいときに適しています。
また、福利厚生要件を満たせば保険料の半額を損金算入できる点もメリットです。
ただし、一般的な生命保険より保険料相場が高めなこと、福利厚生要件を満たすには全従業員を対象にすることなど、活用には保険料負担が大きくなりやすい点がデメリットといえます。
終身保険
終身保険は、被保険者が亡くなるまで保険期間が続く法人保険です。
保障が一生涯続き、保険金か解約返戻金のどちらかは必ず受け取れます。長きにわたって確実な保障を確保したいときや、貯蓄・事業承継をメインに対策したい場合に適しています。
一方、保険料は原則資産計上となるため、節税(課税の繰延)目的には向いていない点がデメリットです。
第三分野保険(医療保険・がん保険など)
第三分野の保険は、生命保険や損害保険に分類されない保険種類を指します。具体的には、医療保険やがん保険、介護保険等です。
解約返戻金がある第三分野保険は、定期保険と同じルールで損金算入が可能です。また、福利厚生要件を満たせば保険料の半額損金算入もできます。
ただし、福利厚生として活用するには、養老保険と同様に全従業員を対象にするなどの条件があるため、制度設計に注意が必要です。
他の金融商品とのメリット比較

法人保険のメリットを紹介しましたが、単純に「資金を運用する」「将来のためにお金を残す」という目的だけなら、預金積立や共済制度など他の手段もあります。
ここからは、類似する金融商品とのメリットの違いを比べ、どの局面で法人保険が優位かを整理します。
VS.預金積立
銀行預金は元本欠損のリスクが低く、流動性も高い点がメリットです。一方、損金算入はできないため節税(繰延)効果がない点がデメリットとなります。
法人保険なら保険料の一部または全額を損金計上し、当期法人税を繰り延べながら貯蓄ができます。さらに死亡・高度障害時の保障も付帯します。
また、配当型の法人保険に加入すれば、運用成績次第で配当分の上乗せが期待できます。
安定や資金の流動性を重視するなら預金が、税務メリットや貯蓄+αを求めるなら法人保険が向いているでしょう。
VS.共済制度
共済制度の中には、掛金の全額損金算入が可能なものもあります。
たとえば「経営セーフティ共済」の場合、掛金上限800万円まで全額損金算入が可能です。また、最大100%の解約返戻率や、最大で掛金の10倍の借入枠という魅力です。
ただし、上限以上の追加入金はできないため、利益が大きい企業だと「損金算入の金額が物足りない」と感じるケースが少なくありません。
法人保険は保険料に上限がなく、契約内容によっては数百万~数億円の損金算入も可能です。
売上が大きい企業は、法人保険を選ぶか、あるいは共済と法人保険を併用して節税(繰延)枠を増やしましょう。
VS.有価証券
資産の運用方法として代表的な株式・投信ですが、高いリターンを期待できる一方、変動リスクが大きい点がデメリットです。
特に、含み損が出た際は損金算入できず、時価会計で純資産が上下するリスクがあります。
短期的な高利回りは有価証券が勝るものの、課税調整やリスク対策の観点では法人保険に分があります。
VS.不動産
不動産投資は減価償却で損金を大きく計上できる一方、法人保険と比べると初期投資が大きく、流動性が低いデメリットがあります。
空室リスクや修繕費も重く、急な現金化が難しい点がネックです。
法人保険なら保険料を損金にしつつ、解約返戻金を設備投資や納税資金に数年で変換できます。
流動性と保障を優先するなら法人保険、長期インフレヘッジなら不動産、性質に合わせた活用が重要です。
まとめ

本記事で紹介した法人保険のメリットは以下の6つです。
- メリット① 節税(課税の繰延)でキャッシュを守る
- メリット② 事業リスクに備える保障機能
- メリット③ 解約返戻金で自己資本比率を改善
- メリット④ 退職金や福利厚生の充実
- メリット⑤ 事業承継・相続対策の準備
- メリット⑥ 契約者貸付制度で資金需要に対応
金銭的なリスクに備えるだけであれば他の選択肢もありますが、法人保険は導入が容易であることや、資金計画の見通しがしやすい、節税(繰延)効果を期待できるという点で優れています。
反面、法人保険は継続して保険料を支払っていくため、キャッシュフローへの影響が大きいというデメリットがあります。また、解約返戻金の出口戦略をあらかじめ考えておくことも必要です。
法人保険を最大限活かすためには、経営と税制に詳しい専門家のアドバイスが不可欠です。保険代理店などのプロフェッショナルに相談し、自社に最適なプランで法人保険に加入しましょう。
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス

- 法人保険を経営に役立てたい
- いま加入している保険を見直したい
- 退職金制度や福利厚生を導入したい
- 事業継承や相続について考えてたい
- 税金対策や財務戦略を相談したい
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて"無料"で最適な保険プランを提案します。