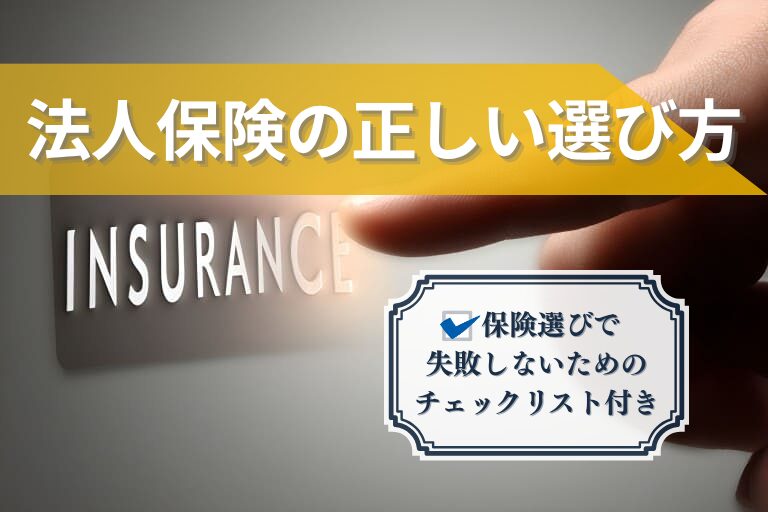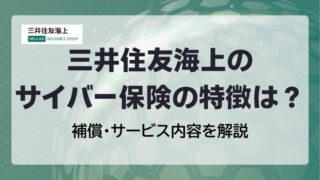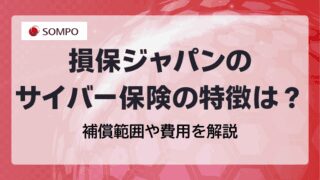個人事業主の税金対策として、マイクロ法人の設立は効果的な節税方法です。マイクロ法人化することで、所得税の減税や消費税の免税期間などさまざまな効果が見込めます。
ただし、法人化にあたりインボイス制度や運営コストなど、知っておくべき注意点もあります。
この記事ではマイクロ法人の概要から節税効果、注意点までわかりやすく解説。また、マイクロ法人の節税が向いている人の特徴もお伝えします。
個人事業主の方は、本記事を参考にぜひマイクロ法人化による節税を検討してみましょう。
マイクロ法人とは代表者1人で運営する会社のこと

マイクロ法人とは、従業員を雇わずに代表者1人で運営する会社を指します。
1人で会社運営を行うことから、フリーランスでも働きやすいエンジニアやライター、コンサルタントといった業種に多い企業形態です。
マイクロ法人を設立すると、税金や社会保険料の面で個人より有利となる場合があるため、個人事業主やフリーランスの節税対策として設立されるケースが一般的です。
普通の法人や個人事業主との違い
マイクロ法人は「1人で運営している会社(法人)」の俗称です。
一方、法人や個人事業主は以下のように定義できます。
| 法人 | 法律上「人」として権利や義務が認められた組織。民法で定義される。 |
|---|---|
| 個人事業主 | 税務署に開業届を出し、個人で事業を行う人。法律用語ではないが、税務上の区分の1つとして存在する。 |
法人は、株式会社や合同会社などの「営利法人」や、一般社団法人などの「非営利法人」、地方公共団体などの「公法人」があります。マイクロ法人は法人の一形態といえます。
一方、個人事業主は「開業届の提出」と「法人を設立していない」という2つを満たす事業者です。「個人事業主 ≠ 法人」なので、マイクロ法人とは明確に異なるといえます。
マイクロ法人の節税効果4つ

マイクロ法人で期待できる節税効果は、以下の4つが挙げられます。
- 所得税や住民税の節税につながる
- 経費の範囲が広がる
- 消費税の免税制度を利用できる
- 社会保険料の軽減にもなる
所得税の節税につながる
マイクロ法人を設立すると利益に対する適用税率が変わるため、節税につながる場合があります。
以下は、個人事業主と法人で課税の違いを比較したものです。
| 税の種類 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 所得税 | 累進課税(5~45%) | (役員報酬に対して)同左 |
| 法人税 | なし | 15~23% |
個人事業主だと最大45%の所得税が課せられますが、法人税は15~23%なので、所得額によっては税率が低くなります。
また、法人化すると「法人の利益から役員に報酬を支払う」という形になるため、給与所得控除の適用が可能です。個人事業主として利益をそのまま受け取るより、税負担を軽減できます。
経費の範囲が広がる
マイクロ法人を設立すれば、個人事業主よりも経費として使える費用項目が大幅に増えます。
以下は、経費にできる主な費用です。
- 役員報酬
- 退職金
- 生命保険料
- 宿泊費・交通費
- 接待交際費・会議費
- 通信費
- 広告宣伝費
- 家賃
- 自動車購入費
経費計上できる割合が増えれば、課税所得を減らして節税効果を高められます。
消費税の免税制度を利用できる
事業者は、基準期間(原則として前々年度)の売上が1,000万円以下の場合、消費税の免税制度を利用できます。この制度は、個人事業主と法人の両方で利用可能です。
仕組み上、法人設立から2年間は「前々年度の売上」が存在しないため、新規法人については制度を適用できます。また、売上が1,000万円の状態が続けば、3年目以降も対象です。
ただし、2023年10月から導入されたインボイス制度により、免税事業者は取引先から敬遠される可能性が生じたため、状況によっては適格請求書発行事業者登録を行い、消費税を納税することも検討しましょう。
社会保険料の軽減にもなる
マイクロ法人を設立すると、社会保険(健康保険と厚生年金)への加入により保険料負担を軽減できます。
社会保険料は役員報酬に応じて計算されますが、マイクロ法人なら役員報酬の金額は自分で決められる点が特徴です。最低限の金額に設定すれば、標準報酬月額の等級が低くなり社会保険料を節約できます。
具体的には、役員報酬月額を63,000円未満にすれば社会保険料は最安になります(令和7年度保険料額の基準)。
ただし、役員報酬が低すぎると税務調査の対象になるかもしれないため、事業規模などに合わせて適切に設定することが大切です。
マイクロ法人設立による節税の注意点
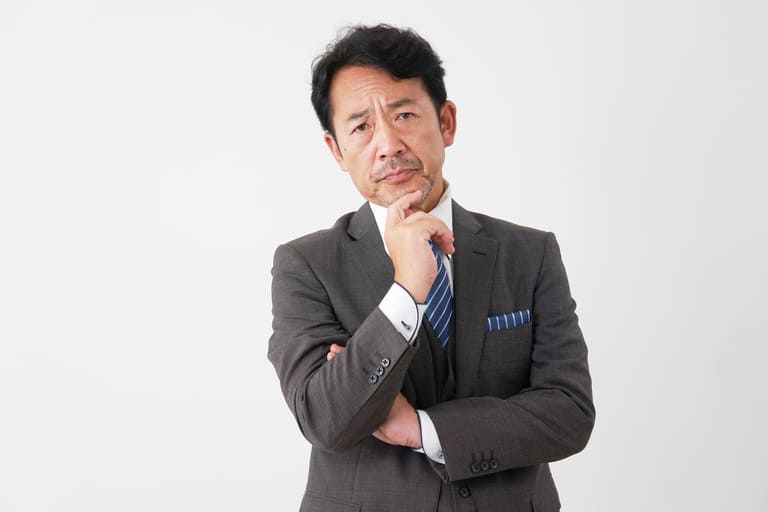
マイクロ法人化で節税効果を得られるのは確かですが、いくつかのデメリットもあります。
節税対策で失敗しないよう、マイクロ法人設立における注意点も理解しておきましょう。
サラリーマンだと社会保険料の軽減効果はない
サラリーマンでも副業で行っている事業をマイクロ法人化できますが、この場合だと社会保険料の軽減効果はありません。
サラリーマンは会社が社会保険料を納めており、マイクロ法人の方からは支払えないためです。
「個人事業主 + マイクロ法人」の二刀流なら社会保険料を節約できますが、「サラリーマン + マイクロ法人」だと軽減できないので注意しましょう。
法人の設立や維持にはコストがかかる
マイクロ法人の設立・維持にはコストがかかります。
一般的に、株式会社の設立には登録免許税などで30万円程度、合同会社の場合は10万円ほどの支出が必要です。
維持費としては、顧問税理士への報酬として約10万円、法人住民税が最低で7万円はかかるので、少なくとも年間17万円の維持コストがかかります。
ほかにも細々とした出費があるため、期待していたほど節税効果を得られない可能性があります。マイクロ法人設立後にどのくらいの費用がかかるのか、具体的に見積もりを立てることが大切です。
決算申告には複雑な手続きが必要
マイクロ法人を設立すると、個人事業主より複雑な決算申告を行わなければなりません。
決算申告ではその年度の収益や費用、負債などを整理して財政状況を明確にする必要があります。
マイクロ法人の決算を自分でやる場合の流れは、次の通りです。
- 日々の取引の記帳を行い帳票を整理する
- 資産・負債の実査を行い財務状況を把握したら試算表を作成する
- 決算整理仕訳をしたら貸借対照表や損益計算書を作成する
- 法人税申告書や株主資本等変動計算書、個別注記表を作成する
- 決算書類を取締役会や株主総会で承認してもらう
- 税務署へ法人税申告書を提出および納税する
決算申告のミスは追徴課税などのペナルティにつながるため、不安があれば税理士などの専門家に相談しましょう。
マイクロ法人による節税を検討すべき基準

ここからは、節税目的でマイクロ法人を検討するときの基準を紹介します。
年間の事業所得が500万円以上ある
事業所得を基準にする場合、年間500万円以上になるとマイクロ法人化による節税効果が期待できます。
以下は、所得税と法人税の税率をそれぞれまとめたものです。
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から194万9,000円まで | 5% | 0円 |
| 195万円から329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円から694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円から899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円から1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
参照:国税庁|所得税の税率
| 資本金 | 税率 |
|---|---|
| 原則 | 23.20% |
| 中小法人(資本金1億円以下)の場合 | 年800万円以下の部分:15% 年800万円超の部分:23.20% |
参照:国税庁|法人税の税率
資本金1億円以下であれば、課税所得のうち年800万円の部分までは税率15%です。所得税と比較した場合、課税所得330万円以上から税率が逆転します。
ただし、マイクロ法人の設立や維持には数十万円はかかるため、これらの費用を考えると課税所得500万円以上が節税効果を得られる目安となります。
配偶者を扶養している
配偶者を扶養しているなら、所得に関係なくマイクロ法人化するのがおすすめです。
個人事業主の場合、扶養家族分の国民健康保険料と国民年金の支払いが必要であり、配偶者の保険料分だけで年間30万円〜40万円程度の支払いが必要になります。
一方、社会保険なら年収130万円未満の配偶者は扶養に入れられるので、保険料・年金保険料ともに不要です。マイクロ法人の維持費用を考えても、トータルで負担を軽減できます。
まとめ

個人事業主のマイクロ法人化は、所得税や社会保険料の軽減により一定の節税効果が見込めます。
所得が500万円以上、もしくは配偶者を扶養している場合は、マイクロ法人化を検討する価値があるでしょう。
ただし、実際にマイクロ法人を設立するときは、家族構成や収入のバランス、将来設計などさまざまな要素を考慮する必要があります。
複雑な手続きも発生するため、まずは税理士などの専門家に相談し、自身の状況にぴったりの節税方法をアドバイスしてもらいましょう。
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス

- 法人保険を経営に役立てたい
- いま加入している保険を見直したい
- 退職金制度や福利厚生を導入したい
- 事業継承や相続について考えてたい
- 税金対策や財務戦略を相談したい
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて"無料"で最適な保険プランを提案します。