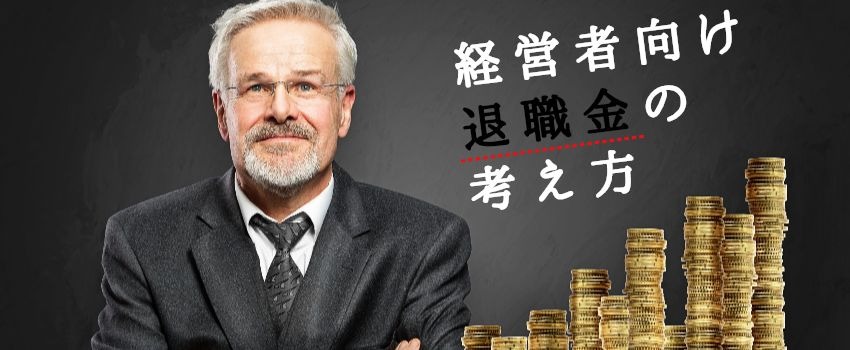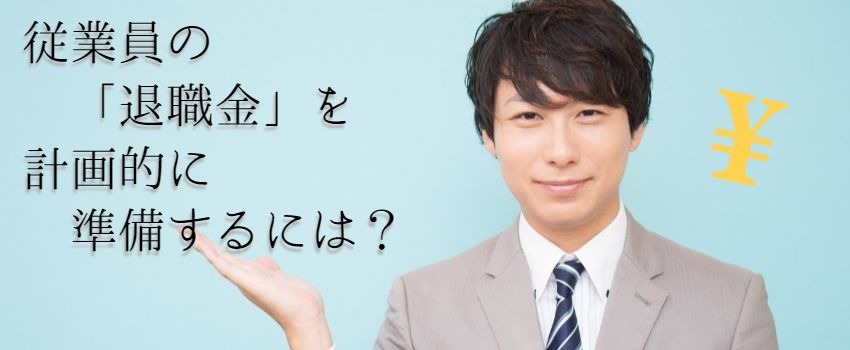中小企業の経営者や人事・総務担当者にとって、退職金制度の整備は重要な課題です。特に、将来の退職金支払いに備えて、どのように資金を準備するかは慎重に検討する必要があります。
その中で注目されているのが、生命保険を活用した退職金の積立です。法人契約で保険に加入し、解約返戻金や満期保険金を退職金の原資として活用します。
本記事では、法人が生命保険を利用して退職金を積み立てる際のメリットやデメリット、導入時の注意点などを詳しく解説します。退職金制度の導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
退職金制度に適した保険積立のプランとは?

退職金の準備方法で保険を活用する場合、貯蓄性のある生命保険に加入します。
貯蓄型の生命保険は保険料の一部が積立金となり、解約時や満期時にまとまったお金(解約返戻金や満期保険金)が払い戻されます。これが退職金の原資です。
法人が契約者となり、役員や従業員を被保険者とすることで、生存退職金・死亡退職金の両方に備えられます。
退職金の積立が可能な保険商品の種類と特徴
退職金の積立ができる保険商品にはいくつか種類があり、それぞれ特徴や適用範囲が異なります。
代表的なものは以下の通りです。
| 終身保険 | 保険期間の定めがない保険。年数の経過に伴い解約返戻金も増え続ける。 |
|---|---|
| 定期保険 | 一定期間内に被保険者が死亡した場合に保険金が支払われる保険。終身保険より保険料が比較的安価。満期保険金はなく、解約返戻金も満期が近づくにつれ下がっていく。 |
| 養老保険 | 一定期間内に被保険者が死亡した場合や満期まで生存した場合に保険金が支払われる保険。満期保険金は死亡保険金と同額を受け取れる。 |
上記は一例で、実際にはさまざまなプランがあります。解約返戻金の有無や増減のペース、いくらまで積立が可能かなど、契約前に細かくチェックしましょう。
経営者・役員・従業員向けプランの違い
退職金の対象が経営者・役員か従業員かで、適切なプランも異なります。
| >経営者・役員の場合 | 高額な退職金を準備するために、終身保険や長期定期保険を活用するケースが一般的。事業承継や相続対策、万が一の事態に備えた事業保障を見据えたプラン設計が重要。 |
|---|---|
| 従業員向けの場合 | 福利厚生の一環として、全従業員を対象にした養老保険の導入が一般的。勤労意欲向上や人材定着を目的とした商品が多い。 |
退職金の導入目的に合わせて、適切なプランを設計することが大切です。
保険積立のシミュレーション例
実際に生命保険の積立で退職金を準備する場合、積立金額など具体的な数値は気になるところです。
ここでは、役員向けの逓増定期保険※を例に取り、積立のシミュレーションをします。
※逓増定期保険…保険期間が前期と後期に分かれ、後期に最大5倍まで保険金額が徐々に増加(逓増)する保険。
- 被保険者:役員
- 保険期間:20年(前期8年、後期12年)
- 保険料払込期間:20年
- 基準保険金額:1億円
- 逓増率:前期0%、後期50%(複利)
- 年払保険料:800万円
【シミュレーション】
横スクロールできます →
| 経過年数 | 保険金額 | 累計の支払済保険料 | 解約返戻金 | 返戻率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,000,000円 | 8,000,000円 | 5,464,000円 | 68.3% |
| 2 | 100,000,000円 | 16,000,000円 | 12,768,000円 | 79.8% |
| 3 | 100,000,000円 | 24,000,000円 | 20,184,000円 | 84.1% |
| 4 | 100,000,000円 | 32,000,000円 | 27,680,000円 | 86.5% |
| 5 | 100,000,000円 | 4,000,0000円 | 35,840,000円 | 89.6% |
| 6 | 100,000,000円 | 48,000,000円 | 43,632,000円 | 90.9% |
| 7 | 100,000,000円 | 56,000,000円 | 52,136,000円 | 93.1% |
| 8 | 100,000,000円 | 64,000,000円 | 59,840,000円 | 93.5% |
| 9 | 150,000,000円 | 72,000,000円 | 66,456,000円 | 92.3% |
| 10 | 225,000,000円 | 8,000,0000円 | 70,880,000円 | 88.6% |
| 11 | 337,500,000円 | 88,000,000円 | 70,752,000円 | 80.4% |
| 12 | 500,000,000円 | 96,000,000円 | 69,504,000円 | 72.4% |
| 13 | 500,000,000円 | 104,000,000円 | 67,288,000円 | 64.7% |
| 14 | 500,000,000円 | 112,000,000円 | 63,840,000円 | 57.0% |
| 15 | 500,000,000円 | 12,000,0000円 | 58,920,000円 | 49.1% |
| 16 | 500,000,000円 | 128,000,000円 | 52,224,000円 | 40.8% |
| 17 | 500,000,000円 | 136,000,000円 | 43,384,000円 | 31.9% |
| 18 | 500,000,000円 | 144,000,000円 | 32,112,000円 | 22.3% |
| 19 | 500,000,000円 | 152,000,000円 | 17,784,000円 | 11.7% |
| 20 | 500,000,000円 | 160,000,000円 | 0円 | 0.0% |
※あくまで一例であり、実際の保険内容とは異なります。
上記のシミュレーションの場合、解約金返戻率がピークとなる7~9年目と退職金支払時期が重なるよう加入することが基本的な戦略となります。
具体的な契約内容や数値はケースバイケースなので、FPなどの専門家と相談しつつプランを検討しましょう。
退職金制度に保険積立を利用するメリット

退職金準備にあたって、なぜ生命保険の積立が選ばれるのでしょうか?
理由となる具体的なメリットを解説します。
1.退職金原資を計画的に積立できる
生命保険を活用することで、法人は退職金の原資を長期的かつ計画的に積立できます。
預金などで企業が独自に積み立てる方法だと、事業拡大や損失補てんなどを優先してしまい、積立が後回しになってしまうケースも少なくありません。一方、生命保険に加入することで、積立に実質的な強制力が生まれます。
結果として、退職原資の積立がしやすくなり、将来の資金不足リスクを軽減できます。
2.保険料の一部を損金(経費)計上できる
法人が支払った保険料は一部または全部を損金として計上できるため、積立しつつ法人税の負担軽減につながります。浮いた負担を事業投資などに回せば、企業の成長性を向上できるでしょう。
ただし、解約返戻金などの受取時には益金として計上する必要があります。退職金支払いによる損金と相殺できますが、総合的な税負担は変わりません。
また、最高解約返戻率(支払済保険料に対して解約返戻金の割合がもっとも高いときの比率)が高いほど、損金として計上できる割合は制限されます。税制に則ったルールを遵守することが大切です。
3.万が一の保障も兼ねられる
積立型の生命保険には死亡保障や高度障害保障の機能もあるため、万が一の事態があっても保険金が支払われます。これにより、緊急時における金銭面での対処がしやすくなります。
例えば、経営者やキーパーソンが急逝した際の事業保障や、遺族への弔慰見舞金など、企業の運転資金として幅広く活用可能です。保険は単なる積立手段ではなく、リスクマネジメントの観点からも有効な手段です。
4.福利厚生の強化になる
保険積立は、役員や従業員の福利厚生手段として有効です。退職金制度の導入はもちろん、健康相談や各種医療サービス、入院特約や特定疾病特約などが付帯する場合もあります。
中小企業の場合、退職金を含む福利厚生の整備に手が回らない会社も多いですが、保険に加入すればさまざまなサポートを受けられます。
福利厚生は、日々の意欲向上や安心感の提供、人材の確保・定着などにも重要です。企業としての信用力向上にもつながり、対外的な評価にも好影響をもたらすでしょう。
デメリットと対策

保険の積立には多くのメリットがある一方、複数のデメリットも存在します。
事前に知っておくべきポイントを解説していくので、適切に制度を構築・運用できるようにしましょう。
1.資金拘束が発生する
生命保険による積立は中長期での運用が前提となるため、資金の流動性が低くなります。事業の急な資金需要や経営環境の変化に対応しにくいというデメリットがあるため、保険に資金を振り分けすぎると、運転資金に支障をきたす恐れがあります。
したがって、積立額や契約期間は、会社のキャッシュフローや将来の事業計画を十分に考慮した上で、バランス良く設計することが必要です。
2.保険料負担が重い場合がある
積立型の生命保険は保障と貯蓄を兼ね備えているため、掛け捨て型と比べて保険料が高くなります。そのため、長期的に見れば有利な制度であっても、短期的には会社の資金繰りに大きな影響を与える可能性があります。
特に経営が不安定な時期には、毎月の保険料の支払いが大きな負担となるかもしれません。導入前には、長期的な収支予測を行い、無理のない範囲で制度設計を行うことが重要です。
3.税制改正の可能性がある
保険料の損金算入や解約時の税務処理については、税制改正の影響を大きく受ける可能性があります。近年も保険料の損金計上ルールが厳格化された例があり、今後も制度が変更されるリスクは否定できません。
当初想定していた節税効果が得られなくなる場合も考えられるため、制度導入時にはFPなどと連携し、法改正の動向を常に把握しながら定期な見直しを実施しましょう。
まとめ

生命保険を活用した退職金の積立は、福利厚生の充実や税負担の軽減など、多くのメリットがあります。一方で、保険料の負担や税制改正などの注意点もあるため、導入するときは慎重な検討が必要です。
退職金制度の導入を検討するときは、まず法人コンサルティングに詳しいFPや税理士などに相談しましょう。保険の積立だけでなく、共済や企業型DC(企業型確定拠出年金)などの選択肢も踏まえて、総合的なアドバイスをもらえます。
専門家と連携し、自社に最適な退職金制度を構築することが、企業の持続的な成長と従業員の安心につながります。
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス

- 法人保険を経営に活用したい
- いま加入している保険を見直したい
- 退職金制度や福利厚生を導入したい
- 事業承継や相続について考えたい
- 税金対策や財務戦略を相談したい
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて
"無料"で貴社に最適な保険プランを提案します。