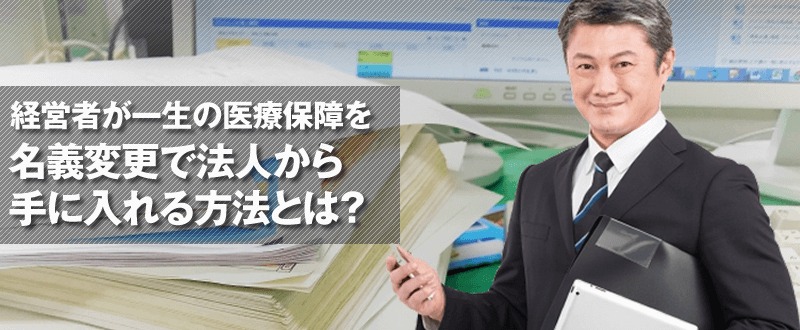会社の成長や経営環境の変化に伴い、法人保険の見直しを検討している経営者の方も多いでしょう。
法人保険の見直しは、キャッシュフローの改善や保障(補償)内容の最適化といったメリットが期待できます。一方で、見直しに失敗すると「保険料が高くなる」「必要な保険を解約してしまう」など、かえって損失につながるかもしれません。
そこでこの記事では、法人保険の見直しで経営者がすべきことや適切なタイミングなどを解説していきます。この記事を参考に、自身の会社に最適な法人保険を見つけましょう。
法人保険の見直しで経営者がすべきこと

法人保険の見直しをするにあたって、経営者の方は以下の点を行いましょう。
- 同じ保障(補償)にコストを払っていないかチェックする
- 経営環境の変化や新しいリスクを整理する
- 法人保険の専門家に相談する
いずれも適切な見直しを行うために重要なポイントです。
それぞれ詳しく解説します。
同じ保障(補償)にコストを払っていないかチェックする
まずは現在の加入状況を整理し、無駄な保険を契約していないかチェックしましょう。
企業によっては、付き合いで複数の保険に加入していたり、起業前から契約していた個人保険をそのままにしていたりなどで、保障(補償)内容が重複しているケースがあります。
無駄な保険を解約すれば、保険料の二重支払いを解消してキャッシュフローを改善できます。
「いま加入している保険の把握ができていない」という経営者も多いため、一度しっかり整理してみましょう。
経営環境の変化や新しいリスクを整理する
自社のビジネスモデルの変化や新たなリスクを洗い出し、いま契約している保険でカバーできているか確認することも大切です。
例えば、事業の成長に伴って従業員数が増えてきたり、企業の資産価値が高くなったりすれば、保障(補償)範囲を広げる必要が出てきます。
また、法改正や海外情勢の変化などで新たなリスクが生まれるなど、外的要因によって保障(補償)内容が不十分になるケースもあります。
ビジネスを取り巻く環境は常に変動しているため、契約中の保険が最新の状況に対応できているかチェックすることが、法人保険の見直しでは大切です。
法人保険の専門家に相談する
保険の見直しは専門的な知識が不可欠であり、経営者がすべて調査・決断するのは非常に負担がかかります。そのため、見直しの際は法人保険に精通した専門家に相談することをおすすめします。
法人保険の専門家なら、経営や税制、各業界の固有リスクを熟知しており、スムーズに相談可能です。過去の事例や最新の情報を参考に、企業に適した保険を提案してくれます。
法人保険の見直しにおすすめのタイミング3選

法人保険の見直しで悩みやすいのが、「どのタイミングで見直すのがベストか」です。
可能であれば、1年~3年に1回程度の頻度で定期的に見直すことをおすすめします。このぐらいのスパンで見直しを行えば、ビジネスを取り巻く環境の変化にも対応しやすいでしょう。
それ以外では、以下のタイミングでの見直しがおすすめです。
- 解約返戻金がピークになるとき
- 新規事業の開始・事業規模の変更を行うとき
- 法律・規制が変わったとき
それぞれ詳しく解説します。
①解約返戻金がピークになるとき
まず、解約返戻金のピーク時が法人保険を見直すタイミングに挙げられます。解約返戻金とは、保険契約を解約したとき返還されるお金です。
具体的な時期は保険商品によって異なりますが、解約返戻金が最大になるときに保険の見直しをすれば、損失を最小限に抑えられます。
ただし、解約返戻金は受け取った際に利益として計上されるため、金額が大きければ大きいほど法人税も増えてしまいます。
法人税を抑えるためには、解約返戻金を受け取った年度に同じだけの支出が発生するイベント(設備投資や退職金支払いなど)を用意しておくなど、出口対策も考えておきましょう。
②新規事業の開始・事業規模の変更を行うとき
新規事業の開始や事業の拡大・縮小を行うときも、法人保険の見直しに適しています。
新規事業を立ち上げるのであれば、その業種に特化した保険が必要です。その事業固有のリスクをカバーするための法人保険に新規加入し、それと合わせて従前の保険内容を見直しましょう。
事業規模が変わるときも、備えるべきリスクの規模や範囲が変わるため、法人保険の拡充もしくは縮小を検討すべきです。新規事業の開始と同じように、新しい保険の加入やいまある保険の整理を行いましょう。
③法律・規制が変わったとき
法律や各種規制が変わったときも、法人保険の見直しを行うべきタイミングです。ルールが変わることで新たなリスクが生じたり、法人税の取り扱いが変わったりする恐れがあります。
直近では、2019年に行われた法人保険の税制改正が代表的です。改正前、法人保険の保険料は1/3~全額を損金として計上できましたが、改正後はそれに制限がかかるようになり、節税効果の大半が失われてしまいました。
このように、ビジネスを取り巻く法律・規制の改正によって、法人保険で得られるメリットが変わる場合もあります。
また、改正に合わせて新しい保険商品が発売されることもあります。改正が自社に直接の影響を及ぼさなくても、新しい保険商品に切り替えることで得られるメリットが増えることもあるため、その点でも見直しはおすすめです。
ニュースなどで最新情報を常にチェックし、柔軟に対応できるようにしましょう。
保険を見直す際に注意すべきポイント

見直しで新たな法人保険に加入する場合、次の2点に注意しましょう。
- 新しい保険の契約目的を明確にする
- 保険料を継続して支払えるか確認する
いずれも法人保険の見直しで失敗しないために重要なポイントです。それぞれ詳しく解説します。
新しい保険の契約目的を明確にする
法人保険を選ぶときは、「契約する目的」を明確にしておく必要があります。見直しで新しい保険に加入する際も、まずは何のために契約するのかをはっきりさせましょう。
目的が決まれば、必要となる保険の種類も自然と決まります。下記は、保険の契約目的とそれに適した保険商品の一例です。
| 目的 | 適した保険商品 |
|---|---|
| 経営者の就労不能に備える | 医療保険、生命保険など |
| 役員の退職金に備える | 養老保険など |
| 従業員の福利厚生に備える | 団体定期保険など |
| 事業承継・相続に備える | 生命保険(障害介護型)など |
| 施設・設備の損害に備える | 地震保険、火災保険など |
見直しの際は、まず目的に合っていないものを解約し、それから適切な保険を改めて契約するという流れで行いましょう。
保険料を継続して支払えるか確認する
保険の見直しによって保険料が上がり、支払いが苦しくなるケースもあります。どれだけ良い保険でも、保険料で経営を圧迫しては元も子もありません。
このような事態を避けるためにも、将来にわたって問題なく保険料を支払えるか、しっかりとしたシミュレーションが大切です。
保険の専門家に相談すれば保険料の見積もりも出してもえるので、各保険商品の保険料を比較し、自社に適切なものを選びましょう。
まとめ

法人保険は、不要な保障(補償)に保険料を払っていたり、節税効果があると思っていてもあまり意味がなかったりと、無駄な支出をしている企業が少なくありません。
契約時には有用でも、会社の成長やビジネス環境の変化に伴ってメリットを失ってしまうケースも多いため、定期的な見直しが大切です。手間はかかりますが、最適な保障(補償)を準備するためにも、こまめに見直しを行いましょう。
「備えるべきリスクがわからない」「自社がどのような保険に加入しているか把握しきれていない」という場合は、法人保険の専門家に相談することをおすすめします。法人保険のプロフェッショナルなら、企業の財務状況などを分析し、最適な見直しを実行してくれます。
専門家の力も借りつつ、安定的な事業継続につながる法人保険を選びましょう。
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス

- 法人保険を経営に活用したい
- いま加入している保険を見直したい
- 退職金制度や福利厚生を導入したい
- 事業承継や相続について考えたい
- 税金対策や財務戦略を相談したい
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて
"無料"で貴社に最適な保険プランを提案します。