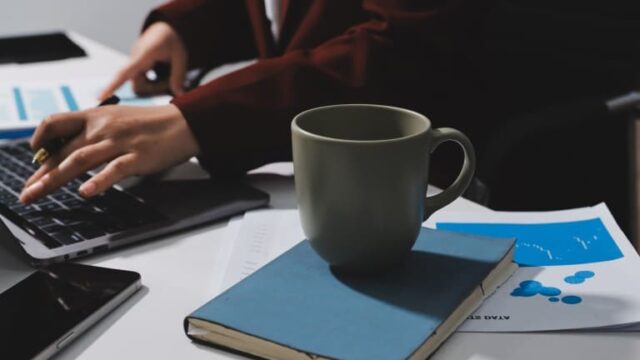副業あるいは個人事業主として始めた事業が軌道に乗ってきたら、法人設立で節税できる可能性があります。
ただし、事業規模や経営体制によっては、法人設立によってかえってコストが上がる場合もあるため、慎重な検討が必要です。
この記事では法人設立で節税できる理由から、メリット・デメリットまでを徹底解説します。
法人化を検討する具体的なタイミングもお伝えするので、キャッシュフローの改善を考えている副業者・事業者の方はぜひ参考にしてください。
法人設立で節税できる理由は?

法人設立によって節税できる理由は、主に以下の2つが挙げられます。
- 税率に違いがあるから
- 所得を分散できるから
税金の種類が所得税から法人税に切り替わることで、税制上の恩恵を受けられる可能性があります。
それぞれ詳しく解説するので、法人税の仕組みを把握しましょう。
理由①税率に違いがあるから
個人事業主と法人を比べると、税率に大きな違いがあります。
個人事業主の所得税率は、所得の額に応じて徐々に税率が高くなる超過累進税率です。
一方、法人税率は定率課税が適用され、課される税率の上限には限度があります。
所得税と法人税の違いをまとめると、次のとおりです。
| 課税所得金額 | 所得税の税率 | 法人税の税率 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 原則23.2% ※中小企業(資本金1億円以下の企業)は800万円までは15% |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | |
| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | |
| 4,000万円超 | 45% |
参照:所得税の税率|国税庁
参照:法人税の税率|国税庁
法人税率はMAXでも23.2%なため、高所得であれば個人事業主より節税できる可能性があります。
理由②所得を分散できるから
法人設立後に自身や家族を役員もしくは従業員にすれば、所得を分散して節税につなげられます。
法人税は会社の課税所得に対して課せられますが、所得を複数人で分けることでトータルの課税金額を少なくできるということです。
たとえば、以下のような状況があったとします。
- 事業所得…1,000万円
- 所得控除※…150万円と仮定
- 中小法人(資本金1億円以下)で法人化
※所得控除…所得税の計算において、所得から差し引くもの(基礎控除や社会保険料控除など)
個人事業主で課税所得金額が1,000万円だった場合、所得税は以下の計算になります。
(1,000万円 – 150万円) × 23% – 63万6,000円 = 131万9,000円
※事業所得から所得控除として50万円が差し引かれるため、課税所得は850万円となり、税率は23%、控除額は63万6,000円となる。
一方、自身を役員として500万円の報酬を支払う場合、課税関係は以下のようにシミュレーションできます。なお、役員報酬には給与所得控除が適用され、年収500万円の場合は144万円です。
【所得税の計算】
(500万円 – 144万円 – 150万円) × 10% – 9万7,500円 = 10万8,500円
※役員報酬から各種控除を差し引くと課税所得は206万円となり、税率は10%、控除額は9万7,500円になります。
【法人税の計算】
500万 × 15% = 75万円
所得税と法人税を合わせると85万8,500円となり、個人事業主だったときの131万9,000円と比較して大きく節税できることがわかります。
注)上記はあくまで概算です。正確なシミュレーションは、税理士など専門家にご相談ください。
法人設立による節税のメリットとデメリット

ここでは、法人設立による節税のメリットとデメリットを解説します。
良い点と悪い点を両方理解することで、事業の成功確率を高めることができます。
メリット
法人設立による節税のメリットは、以下の4つが挙げられます。
- 法人税率を適用できる
- 役員報酬で給与所得控除を使える
- 経費の範囲が広がる
- 相続税の節税につながる
1.法人税率を適用できる
法人税の適用は、法人設立で得られる大きなメリットです。
先述の通り、所得税の税率は最高で45%ですが、法人税は23.2%です。
所得が大きい人ほど、低い税率の節税につながります。
2.役員報酬で給与所得控除を使える
先述したシミュレーションにもあるように、法人設立後に役員報酬を受け取ると、給与所得控除を適用できます。
給与所得控除の金額は収入によって異なります。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| ~1,625,000円 | 550,000円 |
| 1,625,001円~1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
| 1,800,001円~3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円~6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円~8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円~ | 1,950,000円(上限) |
参照:国税庁|給与所得控除
家族に役員報酬を支払う際にも給与所得控除は適用されるので、より節税効果を高められます。
3.経費の範囲が広がる
法人は、個人事業主より経費の範囲が広がります。
経費にできる項目の一例は、以下のとおりです。
- 経営者本人の給与・退職金
- 家族への給与・退職金
- 生命保険料や健康保険料(法人契約に限る)
- 健康診断にかかる費用
- 福利厚生にかかる費用
- 家賃(社宅制度を利用した場合)
- 出張手当
- 慶弔費
課税所得を減らして節税効果を高めるためにも、どのような費用を経費計上できるかチェックしておきましょう。
4.相続税の節税につながる
法人設立は、相続税の節税対策にもなります。
相続税は個人の資産に対して課せられますが、資産を法人に移すことで相続財産から除外可能です。課税対象となる財産が減るため、相続税の節税につながります。
ただし、相続税対策のみを目的とした法人設立は、税務署から否認される恐れがあるため注意が必要です。法人として活動実態や、財産移転時の譲渡価格が適正ではない場合、節税できない場合があります。
相続税対策のために法人設立を検討している方は、事前に税理士などに相談すると良いでしょう。
デメリット
法人設立による節税のデメリットは、以下の4つです。
- 法人設立や維持にコストがかかる
- 確定申告や決算作業が面倒
- 赤字でも納税義務がある
- 廃業時する場合は費用がかかる
1.法人設立や維持にコストがかかる
法人を設立すると、個人事業主より多くのコストがかかります。
株式会社を設立する場合は登録免許税などで30万円程度、合同会社の場合は10万円ほどが必要です。
さらに、法人住民税や社会保険料、顧問税理士を雇う場合はその報酬がかかるので、年間数十万円以上の維持コストが見込まれます。
いずれも高額な出費になるので、資金繰りには注意が必要です。
2.確定申告や決算作業が面倒
法人設立は、確定申告や決算作業といった事務負担が増加します。
個人事業主の確定申告よりも作成しなければならない書類が多く、手続きも煩雑です。税理士に事務作業を代行すれば、負担は軽減されますが報酬を支払わなければなりません。
手間やコストが個人事業主のときより増えるため、節税分の経済的メリットが相殺される恐れがあります。
3.赤字でも納税義務がある
法人を設立した場合、事務所を置く地方自治体に法人住民税を納めます。
法人住民税は「均等割」と「法人税割」の2区分があり、均等割は従業員数や資本金の金額から算出されます。
以下は、均等割の標準化税額です(実際の課税額は自治体によって異なります)。
| 資本金等の額 | 都道府県民税均等割 | 市町村民税均等割 | |
|---|---|---|---|
| 従業者数50人超 | 従業者数50人以下 | ||
| 1千万円以下 | 2万円 | 12万円 | 5万円 |
| 1千万円超1億円以下 | 5万円 | 15万円 | 13万円 |
| 1億円超10億円以下 | 13万円 | 40万円 | 16万円 |
| 10億円超50億円以下 | 54万円 | 175万円 | 41万円 |
| 50億円超 | 80万円 | 300万円 | 41万円 |
参照:総務省|法人住民税
均等割は法人の売上に関係なく課されるため、赤字でも納付義務があることを覚えておきましょう。
法人化を検討すべきタイミング

法人設立はいつでも良いというわけではなく、節税効果を得られるタイミングを見計らう必要があります。
適切な法人設立のタイミングをいくつか紹介するので、いまの事業の状況と照らし合わせてみましょう。
所得額が800万円を超えたとき
利益の観点からいうと、所得額が800万円を超えたとき、法人設立による節税効果が期待できます。
個人事業主の所得税率は所得額900万円以下なら23%以下、900万円を超えると33%です。
一方で法人税の税率は所得額が800万円以下なら15%、800万円以上の場合に23.2%となります(中小法人の場合)。
800万円を超えると法人設立後のほうが低い税率になり、節税できる可能性があります。
年間売上が1,000万円を超えたとき
年間売上が1,000万円を超えたときは、法人設立で消費税を節税できる可能性があります。
年間売上が1,000万円を超えると、その2年後から課税事業者となり消費税の申告・納付義務が必要です。
しかし、個人事業主の年間売上が1,000万円を超えたときに法人化すれば、法人と個人事業は別扱いになります。そのため設立1期目と2期目は2年前の売上がない扱いとなり、消費税の納付義務が発生しないのです。
ただし消費税の納付義務が免除されるためには、資本金1,000万円未満で法人設立する必要があります。また、インボイス発行事業者になると消費税の免税事業者期間は利用できません。
消費税の免除を受けるか課税事業者になるかは、どちらが自社にとって有利なのか十分に検討するようにしましょう。
まとめ

法人設立は定率課税が適用されたり所得を分散したりと、個人事業主にはない節税効果が見込めます。
ただし、会社を設立すれば必ず節税できるとは限りません。
確定申告などの事務作業が頻雑になり、赤字でも納税義務が発生するなど注意点があるのも事実です。
「法人設立でどれほど節税できるかを知りたい」「事務作業をせずに事業に専念したい」という方は、税理士などのプロに相談することをおすすめします。
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス

- 法人保険を経営に活用したい
- いま加入している保険を見直したい
- 退職金制度や福利厚生を導入したい
- 事業承継や相続について考えたい
- 税金対策や財務戦略を相談したい
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて
"無料"で貴社に最適な保険プランを提案します。