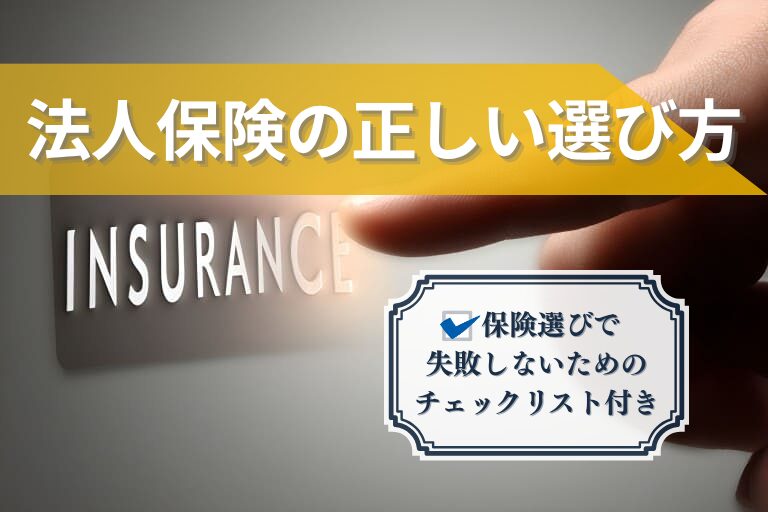個人事業主として活動していると、「法人保険は自分には関係ない」と考える方も多いかもしれません。しかし、実は法人保険の一部は、個人事業主でも加入や活用が可能な商品があります。
事業の安定や将来への備えとして、保険の活用は非常に重要です。法人保険を始めとした保障の導入・見直しは、不安定になりがちな個人事業主こそ考えるべき課題といえます。
本記事では、個人事業主と法人保険について徹底的に解説。個人契約との違いや、個人事業主が保険に加入するメリットをわかりやすくお伝えします。
そもそも法人保険とは?個人契約との違い

法人保険とは、企業が契約者となって加入する保険の総称です。主に企業の経営安定や福利厚生、役員退職金の準備、事業承継対策などに用いられます。
契約形態は「法人契約」であり、保険料の一部または全部が経費として計上できるのが特徴です。また、法人保険は保障額が大きく、節税効果や資産形成機能を兼ね備えた商品が多く販売されています。
一方、個人契約の保険は、文字通り個人名義で加入する保険を指します。個人事業主やフリーランスの場合、保険料は「所得控除」の対象となるものの、経費計上できる範囲も限定的です。
このように、法人保険と個人保険の違いは「契約主体の違い」のほか、税制優遇や活用目的、保障の幅にも大きな違いがあります。
一部の法人保険は個人事業主でも加入できる

保険商品は法人契約を前提としているものの、個人事業主でも実質的に同様の保障内容で加入できる場合があります。実際に加入できるかは、保険商品ごとの加入要件次第です。
ただし、法人保険は「法人(株式会社、合同会社など)」が契約者となることを前提に設計されているため、個人事業主がそのまま加入しても最大限活用できるとは限りません。
保険商品ごとに特性が異なるため、加入するときは保障内容や保険料、キャッシュフローへの影響などをしっかり検討する必要があります。
個人事業主が入れる法人向け保険商品の例
個人事業主にも対応している法人保険の例としては、以下のような種類が挙げられます。
- 終身保険・養老保険・定期保険
- 個人事業主自身の死亡保障、老後資金準備、事業承継資金の準備などを目的として加入する法人保険。
- 収入保障保険
- 個人事業主が万が一働けなくなった場合の収入減をカバーするための法人保険。
- 医療保険・がん保険
- 個人事業主自身の病気やケガによる医療費、がん治療費に備えるための法人保険。
- 傷害保険
- 個人事業主自身のケガによる入院・通院・死亡・後遺障害を保障する法人保険。従業員を雇用している場合、従業員の業務中の事故や通勤中の事故に備えるための「業務災害補償保険」や「総合福祉団体定期保険」のような団体契約もある。
- PL保険(生産物賠償責任保険)
- 製造・販売した製品や提供したサービスが原因で、他人に身体障害や財物損壊を与えてしまった場合の賠償責任を補償する法人保険。
- 施設賠償責任保険
- 事業を行う施設や設備に起因して、他人に身体障害や財物損壊を与えてしまった場合の賠償責任を補償する法人保険。
- 業務災害補償保険(任意労災)
- 従業員を雇用している個人事業主が、政府労災保険の補償だけでは不十分な場合に、上乗せして補償するための法人保険。
これらの法人保険は、「従業員なしの経営者」や「小規模な個人商店」などにも適しており、個人事業主の保障として十分に活用できます。
ただし、商品によっては加入条件や保障内容が法人契約と異なるため、保険会社のサービス窓口での事前相談が重要です。
「個人事業主が保険に加入する3つのメリット

個人事業主が保険を活用する最大の目的は、将来の生活保障と事業の継続性の確保です。
法人保険を上手く活用すれば、リスク対策や退職金の確保、経費計上による節税などが可能になります。
代表的な3つのメリットを解説します。
- 事業のリスクに備えられる
- 退職金代わりにできる
- 経費計上できる(種類や契約内容による)
1.事業のリスクに備えられる
個人事業主にとって、病気・ケガ・災害などによる収入減少は経営上の重大なリスクです。
医療保険や所得補償保険に加入していれば、長期療養時の健康保険の適用外費用や休業中の収入減をカバーできます。また、火災保険や地震保険、さらには事業活動中の損害賠償リスクに対応した補償商品も存在します。
会社に比べて社会保障が限定的な個人事業主にとって、公的保険制度だけに頼らない備えは必須といえるでしょう。
2.退職金や年金代わりにできる
個人事業主には、会社員のような退職金制度が存在しません。その代替手段として、法人保険で「自分自身の退職金」を準備する方法があります。
たとえば、勇退時期に合わせて解約返戻金※1や満期返戻金※2を受け取れるよう契約プランを設計すれば、計画的にまとまった資金を受け取れます。保険期間中は保障も確保できるので、万一の事態にも安心です。
※1解約返戻金…保険を途中解約するとき、保険会社から払い戻されるお金。
※2満期返戻金…保険期間中に保険事故(保険金の支払い)がないまま満期を迎えたとき、保険会社から支払われる保険金。満期保険金ともいう。
また、商品によっては保険金の年金形式で受け取れる場合もあります。勇退時にまとめて受け取るか、老後の生活資金として少しずつ受け取るか、ライフプランに応じて選びましょう。
3.経費計上できる(種類や契約内容による)
保険商品によっては、支払った保険料を「必要経費」や「損金」として計上できる場合があります。
たとえば、医療保険は「生命保険料控除」、小規模企業共済は「所得控除」として税申告が可能です。
ただし、すべての保険が経費計上できるわけではなく、保険の種類や契約内容に左右されます。判断に迷う場合は、税理士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
保障の幅を広げたいときの対処法

「個人事業主で加入できる法人保険だと物足りない」「もっと保障の幅を広げたい」と感じる個人事業主は、以下2つの対処法も検討してみましょう。
マイクロ法人を設立する
個人事業主が法人保険を本格的に活用したい場合、マイクロ法人の設立も選択肢の1つです。マイクロ法人とは、代表者1人または少人数で運営する小規模な法人形態で、近年フリーランスや副業者を中心に注目されています。
マイクロ法人を設立することで、法人保険に正式に加入でき、保険料を会社の経費として計上可能になります。また、社会保険の加入義務が発生し、厚生年金や健康保険の適用が受けられる点も大きなメリットです。
ただし、法人設立には初期費用や維持コストがかかるほか、手続きや税務処理も複雑になります。また、事業実態が伴わない場合は「ペーパーカンパニー」として税務上の指摘を受けるリスクもあるため、制度や目的をしっかり理解したうえで活用しましょう。
共済制度を活用する
保障確保が目的であれば、法人保険だけでなく国の共済制度も選択肢となります。
個人事業主が入れる主な共済保険は以下の通りです。
| 共済名 | 内容 | 管轄組織 |
|---|---|---|
| 小規模企業共済 | 個人事業主やその共同経営者、小規模企業の役員が対象。廃業や退職時の生活資金を積み立てる。 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 |
| 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済) | 個人事業主または会社で「中小企業者」にあてはまる事業者が対象。取引先の倒産リスクに備えるための共済制度。 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 |
| 各種団体の共済 | 各種団体が、その会員向けに独自の共済制度を提供しているケース。福利厚生や死亡・医療保障を目的としたものが多い。 | 商工会、商工会議所、協同組合など |
| 中小企業退職金共済制度(中退共) | 従業員を雇用している場合、その退職金資金を積み立てる共済。個人事業主本人は加入不可。 | 独立行政法人勤労者退職金共済機構 |
種類によって個人事業主の経費(必要経費)または所得控除の対象となります。
法人保険と共済制度をうまく組み合わせれば、より手堅い保障体制を整備できます。事業規模や業種、個人のライフプランに応じて検討してみましょう。
まとめ

個人事業主でも、法人保険と同様の効果を持つ保障や制度を十分に活用することが可能です。また、マイクロ法人を設立して法人契約を結んだり、共済制度を活用したりと、目的や経営状況に応じて取れる選択肢は多岐にわたります。
ビジネスが不安定になりがちな個人事業主にとって、年金・医療・退職金・事業リスクといった「将来の不安」を軽減するためには、情報収集と早めの制度活用がカギとなります。
経費計上や所得控除などの節税メリットも含め、信頼できる専門家への相談を通じて、自身に合った保障の形を構築していきましょう。
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス

- 法人保険を経営に活用したい
- いま加入している保険を見直したい
- 退職金制度や福利厚生を導入したい
- 事業承継や相続について考えたい
- 税金対策や財務戦略を相談したい
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて
"無料"で貴社に最適な保険プランを提案します。