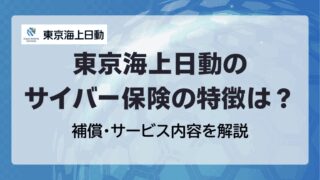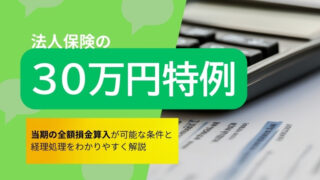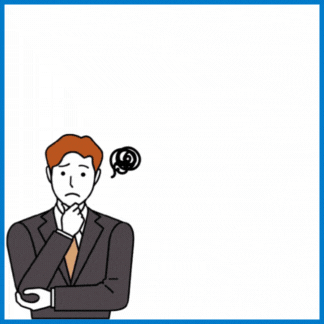企業にとって経営者や役員の存在は欠かせないものです。
日々の会社経営と並行して、退職金の準備をしっかりと整えておくことは、中長期的に見れば会社の業績を向上させることにもつながっていきます。
退職金は、手順とルールに沿って進めることが重要です。一方で、役員退職金をどう設定していいのか悩むこともあるでしょう。
そこで本記事では、役員退職金を用意する際の注意点や、損金算入の観点で押さえておきたい実務ポイントについて解説します。
順序立てて考えよう!役員退職金を決める流れ
1.まずは前提を押さえる(規程・基準づくりの重要性)
役員退職金は、客観的に見て支給の合理性が説明できるよう、合理的な基準づくりが重要です。そのために「退職金規程(退職慰労金規程)」を定めておきましょう。
支給にあたってトラブルを未然に防げるほか、税務上の説明を行う際の根拠資料にもなります。
退職金はまとまった金額を支給するものですから、損金として取り扱うためには税務上のポイントを押さえておく必要があります。
なお、死亡時に支給する弔慰金についても、社内規程や支給根拠を整備しておくことで、税務上の説明がしやすくなります。弔慰金は支給目的や金額の相当性(社会通念)などにより取扱いが変わる点に注意が必要です。
2.「退職の事実」を明確にする(実質退職の考え方)
退職金は、形式上の退職だけで受け取れるとは限りません。
実質的な退職の事実が重要であり、役員報酬の状況や勤務状況、経営への関与の度合いなどから判断されます。
また、役員が退任せずに職務を変更するケースでも、職務内容が大きく変わり、実質的に退職したのと同様の事情があると認められる場合には、退職給与として取り扱えることがあります(例:常勤役員が非常勤役員になる、取締役が監査役になる等)。ただし、判断は個別事情によります。
退職の事実が認められない場合には、会社側で損金算入できなくなる可能性があるだけでなく、個人側でも退職所得ではなく給与所得として扱われるなど、課税関係が変わることがあります。
一方で、退職の事実を適切に整理できれば、支給した退職金を会社は損金として算入でき、個人も退職所得として申告できる可能性が高まります。
3.社内手続を整える(規程・決議・議事録)
中小企業の場合、退職金規程を作成していないケースもありますが、税務上のリスクを回避したり、死亡退職金を巡って遺族とトラブルになったりすることを防ぐためにも、規程を作成しておくことは重要です。
退職金規程に盛り込む内容としては、支給時期・支給の決定方法・退職金の計算基準・功績倍率・退職金の増減についての取り決めなどです。
また、役員が死亡したときの退職金の取り扱いや弔慰金の取り決めについても、整理しておきましょう。
4.金額を設計する(「適正額」を意識する)
退職金額をいくらにするのか検討する際のポイントは、税務上、損金として否認されにくい金額を設計することです。
同業種・同一規模・同一エリアといった観点で、同業他社の水準や会社の状況と比べて「適正」と説明できる金額かどうかが重要になります。
役員の在任期間や会社への貢献度などを総合的に見て、最終的な金額を決めましょう。
5.原資を準備する(方法を決め、計画を立てる)
退職金を支給する目安の時期を決め、現状で退職金にあてられる原資がどれくらいあるかを確認します。
不足がある場合は、どのように準備していくのかスケジュールを立てるようにします。事業承継や相続を意識して退職金を設計する場合は、特に計画性が重要です。
退職金原資の準備方法として、法人保険を活用することも選択肢の一つです。
ただし、生命保険を退職金原資として充てる場合、支払った保険料の一部または全部が損金算入できるとは限りません。契約内容(受取人、保険種類、最高解約返戻率、年換算保険料など)により、保険料の一部を資産計上し、残りを損金算入する取扱いとなる場合があります。
また、一時的に資金繰りが悪化してしまった場合に備え、契約者貸付制度などの仕組みを持つ保険もあります。いずれにしても、必要以上に高い保険料の契約にすることは避けたほうが無難です。
業績が好調なときの水準で設計してしまうと、資金繰りが苦しくなった際に保険料負担が重くなるおそれがあります。
退職金原資としてどの程度の金額を準備するのかを明確にし、会社の状況に合った方法で進めていきましょう。
法人税法における役員の範囲とは?
法人税法上の「役員」は、取締役・執行役・会計参与・監査役のほか、理事・監事・清算人なども含まれます。
また、取締役等の肩書がなくても、相談役・顧問などとして実質的に経営に従事している場合や、同族会社の使用人で一定の要件を満たし経営に従事している場合などは、法人税法上「役員」に該当することがあります。
上限はない?役員退職金の基本的な考え方
役員退職金については、法律上の上限額というものはありません。
しかし、損金として算入できるかという視点で見れば、不当に高額な役員退職金は損金として認められない場合もあります。
基準としては同業他社と比べて、退職金の額が適正かといった点が判断要素となります。
したがって、税務上は無制限に役員退職金を損金に算入できるわけではなく、「適正額」を意識して設計する必要があります。
役員退職金を計算する方法としては「功績倍率法」を用いるのが一般的です。
功績倍率法を用いたうえで、同業他社の退職金支給額を参考にしていきます。参考とする基準は地域や業種、退職時期や売上金額などです。退職事由・所得金額・在籍年数なども考慮されます。
ただ、あらかじめ税務当局が認定する役員退職金の適正な額を確定的に把握することは困難です。
そのため、職務内容や会社への貢献度を整理したうえで、説明可能な支給額を決めていくことが無難だと言えるでしょう。
また、退職金規程を作成するときには、不正行為が事後的に発覚した場合の取り決めも盛り込んでおくことが大切です。
役員が退職後に問題が発覚したときに、何の取り決めもなければトラブルのもとになってしまいます。
退職金の減額や不支給の判断を行いやすいように「退職金の支払い時期を一定期間後にする」など、あらかじめ備えておくことも検討しましょう。
そして、退職金を支給してから不正行為が発覚したときの取扱いについても、社内ルールとして整理しておくことが重要です。退職金制度を健全に維持していくためには、ルールづくりが欠かせません。
役員の退職金を損金算入するための計算方法
役員退職金を損金算入の観点で検討する際の計算方法として、代表的には「平均功績倍率法」と「最高功績倍率法」が挙げられます。
平均功績倍率法を使った役員退職金の計算方法は、次の式で表すことができます。
最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率
ポイントとしては、役員在任年数を重視している点です。会社への功績を推し量るうえで、在任年数が長いほど功績が大きいと整理されやすいからです。
一方、最高功績倍率法では次の式を用います。
最終報酬月額×役員在任年数×最高功績倍率
功績倍率とは会社への貢献度を倍率で示したものであり、役職によって異なります。たとえば、代表取締役で在任期間が30年、最終報酬月額が80万円、功績倍率を3倍とすると、80万円×30年×3倍で役員退職金は7,200万円となります。
なお、役員退職金の支給方法には、一時金(一括・分割を含む)や年金形式などの選択肢があります。実際の支給方法は、社内規程や決議内容、個別の合意に沿って決まります。
退職金の支給により一時的に大幅な赤字とならないよう、支給方法や支給時期を含めて設計することが大切です。
また、保険の解約返戻金を退職金原資として活用する場合は、返戻金を受け取る年度の益金と、退職金支給年度の損金の関係を踏まえ、年度設計を行うことがポイントになります。
役員退職金の金額を決めるときには、会社が損金算入できる範囲、そして受け取り時の税負担(退職所得の取扱い)を把握したうえで決めることが大切です。
損金算入できる範囲で決めるのが重要
経営者や役員が退任するタイミングは、個人にとっても会社にとっても重要な節目です。
円滑に退任し、退職金を支給できる仕組みを整えておくことは、経営においても重要だと言えるでしょう。
ただし、役員退職金は自社のなかだけで決めれば良いというものではありません。
税務上の損金算入の問題を意識したうえで、適正な退職金額を決めていく必要があります。
過大な退職金は損金として算入できない可能性があるだけでなく、受け取る側にとっても税負担が増える要因になり得ます。
退職金規程をきちんと定めて、客観的な視点で見たときにも支給が適正であると示せることを意識しましょう。
退職金規程を定めておくことは、死亡退職金の支給時に遺族とのトラブル回避にも役立ちます。
そして、役員退職金とは別に、各種保険や共済制度(中小企業倒産防止共済・小規模企業共済など)を活用することも検討してみましょう。
計画的に活用することで、退職金を準備したり積み増したりする原資を確保しやすくなる場合があります。
役員退職金の準備は長期間にわたり行っていくものです。自社に合った退職金制度の在り方を見極め、同業他社の水準なども参考にしつつ、役員の在任年数や会社への貢献度を適正に判断して金額を決めていきましょう。
役員退職金は、損金算入が認められる範囲に留めることを意識しながら、経営者や役員が安心して退任できる環境を整えていくことが大切です。
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス

- 法人保険を経営に活用したい
- いま加入している保険を見直したい
- 退職金制度や福利厚生を導入したい
- 事業承継や相続について考えたい
- 税金対策や財務戦略を相談したい
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて
"無料"で貴社に最適な保険プランを提案します。