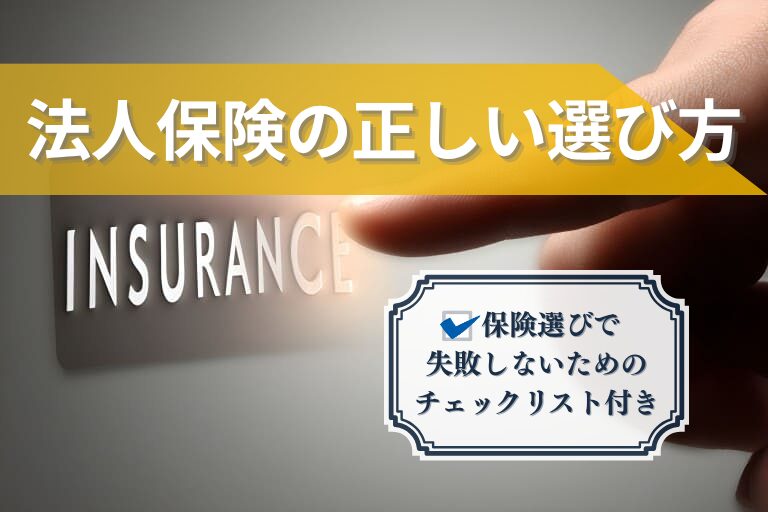「保険料の経理処理はどうすればいい?」
「法人保険の損金算入って何?」
経営者や財務担当者の方で、上記のような疑問を持つ方も少なくありません。
かつては保険料の“全額損金”が当然のように活用されてきましたが、2019年の税制改正によりルールは大きく変わりました。
この記事では、法人保険の損金算入ルールの基本から、保険のタイプ別の判断基準まで、実務に役立つよう解説します。
保険を経営の武器として活かすために、正しい知識を押さえておきましょう。
そもそも「損金算入」とは?法人保険と税務におけるルールについて
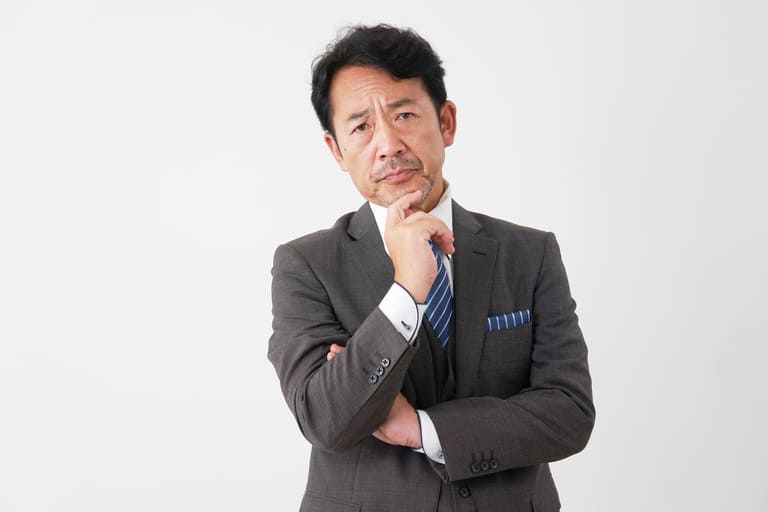
税務における「損金」とは、収益を得るために必要な費用や損失を指します。損金に該当する支出は課税所得から控除され、結果的に法人税の負担を軽減できます。
法人が契約者となる「法人保険」も、一定の条件を満たせば保険料の一部を損金算入が可能です。税制改正によりルールが厳しくなりましたが、2025年現在も税金対策として一定の効果が期待できます。
返戻率・保障内容・契約内容で税務上の処理方法が変わる
法人保険における損金算入ルールは、解約返戻率や契約内容などによって異なります。
特に、解約返戻率が高い保険や、保障期間が長期にわたる保険では、保険料の一部を資産計上しなければいけません(資産として計上した分は一定期間後に損金として取り崩し)。
法人保険を契約するときは、対象となる保険商品の特徴を十分に理解し、税務上の取り扱いを確認することが重要です。
2019年の税制改正後における損金算入ルールと経理処理の例

法人保険の損金算入ルールは、2019年の税制改正に大きな影響を受けました。改正前は保険料の全額損金算入も容易でしたが、改正により以下のようなルールが定められます。
定期保険の場合:解約返戻率に応じて資産・損金の割合を判定
定期保険(期間に定めがある保険)は、期間中の最高解約返戻率次第で資産・損金の割合が決まるルールになっています。
最高解約返戻率ごとに定められた資産計上期間に従い、保険料の一部を資産として計上します。その後、取り崩し期間に分割して損金算入します。
具体的な内容は以下の通りです。
| 最高解約返戻率 | 資産計上期間 | 資産計上額 | 取崩期間 |
|---|---|---|---|
| 50%以下 | なし | なし | なし |
| 50%超〜70%以下 | 保険期間開始日から40%を経過するまで | 保険料の40% | 保険期間の75%経過後から終了日まで |
| 70%超〜85%以下 | 保険期間開始日から40%を経過するまで | 保険料の60% | 保険期間の75%経過後から終了日まで |
| 85%超 | 次のいずれか長い期間まで ①保険期間開始日から最高解約返戻率となる期間の終了日まで ②①の期間経過後で「(当年の解約返戻金相当額-前年の解約返戻金相当額)÷年換算保険料相当額」が70%を超える期間 |
保険期間開始日から10年経過するまでは「保険料×最高解約返戻率の90%」、11年目以降は「保険料×最高解約返戻率の90%」 | 解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間経過後から保険期間終了日まで |
最高解約返戻率が高い、つまり貯蓄性の高い保険商品ほど契約前半における資産計上の割合が大きくなり、税金対策の面では不利になります。
定期保険の経理処理例
- 保険料:年額100万円(毎年払込)
- 保険期間:20年
- 最高解約返戻率:80%
- 保険対象が店舗併用住宅
| 時期 | 借方科目 | 貸方科目 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 資産計上期間中(20年の40%経過まで=8年目まで) | 支払保険料 600,000円 前払保険料 400,000円 |
現金・預金 1,000,000円 | 支払保険料のうち、60%を損金、40%を資産として計上 |
| 資産計上期間の終了後 | 支払保険料 1,000,000円 | 現金・預金 1,000,000円 | 支払保険料の全額を損金算入 |
| 取り崩し期間(20年間の75%経過後以降=16年目以降) | 支払保険料 1,640,000円 | 現金・預金 1,000,000円 前払保険料 640,000円 |
年間の保険料に加えて、前払保険料に累計を残りの保険期間で分割して損金算入 1年当たりの取り崩し金額:(400,000円×8年)÷5年=640,000円 |
※解約返戻金もしくは死亡保険金の受取時、それまでの資産計上分を取り崩し、差額を雑収入もしくは雑損失として計上。
養老保険の場合:一定の要件を満たせば半額の損金算入が可能
養老保険とは、死亡したときは死亡保険金、満期まで生存したときは同額の満期保険金が支払われる保険です。
保険金の受取人によって、適用される損金算入ルールが異なります。
| 受取人 | 保険料の経理処理 |
|---|---|
| 死亡保険金・満期保険金どちらも法人の場合 | 保険料積立金として全額資産計上 |
| 死亡保険金・満期保険金どちらも被保険者またはその遺族の場合 | 給与として全額損金算入(被保険者は所得税課税/生命保険料控除の適用) |
| 死亡保険金が被保険者の遺族、満期保険金が法人の受取の場合 | 福利厚生費として半額を損金算入、保険料積立金として半額を資産計上 |
※福利厚生費とみなすには普遍的加入(役員および従業員の全員を対象にすること)が必要で、要件を満たさない場合は給与として扱われる。
一般的には、福利厚生費としての要件を満たし、半額を損金算入するプランが利用されます。
養老保険の経理処理例
- 保険料:年額100万円(毎年払込)
- 死亡保険金の受取人:被保険者の遺族
- 満期保険金受取人:法人
- 福利厚生プランとして契約(全役員・全従業員が加入対象)
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 保険料積立金 500,000円 福利厚生費 500,000円 |
現金・預金 1,000,000円 |
※遺族に死亡保険金が支払われた場合、保険料積立金は雑損失として計上。満期保険金もしくは解約返戻金の受取時は保険料積立金を取り崩し、差額を雑収入か雑損失として計上。
第三分野保険:保険の種類などで適用されるルールが異なる
第三分野保険とは、生命保険(第一分野)と損害保険(第二分野)に属さない保険を指し、医療保険・がん保険・介護保険などが該当します。
第三分野の法人保険における損金算入ルールは、受取人によって処理が異なります。
| 受取人 | 保険料の経理処理 |
|---|---|
| 法人の場合 | 福利厚生費として計上(普遍的加入など要件あり) |
| 被保険者やその遺族の場合 | 給与として計上 |
また、保険の種類によって損金算入の割合が変わります。
| 解約返戻金がある場合 | 定期保険の経理処理に準じる |
|---|---|
| 役員・従業員が被保険者、保険金受取人が法人 | 原則として全額損金算入可能 |
| 役員・従業員が被保険者、本人または遺族が保険金受取人 | 福利厚生の要件を満たすことで全額損金算入可能(満たさない場合は給与扱い) |
| 終身タイプで短期払い | 一部損金算入(年間保険料が30万円以下なら全額損金算入) |
※短期払い…保険期間より短い期間で保険料の支払いを完了すること。
終身で短期払いのケースでは、「年間保険料×払込期間÷保険期間」で計算した金額を損金に、残りを資産として計上します。なお、ここでいう保険期間は「116歳-契約年齢」で算出した年数とみなします。
払込期間の終了後は、116歳になるまで上記で計算した金額を損金算入するとともに、同額で資産計上分を前払い保険料として取り崩します。
第三分野保険の経理処理例
- 保険料:年額100万円(毎年払込)
- 受取人:法人
- 保険期間:終身
- 払込期間:5年(短期払い)
- 契約年齢:50歳
| 時期 | 借方科目 | 貸方科目 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 払込期間中(1~5年目) | 支払保険料(損金処理) 75,757円 前払保険料(資産計上) 924,243円 |
現金・預金 1,000,000円 | 支払保険料:1,000,000円×5年÷(116歳-50歳)=75,757円 |
| 払込期間終了後(6年目以降) | 支払保険料 75,757円 | 前払保険料 75,757円 |
一部の定期保険や第三分野保険は「30万円特例」の対象
ここまで解説した保険のうち、一部の定期保険および第三分野保険には「30万円特例」という例外ルールが存在します。
年間の支払保険料が1人あたり30万円以下の場合、保険料の全額を損金算入できるというルールです(定期保険は最高解約返戻率が70%以下が条件)。
ただし、被保険者が加入するすべての保険の保険料を合算して判定するため、複数の保険商品に加入している場合は注意しましょう。
税務調査で否認される典型パターンと対策

法人保険の損金算入ルールは複雑ですが、適切に処理しなければ税務調査の対象となり、損金算入が否認される恐れがあります。
税務調査において否認される典型的なパターンとして、以下のようなケースが挙げられます。
- 資産計上が必要な保険にもかかわらず、全額を損金算入にして不当に税負担を減らしている。
- 税務上の取扱いが変更されたにもかかわらず、旧来の処理を継続している。
- 被保険者の給与に対して保険料が高く、経済的な合理性がない。
- 一部の役員のみ対象としているなど、福利厚生の要件を満たしていない
これらのリスクを回避するためには、以下のような対策が有効です。
- 契約前に税理士へ必ず相談する
- 契約時の設計内容によっては、想定と異なる処理が必要になる場合があります。専門家の意見を踏まえて正確な処理方法を確認しましょう。
- 節税効果をうたった営業トークに注意
- 税負担の軽減を主目的とした保険の販売・勧誘は規制されています。節税を強調した営業トークは鵜呑みにせず、内容をしっかりと検討しましょう。また、信頼できる保険代理店のFPに相談することも大切です。
- 帳簿と保険証券の整合性を保つ
- 税務調査では、書類の整合性と経理処理の妥当性を見られます。記帳内容、保険証券、契約書などに食い違いがないようにしましょう。
よくある質問とその回答(FAQ)

返戻金がある法人保険はすべて資産計上?
いいえ、すべてではありません。返戻率が一定水準を超える場合に、一部を資産計上する必要があります。
たとえば、定期保険や第三分野の場合、最高解約返戻率が50%未満なら全額損金処理が可能です。
また、年間支払保険料が30万円以下の場合も全額損金となる「30万円特例」もあります。
節税効果を狙うなら全額損金の法人保険にすべき?
一概にそうとは言えません。確かに全額損金になる法人保険は短期的な節税効果がありますが、解約返戻金がほとんどないなど、長期的な資産形成には向いていない場合があります。
また、解約返戻金や保険金の受取時には益金として計上する必要があるため、総合的な税負担は減らない点にも注意が必要です(法人保険による損金算入はあくまで「課税の繰延」)。
企業の財務状況や目的(資金準備、保障、税金対策)のバランスを考慮し、慎重に選ぶことが大切です。
役員が受取人でも損金処理はできる?
基本は可能ですが、場合によります。役員が保険金の受取人である場合、その支払が「経済的利益」とみなされ、役員報酬や退職金と同様に課税対象となるケースがあります。
また、法人が保険料を支払っていても、契約内容によっては個人受取と判断され、損金として処理できないこともあります。
契約時点で適切にプラン設計を行い、合理的な根拠のもと処理することが重要です。
まとめ|法人保険の損金算入は「返戻率と契約条件」がカギ

法人保険の損金処理は、返戻率や契約内容、保険の種類により取り扱いが大きく異なります。
2019年の改正後のルールでは、原則として「高返戻率=資産計上」という考え方が基礎となっており、節税(恒久的な税負担の軽減)としての効果は期待できません。
正確な損金処理のためには、信頼できる専門家に相談し、税制と契約条件をしっかり理解することが不可欠です。自社の経営状況に適した商品を選び、法人保険を有効な経営ツールとして活用しましょう。
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス

- 法人保険を経営に活用したい
- いま加入している保険を見直したい
- 退職金制度や福利厚生を導入したい
- 事業承継や相続について考えたい
- 税金対策や財務戦略を相談したい
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて
"無料"で貴社に最適な保険プランを提案します。