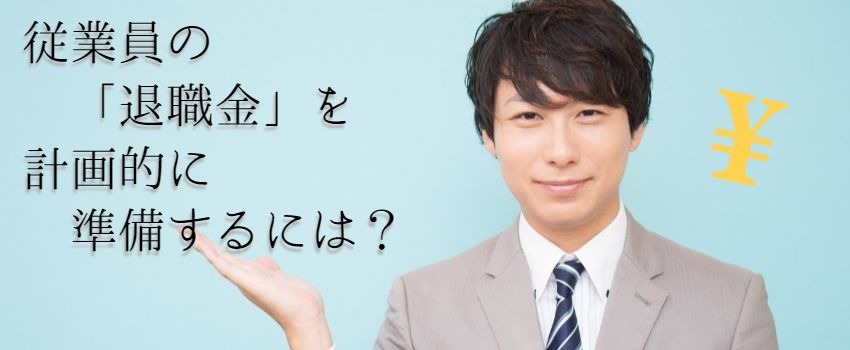中小企業の経営者や役員の皆さま、退職金の準備は進んでいますか?経営者自身の老後の備えや、福利厚生による従業員のモチベーションアップなどにつながる退職金制度は、企業によって重要な課題です。
そんな中、近年は保険を活用した退職金の積立が注目されています。
本記事では、保険を利用した退職金準備の仕組みやメリット・デメリット、導入時の注意点などを詳しく解説します。将来の安心のため、また従業員の福利厚生として、ぜひ参考にしてください。
退職金の代わりに保険を使うとはどういうこと?

「退職金代わりに保険を使う」とは、退職金の積立先として保険に加入することを意味します。
保険には「解約返戻金」や「満期保険金」など、解約や満期によって保険会社からお金が払い戻される商品があります。つまり、保険料は積立金と同じ性質を持つということです。
このような「貯蓄型の保険」を活用すれば、法人は無理なく退職金の原資を準備できます。
退職金代わりに保険を活用する仕組み
退職金代わりに保険を活用する場合、法人が契約者となり、経営者や役員、従業員を被保険者として生命保険に加入します。
保険料は法人が支払い、契約期間中に積み立てられた解約返戻金や満期保険金を、退職時の退職金として支給します。
さらに、法人名義から退職者の個人名義へ変更することで、保険契約をそのまま現物支給することも可能です。また、一括ではなく年金形式での受取もできます。
老後の保障確保や相続対策など、法人・個人両方のニーズに合わせて柔軟に制度設計できる点が特徴です。
他の退職金準備制度との比較
退職金の準備方法には、保険以外にもさまざまな制度があります。
主な制度とポイントは以下の通りです。
- 法人保険
- 自由度が高く、契約内容によって保障と貯蓄を両立できる。税務リスクがあるため、ルールに則った制度設計が重要。
- 中退共
- 公的制度で安心感があり、掛金全額を損金として計上可能。途中解約やカスタマイズ性に乏しい点がデメリット。
- 確定給付企業年金
- 安定した福利厚生制度を提供したい企業に向いている。給付額が確定しているため企業側の責任が重く、中小企業では導入・維持のハードルが高い傾向。
- iDeCo/企業型DC
- 年金制度として優秀だが、「退職金」として一括支給はできない。
- 厚生年金基金
- 法改正により廃止。
各制度の特徴を理解し、自社に最適な方法を選択することが重要です。
退職金代わりに保険を活用するメリット

ただ退職金を積み立てるだけなら、他の制度や貯蓄でも対応は可能です。しかし、保険を活用することで以下のようなメリットを得られます。
保険料の損金処理によって税金対策につながる
法人が支払う保険料は、条件を満たすことで全額または一部を損金算入可能です。これにより、法人税の課税所得を減少させ、税負担の軽減につながります。
ただし、解約返戻金や満期保険金を受け取る際には益金として計上されるため、あくまで「課税の繰延」であることに注意しましょう。
恒久的な税金の削減はできませんが、課税の繰延により資金繰りの安定化や利益調整に効果があります。
資金を計画的に積み立てられる
保険に加入することで、退職金の原資を計画的に積み立てられる点もメリットです。契約時に返戻率(支払済保険料に対する返戻金の割合)の推移を把握できるため、何年目にいくら積み立てられるかの計画が立てやすく、将来的な支給額を逆算できます。
また、毎月あるいは年単位で定期的に保険料を支払う仕組みを作ることで、先々の支出を織り込んだ綿密な資金計画を作れます。
さらに、契約者貸付制度※のある保険商品なら保険会社から融資を受けられるため、急な資金ニーズにも柔軟に対応可能です。
“保障”と“貯蓄”の両立が可能
保険が他の退職金制度と異なるのは、死亡保障や高度障害保障などを兼ね備えていることです。
たとえば、逓増定期保険では契約初期から高額な死亡保険金が設定されており、被保険者が万一の際には遺族や会社が保険金を受け取れます。死亡退職金としての役割はもちろん、経営者や役員などキーパーソンが亡くなったときの事業保障、事業承継や相続にかかる費用の捻出など、その用途はさまざまです。
“保障”と“貯蓄”の両立が保険ならではの魅力であり、単なる資金積立以上の価値となります。
退職金代わりに保険を導入するときの注意点

さまざまなメリットがある保険ですが、退職金代わりに活用する際は以下のような注意点もあります。
解約返戻金のピーク時期と退職時期のズレに要注意
解約返戻金の推移は保険商品や契約内容によって異なり、一定期間を過ぎると低下する場合もあります。
たとえば、逓増定期保険というタイプは5~10年後、長期平準定期保険というタイプは10~30年後がピークの目安です。どちらも満期になると返戻金は0円まで下がります。
退職時期と解約返戻金のピーク時期がずれると、想定よりも少ない金額しか受け取れないため、契約時にしっかりと計画を組む必要があります。
過大な退職金設定は税務調査の対象になる恐れ
退職金の金額が過大と判断されると、税務調査の対象となり、損金算入が否認されるリスクがあります。
適正な退職金額を設定するためには、各種規程を整備し、業界水準や退職者の貢献度を考慮した算定基準を定めることが大切です。
保険商品の比較やプラン作成と合わせて考える必要があるため、法人コンサルティングに特化したFPなどにアドバイスをもらいましょう。
よくある質問(FAQ)

どの保険商品が退職金向き?
退職金の準備に適した法人向け保険商品には、逓増定期保険、長期平準定期保険、養老保険などがおすすめです。それぞれ特徴が異なるため、企業の目的や財務状況に応じて最適な商品を選択することが重要です。
役員退職金を個人が受け取る場合、課税はどうなる?
役員退職金を個人が受け取る場合、退職所得として扱われ、一定の控除が適用されます。ただし、支給額が過大と判断されると、一部が給与所得として課税される可能性があるため、適正な金額設定が必要です。
退職金や保険料の相場はいくら?
退職金や保険料の金額はケースバイケースなため、決まった相場はありません。
たとえば、中小企業の役員退職金として20年間で5,000万円を積み立てる場合、月に約20万円が必要です。保険の解約返戻率を80%と考えた場合、プラスで5万円程度かかります。
実際に退職金制度を導入する際は、被保険者となる個人の役職や貢献度、企業の業種や財務指標など、さまざまな観点を考慮したうえで保険を選ぶ必要があります。
まとめ

保険を活用した退職金の準備は、計画的な資金積立や税制上のメリット、保障機能の付加など、多くの利点があります。
一方で、制度設計に失敗すると損失を被る恐れもあるため、導入時は慎重な検討が必要です。
FPなどの専門家にも相談し、自社の状況に最適な方法で老後の安心や福利厚生の充実を実現しましょう。
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス

- 法人保険を経営に活用したい
- いま加入している保険を見直したい
- 退職金制度や福利厚生を導入したい
- 事業承継や相続について考えたい
- 税金対策や財務戦略を相談したい
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて
"無料"で貴社に最適な保険プランを提案します。