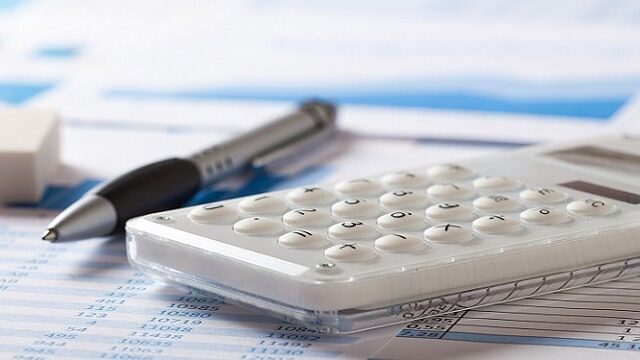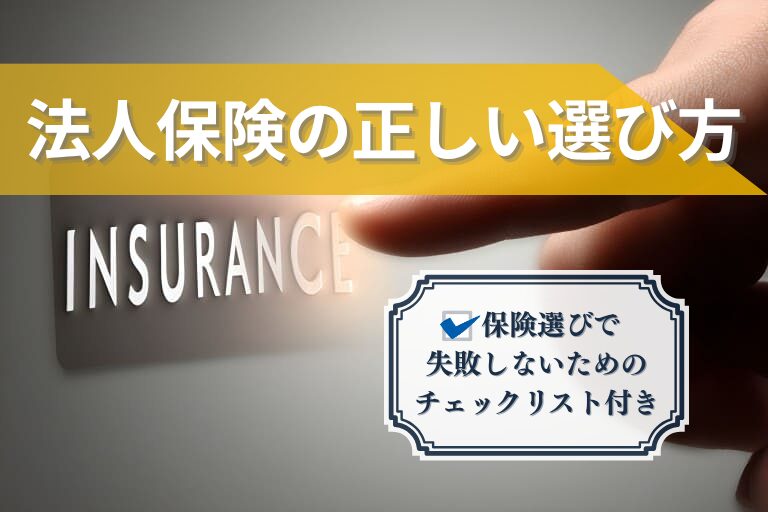積立型の法人保険は、資産形成や退職金準備、経営者の保障など複数の課題を解決できる便利な経営ツールです。
一方で、税務上の損金算入ルールが複雑であり、これが積立型法人保険の導入障壁となっている企業も少なくありません。
本記事では、積立型法人保険の仕組みや、企業経営者向け視点でのメリット・デメリットをお伝えします。
積立型法人保険を最大限活用するための知識を解説するので、経営者や財務・総務担当者の方はぜひご覧ください。
積立型法人保険の仕組みと活用目的

積立型法人保険は、企業が契約者となる保険商品のうち、貯蓄効果があるものを指します。
保険料の一部が保険会社によって積立・運用され、将来的に「解約返戻金」や「満期保険金」として払い戻される仕組みです。
主な活用目的としては、以下の5つが挙げられます。
- 退職金や年金代わりの資産準備
- 経営者・役員の保障の確保(死亡/疾病)
- 事業承継や相続への備え
- 売上減少などの経営リスクに対する事業保障
- 節税対策による税負担の平準化(課税の繰延)
保障と貯蓄を両立できるため、万が一に備えつつ資産形成も行いたい企業に人気のある保険タイプです。
有期型と終身型の違い
法人向け積立型保険には大きく分けて「有期型」と「終身型」があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
有期型の法人保険
有期型の法人保険は、保険期間に定めがあり、期間満了で保障が終了します。
メリットは保険料の相場が低く、費用負担を抑えつつ保障を確保できることです。また、保険料を損金算入できるため、節税(課税の繰延)効果が得やすい点も特徴です。
一方、デメリットは解約返戻率※も低めであることで、貯蓄効果のみを見ると終身型にやや劣ります。
※解約返戻率…それまでに支払った保険料総額に対する解約返戻金の割合。
まとめると、有期型は「損金算入しやすい・短期的な財務戦略に使いやすい」ことが特徴で、主に決算対策や短中期の資金調整に向いている法人保険となります。
- 定期保険
- 養老保険
- 逓増定期保険
- 長期平準定期保険 など
終身型の法人保険
終身型の法人保険は、保険期間に定めがなく、保障が一生涯続きます。
メリットは解約返戻率が高く設計されており、長く加入するほど積立効果も増加していくことです。
デメリットは保険料の高さで、有期型以上にキャッシュフローへの影響を考慮する必要があります。また、保険料は基本的に損金算入できないため、節税(課税の繰延)効果は得られません。
まとめると、終身型の法人保険は長期安定運用向きで、主に相続・事業承継、資産移転の手段として有効な法人保険です。
- 終身保険
- 変額終身保険
- 終身型の医療保険やがん保険 など
積立型法人保険の税制(損金算入ルール)
積立型法人保険の税制では、基本的に貯蓄性が高いほど損金算入が制限されます。
大まかなルールは下記の通りです。
| 最高解約返戻率 | 資産計上期間 | 資産計上額 | 取崩期間 |
|---|---|---|---|
| 50%以下 | なし | なし | なし |
| 50%超〜70%以下 | 保険期間開始日から40%を経過するまで | 保険料の40% | 保険期間の75%経過後から終了日まで |
| 70%超〜85%以下 | 保険期間開始日から40%を経過するまで | 保険料の60% | 保険期間の75%経過後から終了日まで |
| 85%超 | 次のいずれか長い期間まで ①保険期間開始日から最高解約返戻率となる期間の終了日まで ②①の期間経過後で「(当年の解約返戻金相当額-前年の解約返戻金相当額)÷年換算保険料相当額」が70%を超える期間 |
保険期間開始日から10年経過するまでは「保険料×最高解約返戻率の70%」、11年目以降は「保険料×最高解約返戻率の90%」 | 解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間経過後から保険期間終了日まで |
※最高解約返戻率が70%以下で、被保険者1人あたりの年間保険料が総額30万円以下の場合、例外として全額損金算入が可能(30万円特例)
資産計上分については、保険期間の後期に按分して損金に振り替えるか、保険金・解約返戻金の受取時に差額を計上します。
積立型法人保険では得られる節税効果は「恒久的な節税」ではなく、課税の繰延(先送り)であることに注意が必要です。トータルの課税額は変わりませんが、繰り延べることで財務の改善やキャッシュフローの調整ができます。
積立型法人保険の主要タイプ一覧

積立型の法人保険には、さまざまな「タイプ」と「商品」が存在し、それぞれ特徴が異なります。
主なタイプとしては、以下の4つが挙げられます。
- 終身保険
- 保障が一生涯続くため、退職金や事業承継資金の準備に向いています。解約返戻金が高く、資産計上をしながら長期的に運用できる点がメリットです。一方、保険料は高めで、損金算入は基本的にできません。
- 定期保険(逓増定期保険なども含む)
- 一定期間の保障で、保険料の一部または全額が損金算入可能な商品が多いです。解約返戻率のピークが数年~10年程度に設定されており、計画的な資金管理に役立ちます。ただし、解約返戻率が下がるタイミングに注意が必要です。
- 養老保険
- 満期時に死亡保障と同額の解約返戻金が受け取れるタイプで、年金や退職金代わりに活用可能です。全額損金計上できる場合もありますが、税制改正以降は制限が増えています。
- ハイブリッド型
- 医療保険や三大疾病保障などを組み合わせたタイプで、保障を重視しながら積立要素も兼ね備えます。経営者・役員の健康リスクに備えつつ、福利厚生目的での導入に適しています。
企業の目的に合った保険を選ぶには、保険の分類とその特徴を明確に理解することが重要です。
企業が保険に加入する際の注意点
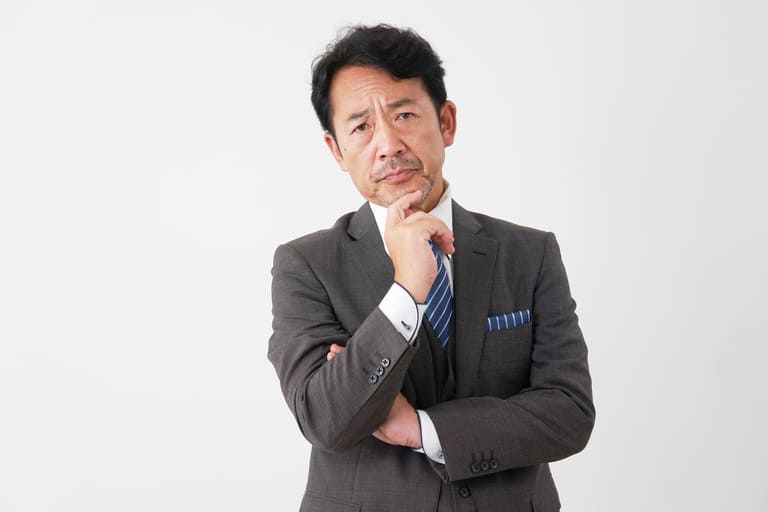
積立型の法人保険は多様な目的に活用できる一方で、誤った導入や処理を行うと、税務上のトラブルやキャッシュフロー悪化などの重大な問題を引き起こす恐れがあります。特に損金算入の扱いは、商品タイプや契約内容によって異なるため、会計処理との整合性を確保することが極めて重要です。
また、有期型の法人保険は「いつ解約するか」によっても解約返戻率が大きく変動し、結果として税負担が増加することもあります。契約期間の途中で解約を迫られた場合、損失が出る可能性があるため、中長期の資金計画と連動させた設計が必要です。
さらに、節税目的だけで加入するのではなく、退職金や事業承継、医療保障といった本来の目的に即した設計が重要です。経営者個人の保障と企業の資産形成のバランスを取りながら、税理士や保険専門家と連携し、商品選定と制度理解を深めることが失敗しない導入の鍵です。
損害保険と生命保険の違いと適用シーン
法人が加入できる保険には大きく分けて「損害保険」と「生命保険」があり、それぞれ目的と補償範囲が大きく異なります。積立型保険は通常、生命保険の一種ですが、損害保険と混同して契約・処理されることも少なくありません。
損害保険は掛け捨て型が基本で、基本的に積立効果はありません。
一方、生命保険は経営者や役員などの「人」に関するリスク(死亡・疾病・退職など)に備えるもので、積立型法人保険もここに含まれます。
企業にとって、これらの保険の使い分けは非常に重要です。万が一のリスク対策は損害保険、将来への備えや福利厚生には生命保険というように、目的ごとに適切な保険を選定することで、無駄のない制度設計が可能になります。
積立型法人保険を選ぶときに重視すべきポイント
企業が積立型法人保険を効果的に導入するためには、単に保険料や解約返戻率だけでなく、企業の目的や財務戦略に応じた多角的な視点から選定する必要があります。以下は保険選びで重視すべき6つのポイントです。
1. 契約目的の明確化
退職金準備、事業承継、福利厚生、資産形成など、保険の主目的を明確にすることで、適切な商品タイプ(定期・終身など)を選びやすくなります。
2. 損金算入の可否と税効果
税制改正にも注意し、経理処理と会計方針に沿った設計が必要です。
3. 解約返戻率のピーク時期と解約時期
解約タイミングによって手元に残る金額が大きく変わるため、自社の財務戦略と一致しているかを確認しましょう。
4. 保障内容(死亡・疾病)
経営者や役員にとって必要な保障が含まれているかをチェックします。重大疾病への備えもポイントです。
5. 保険料支払い期間と負担
短期払いと長期払いで、キャッシュフローや解約返戻率に差が出ます。企業の資金繰りに合った期間設計が必要です。
6. 税理士・FPとの連携
税務リスクを防ぐためにも、契約前に専門家の意見を取り入れることが重要です。税務や会計業務は税理士に、商品選びは法人保険に強いFP(または保険代理店)に相談しましょう。
まとめ

法人保険の積立型は、企業の「保障」「節税」「資産形成」を一体で実現できる有効な手段です。一方で、制度の複雑さ、税務処理の精度、解約タイミングの戦略性など、多くの注意点を伴います。
解約返戻率や保険料だけでなく、企業の資金計画との整合性を考慮することで、長期的に見て損のない制度運用が可能です。
将来の退職金、保障、財務安定性を見据えた戦略的な保険活用こそが、企業の成長と安定化の礎となります。税理士・FPとの連携を密にしながら、制度の仕組みを正しく理解し、自社に最適な保険プランを選定しましょう。
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス

- 法人保険を経営に活用したい
- いま加入している保険を見直したい
- 退職金制度や福利厚生を導入したい
- 事業承継や相続について考えたい
- 税金対策や財務戦略を相談したい
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて
"無料"で貴社に最適な保険プランを提案します。