企業が利益を有効に活用し、自社の成長や安定的な資金繰りを実現するためには、適切な節税対策を取る必要があります。
しかし、税制は複雑な仕組みになっているため、どのような節税対策があるか探すだけでも大変な作業です。
本記事では、法人の節税対策について基本的な考え方から、実際に活用できる22の対策方法まで、詳しく解説します。
経営者や財務担当者で、自社にぴったりな節税対策を探している方は、ぜひ参考にしてください。
- 法人税と節税の仕組み
- 法人におすすめの節税対策22選
- 節税対策① 法人保険の加入
- 節税対策② 共済の加入
- 節税対策③ 役員賞与の支給
- 節税対策④ 決算賞与の支給
- 節税対策⑤ 社宅の導入
- 節税対策⑥ 社用車の購入
- 節税対策⑦ 旅費日当の設定
- 節税対策⑧ 未払金・未払費用の計上
- 節税対策⑨ 赤字繰り越し
- 節税対策⑩ 不要在庫の処分
- 節税対策⑪ 接待交際費の経費計上
- 節税対策⑫ 福利厚生の充実(健康診断、社員旅行)
- 節税対策⑬ 30万円未満の消耗品購入
- 節税対策⑭ 貸倒引当金の計上
- 節税対策⑮ 寄付
- 節税対策⑯ 企業版ふるさと納税
- 節税対策⑰ 非営利法人の設立
- 節税対策⑱ 賃上げ促進税制の活用
- 節税対策⑲ 設備投資の優遇措置を使う
- 節税対策⑳ 短期前払費用の特例
- 節税対策㉑ 不動産投資
- 節税対策㉒ 株式投資
- まとめ
法人税と節税の仕組み

法人税とは、法人の所得に対して課される税金です。個人における所得税に当たります。
事業年度ごとに課税され、決算日翌日の2か月後までに申告・納税する必要があります。
法人の節税対策は、いかにして課税所得を減らすかが基本です。また、方法によっては税率の引き下げや、課税額からの直接控除といったやり方もあります。
法人税に関連する税金の種類
法人の所得には、法人税(法人所得税)以外にもいくつかの税金がかかります。
- 法人税(法人所得税)…法人の所得に課される税金。国税。
- 地方法人税…地方公共団体の財源不均衡を調整するために徴収する税金。国税。
- 法人住民税…行政サービスの財源として、法人に課される税金。地方税。
- 法人事業税…行政サービスの財源として、事業に課される税金。地方税。
上記4つをまとめて「法人税等」と呼ぶこともあります。
それぞれ税率や計算方法は異なりますが、課税所得が減れば課税額が減る点は同じです。そのため、節税対策も共通のものが多くあります。
税率と計算方法
以下の表は、法人税等の税率と計算方法をまとめたものです。
| 税金の種類(納付先の分類) | 計算式 | 税率等 |
|---|---|---|
| 法人税(国税) | 課税所得×税率-控除額 | 原則23.2%(ただし、中小法人(資本金が1億円以下の法人)は年800万円の所得まで15%) |
| 地方法人税(国税) | 法人税額×税率 | 10.3% |
| 法人住民税(地方税) | 法人税割(法人税額×税率)+均等割 | 自治体および業種や所得などで異なる 【東京都の例】 ・法人税割:法人税額が年1,000万円以下かつ東京都23区内に事務所がある場合 7% ・均等割:7万円~ |
| 法人事業税(地方税) | 課税所得×税率 | 自治体および業種や所得などで異なる 【東京都の例】 ・普通法人の場合3.5%~ |
※税率は2025年時点のものです。
法人税は、中小法人か否かで適用される税率が変わるため、企業によっては減資(資本金の引き下げ)を行うケースもあります。
法人住民税や法人事業税は自治体によって税率等が異なるため、地域の税事務所などで確認しましょう。
法人の節税対策の選び方
法人の節税対策は数多くあり、効果も仕組みも多種多様です。「何を基準にどうやって方法を選べばいいの?」と思う経営者の方も少なくありません。
特に重要なポイントを挙げると、以下の通りです。
- 節税タイプ
- 減額分を今後も支払う必要がない「永久型節税」か、将来に課税を先送りする「繰延型節税」か。
- キャッシュアウトの有無
- 節税対策の実行にあたって、支出(手元資金の流出)があるかどうか。資金繰りへの影響はどのくらいか。
これらを正確に見極め、自社にとって最大限効果的な対策を選ぶことが大切です。
法人におすすめの節税対策22選

ここからは、法人が実際に活用できる節税対策を22種類紹介します。
| 対策方法 | 節税タイプ | キャッシュアウト | 即効性(決算直前の対策としての有効性) | 副次効果 |
|---|---|---|---|---|
| 法人保険の加入 | 繰延型 | あり | なし | あり |
| 共済の加入 | 繰延型 | あり | あり | あり |
| 役員報酬の損金計上 | 永久型 | あり | なし | あり |
| 決算賞与の支給 | 永久型 | あり | あり | あり |
| 社宅の導入 | 永久型 | あり | なし | あり |
| 社用車の購入 | 永久型 | あり | あり | あり |
| 旅費日当の設定 | 永久型 | あり | あり | あり |
| 未払金・未払費用の計上 | 繰延型 | なし | あり | なし |
| 赤字繰り越し | 繰延型 | なし | あり | なし |
| 不要在庫の処分 | 永久型 | なし | あり | あり |
| 接待交際費の経費計上 | 永久型 | あり | あり | あり |
| 福利厚生の充実(健康診断、社員旅行) | 永久型 | あり | あり | あり |
| 30万円未満の消耗品購入 | 永久型 | あり | あり | なし |
| 貸倒引当金の計上 | 繰延型or永久型 | なし | あり | あり |
| 寄付 | 永久型 | あり | あり | あり |
| 企業版ふるさと納税 | 繰延型 | あり | あり | あり |
| 非営利法人の設立 | 永久型 | あり | なし | あり |
| 賃上げ促進税制の活用 | 永久型 | なし(賃上げ分の支出増加はあり) | なし | あり |
| 設備投資の優遇措置を使う | 永久型 | あり | あり | あり |
| 短期前払費用の特例 | 繰延型 | あり | あり | なし |
| 不動産投資 | 手法による | 手法による | 手法による | あり |
| 株式投資 | 手法による | 手法による | 手法による | あり |
節税対策① 法人保険の加入
- 節税タイプ:繰延型
- キャッシュアウト:あり
- 即効性:なし(※原則、損金計上には継続性や期間要件あり)
- 副次効果:事業保障、解約返戻金による将来の資金準備など
法人保険とは、法人が契約者となる保険全般を指します。税金対策としては、生命保険の活用が代表的です。
解約返戻金※のある保険に加入し、保険料を損金算入しつつ将来的な資金準備に備えます。もちろん、被保険者に万一があれば保険金が支払われるので、経営者や役員になにかあったときの事業保障としても有用です。
※解約返戻金…解約時に保険会社から払い戻されるお金。
ただし、近年は法改正により損金算入のルールが厳格化されているため、適切な経理処理が重要となります。法人コンサルティングに強い保険代理店など、プロフェッショナルのアドバイスを受けつつプランを組み立てましょう。
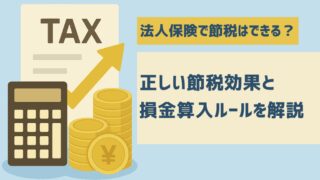
節税対策② 共済の加入
- 節税タイプ:繰延型
- キャッシュアウト:あり
- 即効性:あり(※加入月に年額払いできる場合あり)
- 副次効果:緊急時の運転資金確保、退職金準備など
共済とは、組合員の相互扶助を目的とした制度及び組織です。
共済の種類にもよりますが、以下に加入すれば掛金の全額損金算入が可能です。
| 共済名 | 概要 | 節税効果 |
|---|---|---|
| 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済) | 取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための共済制度 | ・掛金を全額損金算入可能 ・最大800万円まで積立 |
| 小規模企業共済 | 小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのために退職金を準備する共済制度 | ・掛金を全額所得控除 ・月々の掛金は最大7万円 ・共済金の受取は退職金所得扱いとなり、税負担が軽減 |
| 中小企業退職金共済(中退共) | 中小企業が自社の従業員に退職金を支払うための共済制度 | ・掛金を全額損金算入可能 ・月々の掛金は1人あたり最大3万円 ・退職金は従業員に直接支払われるため、企業の資金繰りに影響しない |
取引先の倒産に備えたり、役員や従業員の退職金準備に充てたりと、共済本来のメリットも考慮して加入しましょう。
節税対策③ 役員賞与の支給
- 節税タイプ:永久型
- キャッシュアウト:あり
- 即効性:なし(※株主総会での決定など必要)
- 副次効果:役員のモチベーション向上・社会保険料負担の最適化など
役員賞与は、以下いずれかの条件を満たせば損金として計上可能です。
- 定期同額給与(1か月以下のサイクルで定期的かつ同額が支払う)
- 事前確定届出給与(支払い額や期日を事前に税務署へ届け出る)
- 業績連動給与(有価証券報告書を提出しており、業績に応じて支給する)
株主総会での決定や税務署などの手続き、支給基準の書面化など、他にもいくつかの要件があります。
また、同業・同規模の他社と比較し、自社の収益や役員の職務内容から適切な金額を設定することが大切です。
節税対策④ 決算賞与の支給
- 節税タイプ:永久型
- キャッシュアウト:あり
- 即効性:あり(※事前確定届出と支給が要件、決算1か月前でも可能)
- 副次効果:社員のモチベーションアップ、定着率向上など
従業員への決算賞与は、以下の要件を満たすことで損金算入が可能です。
- 支給対象となる従業員全員へ、事業年度内に支給額を通知している
- 事業年度終了日の翌日から1か月以内に全額支払う
- 通知した事業年度内に損金処理を行う
支給自体は決算後でも問題ないため、直前の決算対策としても利用しやすい点が役員賞与と異なります。
節税対策⑤ 社宅の導入
- 節税タイプ:永久型
- キャッシュアウト:あり
- 即効性:なし(※契約・準備に時間がかかる)
- 副次効果:人材確保、福利厚生充実、住宅手当圧縮
社宅制度を導入すれば、法人が支払った家賃の一部を損金として計上できます。
企業が賃貸物件を借り、それを役員や従業員に対して本来の賃料より安く貸し出すことで、企業が負担した差額分を計上可能です。
ただし、役員や従業員に貸し出す際の賃料が極端に低いと、損金の計上を認められない恐れがあるので注意しましょう。国税庁が定める賃貸料相当額に対して、従業員なら50%、役員なら100%を受け取る必要があります。
節税対策⑥ 社用車の購入
- 節税タイプ:永久型
- キャッシュアウト:あり
- 即効性: あり(※購入月に減価償却費を一部計上可)
- 副次効果:業務効率化
社用車を購入すれば、減価償却費の経費計上が可能です。計上方法はどのように取得したかで変わります。
| 新車で購入 | 法定耐用年数(普通自動車なら6年、軽自動車なら4年)で減価償却 |
|---|---|
| 中古車で購入 | (法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×0.2)で減価償却※法定耐用年数を超えている場合は経過年数×0.2 |
ガソリン代や車検費用、自動車保険の経費計上も可能です。
また、社内規定を定めたうえで一定の利用料を設定すれば、プライベートでも利用することができます。
節税対策⑦ 旅費日当の設定
- 節税タイプ:永久型
- キャッシュアウト:あり
- 即効性:あり(※社内規定の作成などが決算に間に合う場合)
- 副次効果:給与課税回避、従業員の手取りUP、出張時の満足度向上
旅費日当とは、出張時にかかる費用のうち、交通費や宿泊費を除いたものです。
社内規定を作成すれば、食費や通信費などの支給を一定の範囲内で損金にできます。また、支給を受ける側の所得税も非課税です。
ただし、不自然に高額な旅費日当は認められないため、一般的な範囲で金額を設定する必要があります。
節税対策⑧ 未払金・未払費用の計上
- 節税タイプ:繰延型
- キャッシュアウト:なし
- 即効性: あり(※発生事実があれば決算直前でも計上可能)
- 副次効果:なし
未払金・未払費用とは、サービスの提供などを受けているものの、支払いや請求が来期以降になる費用です。単発の取引による費用が未払金、継続的な取引の費用が未払費用となります。
未払金・未払費用は、以下の「債務確定基準」を満たしていれば、実際に支払っていなくても当期の経費として計上できます。
- 債務が確定している(契約が成立している)
- 支払いの根拠となる事実が発生している(サービス提供やモノの引き渡しがされている)
- 支払い金額を計算できる(契約書や請求書などで金額を確定できる)
人件費や水道光熱費、固定資産税などさまざまな費用が該当します。実務上、すべてを計上するのが難しい場合は、経理作業の効率なども考えて処理しましょう。
節税対策⑨ 赤字繰り越し
- 節税タイプ:繰延型
- キャッシュアウト:なし
- 即効性:あり(※過年度赤字があれば自動で控除対象)
- 副次効果:なし
赤字の繰り越し(繰越欠損金制度)は、赤字が発生したとき、翌年以降の黒字と相殺する制度です。法人の場合、最大10年間まで繰り越せます。
適用には、青色申告承認申請書や確定申告書を期限内に提出していることが必要です。
控除額の上限は、資本金1億円以下の中小法人なら全額、資本金1億超の大企業は課税所得の50%までとなります。
節税対策⑩ 不要在庫の処分
- 節税タイプ:永久型
- キャッシュアウト:なし
- 即効性:あり(※期末までに処分すれば棚卸減で損金化)
- 副次効果:在庫管理の効率化、倉庫スペースの有効活用
売上につながる見込みがない不要在庫は、処分することで節税対策になります。
原価より安く売った場合は差額を売却損として、廃棄処分した場合は除却損として計上可能です。また、在庫処分にかかった費用も損金に算入できます。
また、不要在庫の処分は保管にかかる場所代や人件費も削減できるため、コストカットの面でもメリットがあります。
節税対策⑪ 接待交際費の経費計上
- 節税タイプ:永久型
- キャッシュアウト:あり
- 即効性: あり(※実施・計上すれば即時反映)
- 副次効果:顧客との関係構築、営業活動の活性化
接待交際費とは、法人が取引先を接待したときの費用を指します。
本来なら損金算入できませんが、租税特別措置法の特例により、以下の条件を満たす法人は経費として損金算入が可能です。
| 企業規模 | 損金算入が可能な額 |
|---|---|
| 中小企業 | 年間800万円もしくは接待飲食費のうち50% |
| 大企業(資本金100億円超の企業は除く) | 接待飲食費のうち50% |
ただし、上限額を超えると超過分の損金算入はできないため気をつけましょう。
節税対策⑫ 福利厚生の充実(健康診断、社員旅行)
- 節税タイプ:永久型
- キャッシュアウト:あり
- 即効性:あり(※即時実行・計上が可能な内容に限る)
- 副次効果:社員の満足度向上、健康維持、離職防止
福利厚生費は、従業員の満足度を向上させるだけでなく、法人の節税対策としても効果があります。
代表的な方法としては、健康診断と社員旅行が挙げられます。ただし、損金として計上するためには細かい条件があるので注意しましょう。
- 健康診断:従業員全員を対象とし、企業から医療機関へ直接支払いをすること。
- 社員旅行:4泊5日以内で、全従業員の50%以上が参加すること。
節税対策⑬ 30万円未満の消耗品購入
- 節税タイプ:永久型
- キャッシュアウト:あり
- 即効性: あり(※即時償却可、決算前でも対応可能)
- 副次効果:なし
30万円未満の消耗品購入は、少額減価償却資産の特例により当年の全額損金算入が可能です。
通常、10万円以上の固定資産は、資産の種類ごとに定められた年数(法定耐用年数)で分割償却する必要があります。
例:100万円で買った資産の法定耐用年数が5年の場合、5年間で毎年20万円ずつ償却(損金参入)する。
上記に対し、少額減価償却資産の特例では30万円未満の資産を一括償却できます。また、事業年度につき累計300万円まで適用可能です。
利用できるのは中小企業のみですが、手軽に実行できる節税対策として魅力的です。
節税対策⑭ 貸倒引当金の計上
- 節税タイプ:繰延型or永久型
- キャッシュアウト:なし
- 即効性:あり(※要件を満たせば期末に計上可能)
- 副次効果:リスクヘッジ、財務健全性の確保
貸倒引当金とは、将来的に未回収となりそうな取引先債権を、あらかじめ損金として計上する制度です。
貸倒引当金として認められるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 将来発生する費用または損失であること
- 発生の原因が当期以前の事象にあること
- 貸倒発生の可能性が高いこと
- 金額の合理的な見積もりができること
貸倒発生の可能性については、過去の統計や取引先の状況(未払いの繰り返しなど)から判断します。
実際に取引先が倒産した場合は永久型、倒産しなかった場合は繰延型の節税対策として利用できます。
節税対策⑮ 寄付
- 節税タイプ:永久型
- キャッシュアウト:あり
- 即効性:あり(※決算前に支出すればOK)
- 副次効果:社会貢献、企業ブランディング、地域との関係構築
法人として寄付することで、その全額もしくは一部を損金として計上できます。
寄付先と節税効果は以下の通りです。
| 寄付先 | 損金算入の限度額 |
|---|---|
| 国や地方公共団体、指定寄付金(財務大臣指定の寄付事業) | 全額損金算入 |
| 特定公益増進法人など | 【普通法人などが寄付する場合】 (資本金などの額×事業年度の月数/12×3.75/1,000+所得額×6.25/100)×1/2 |
| 【一般社団法人などが寄付する場合】 所得額×100分の6.25 |
|
| 一般の寄付金 | (資本金などの額×事業年度の月数/12×2.5/1,000+所得額×2.5/100)×1/4 |
なお、損金として計上できるのは「寄付金の支払い後」なので、当期中に支払う必要がある点に注意しましょう。
節税対策⑯ 企業版ふるさと納税
- 節税タイプ:永久型
- キャッシュアウト:あり
- 即効性: あり(※決算前に支出すればOK)
- 副次効果:地域活性化支援、企業PR、CSR強化
企業版ふるさと納税は、地方公共団体の地方再生事業に寄付することで、税額控除を受けられる制度です。
| 法人住民税 | 寄付金額の40%を税額控除(上限:法人住民税法人税割額の20%) |
|---|---|
| 法人税 | 法人住民税で40%に達しない場合、残額を税額控除(上限:寄付額の10%かつ法人税額の5%) |
| 法人事業税 | 金額の20%を税額控除(上限:法人事業税額の20%) |
先述した「地方公共団体への寄付」による損金算入も適用可能で、合計すると寄付金額の約90%まで税負担を軽減できます。
節税対策⑰ 非営利法人の設立
- 節税タイプ:永久型
- キャッシュアウト:あり
- 即効性:なし(※設立・体制構築に時間がかかる)
- 副次効果:事業分離による資産保全と税制優遇、法人の多層化
非営利法人とは、利益の分配を目的としない法人のことです。NPO法人や公益法人などが挙げられます。
一定の事業以外で法人税が非課税になったり、資産移転で相続税の課税対象から除外できたりといったメリットがあります。
ただし、非営利法人としての活動実態がないなど、不適切な運用を税務署に指摘されると節税効果を受けられないため注意が必要です。
節税対策⑱ 賃上げ促進税制の活用
- 節税タイプ:永久型
- キャッシュアウト:なし(賃上げ分の支出増加はあり)
- 即効性:なし(※年度通しての賃上げが必要、短期では不可)
- 副次効果:採用力の向上、従業員満足度や定着率UP
賃上げ促進税制とは、法人が従業員の給与等を増やした場合、増加分の一部を法人税額から控除する制度です。
前年度と比べて1.5%以上増加していれば増加分の15%を、2.5%以上増加していれば30%を控除します。
また、教育費訓練費の増加など追加条件を満たせば、さらに最大15%まで控除額を上乗せできます。
【例:前年の給与支給額が5,000万円の場合】
- 1.5%増で5,075万円を支給した場合→75万円×15%=11万2,500円を控除
- 2.5%増で5,125万円を支給した場合→125万円×30%=37万5,00円を控除
節税対策⑲ 設備投資の優遇措置を使う
- 節税タイプ:永久型
- キャッシュアウト:あり
- 即効性: あり(※即時償却など活用可能、期限内なら効果あり)
- 副次効果:生産性向上、業務効率化、競争力強化
設備投資はそのままでも減価償却が可能ですが、「中小企業投資促進税制」や「中小企業経営強化税制」という優遇措置を使うことで、より法人税を減らせる可能性があります。
「中小法人に限る」「適用期限がある」などの制限はありますが、要件を満たせば設備投資と節税対策を同時に行えます。
節税対策⑳ 短期前払費用の特例
- 節税タイプ:繰延型
- キャッシュアウト:あり
- 即効性:あり
- 副次効果:なし
短期前払費用の特例とは、前払費用※のうち1年以内に役務(サービスや労働など)を受ける部分について、全額損金算入ができる制度です。
※前払費用…継続的に役務の提供を受けるとき、当期の決算までに提供されていない役務に対して支払った対価のこと。
以下は、短期前払費用の具体例です。
- 保険料
- 家賃
- システム利用料
- 機材のリース料
たとえば、決算前に保険料や家賃を年払いで支払えば、当期分の課税所得を大幅に減らせます。
節税対策㉑ 不動産投資
- 節税タイプ:手法による
- キャッシュアウト:手法による
- 即効性:手法による
- 副次効果:資産の形成や保全など
不動産投資は、法人の中長期的な資産形成と同時に、節税対策としても活用される方法です。特に中小企業では、「減価償却」や「赤字の損益通算」「資産の含み損処理」などを活かし、課税所得の圧縮に役立てられます。
- 減価償却費で利益を圧縮
- 修繕費や管理費を損金計上
- 借入金の利息部分を損金計上
- 含み損や売却損を損金として計上
賃貸物件として貸し出せば賃料収入が確保できますし、社宅として活用すればより効率的な節税対策として活用できます。
節税対策㉒ 株式投資
- 節税タイプ:手法による
- キャッシュアウト:手法による
- 即効性:手法による
- 副次効果:手法による
法人の株式投資は、有価証券(上場株・非上場株)の保有・売買や配当の取得によって、法人税負担を軽減できる場合があります。
- 配当金の益金不算入(一定の要件あり)
- 売却損・評価損による節税
ただし、法人の場合は株式投資の損金・益金計上ルールが明確に定められているため、適切な管理と目的設定が重要です。
まとめ

法人の節税対策は、事業内容や企業規模などによって最適な方法が異なります。
誤った節税対策を実施すると、思ったより効果がなかったり、税務調査で指摘を受けたりする恐れがあります。そのため、節税対策の検討と実施には「法人コンサルティングに特化した専門家」の存在が重要です。
具体的な節税対策については税理士、財務戦略に関する幅広いアドバイスが欲しいならファイナンシャルプランナーと、ニーズにあった専門家に相談することがおすすめです。
適切な節税対策を検討・実行し、自社の成長と安定経営につなげましょう。
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス

- 法人保険を経営に活用したい
- いま加入している保険を見直したい
- 退職金制度や福利厚生を導入したい
- 事業承継や相続について考えたい
- 税金対策や財務戦略を相談したい
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて
"無料"で貴社に最適な保険プランを提案します。




















