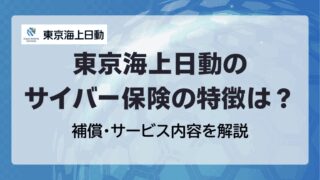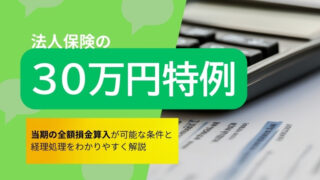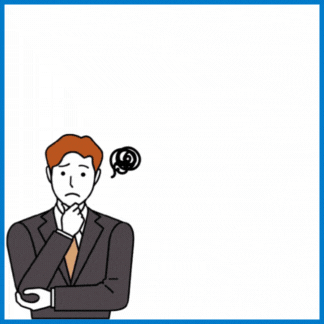法人経営において、税負担を適切にコントロールすることは、手元資金や純利益を確保するうえで重要です。なかでも、役員に対する退職金の取扱いは、金額や決定手続によって税務上の評価が変わるため注意が必要です。
役員退職金(役員退職給与)は、法人税計算上、原則として損金算入が認められます。
ただし、役員給与の一種として扱われ、退職給与として相当と認められる金額を超える部分(不相当に高額な部分)は損金算入できません。取扱いを誤ると損金として認められず、税負担が増える可能性もあります。
効率よく税務対応を進めるためには、損金算入のポイントと注意点を押さえておくことが大切です。
今回は、法人税法上の役員退職金の取扱いについて解説します。
過大にならないように!役員退職金と税金の関係
役員退職金は、取締役や執行役員などが退職したときに支払われるものです。
一般の従業員が退職した場合に支払われる退職金と同様に、原則として法人税法上の損金として認められ、課税所得を圧縮する効果が生じる場合があります。
ただし、役員に関しては、従業員を雇用し経営に責任を持つ立場にあるため、一般の従業員とは違った取扱い規定がありますので注意が必要です。
法人税では、役員退職金を無制限に損金算入することを認めていません。その理由は主に3つあります。
理由① 役員退職金は社内で決めやすい
1つ目は、退職金を役員自身が決定することになるため、過大になる可能性があることです。
役員退職金は株主総会での承認が必要ですが、金額については、会社経営を任されている役員が議案として提案することになります。結果として、役員自身が関与して決める構造になりやすく、過大な退職金が提示される可能性を排除できません。
そのため、法人税法上は、退職金のうち過大な分については損金算入が制限されています。
理由② 株主に帰属すべき利益の流出防止
2つ目は、株主に対して配当金として支払われるべき利益まで役員退職金として流出してしまうことを防ぐためです。
会社が生み出した利益は、配当金か清算金として株主に返還されるべきものです。しかし、過大な役員退職金が通ってしまうと、本来、株主に支払われるべき利益が役員退職金の名目で減少してしまうことになります。
株主へ支払われる配当金は、税金支払い後の利益などを原資として支払われます。役員が会社を私物化して自らの退職金を過大に受け取ることを防ぐ必要があるため、法人税法では過大な役員退職金の損金算入を認めていません。
理由③ 課税の公平性の観点
3つ目は、過大な役員退職金は、法人課税と個人課税の両方を回避することにつながり得るためです。
会社が支払った配当金は、一定の場合を除いて損金算入ができません。一方、個人が配当金を受け取った場合は、原則として所得税や住民税などが課税されます。
配当金として支払われるべきものが役員退職金として支払われると、過大に支払われた分については法人税だけでなく配当金に対する個人課税の観点でも問題となり得ます。
特に、役員が会社株式の大部分を所有しているオーナー社長などの場合、過大な退職金を損金計上して法人所得を減少させ、配当金に対する課税を回避する形になり得るため、過大部分の損金算入が制限されています。
一般の従業員の退職金との違い
一般の従業員の退職金は、社内規程や運用に基づいて支給されるのが通常です。ただし、支給根拠が不明確な場合や、特定の個人に著しく偏った支給となる場合などは、説明が必要になることがあります。
また、従業員であっても、役員の親族など役員と特別な関係があったり、大株主であったりして実態として経営に影響を与えている場合は、法人税法上「みなし役員」として役員同等の取扱いを受けることがあります。結果として、過大な退職金の損金算入が認められない可能性があります。
適正な役員退職金の基準とは
役員退職金の支給金額を決める場合は、税務上、過大な金額だと認定されないようにすることが大切です。
仮に、過大な金額だと税務署から認定されてしまうと、相当額を超える部分は損金算入が認められず、会社資金の流出があったにもかかわらず、その分についても法人税が課税されることになり得ます。
そのため、退職金が適正な金額であることを説明できるように、役員退職金の算定根拠を明確にしておくことが重要です。
算定方法① 功績倍率法
役員退職金の算定方法として採用されることが多い方法が、「功績倍率法」です。
功績倍率法では、役員退職金の適正額を「最終月額報酬×勤続年数×同業類似法人の功績倍率」で算出します。
功績倍率法は、一般に次の式で検討します。
※同業類似法人の水準等を参考
最終月額報酬とは、役員が退職する直前の月当たり役員報酬額のことです。
そのため、退職直前の役員報酬がゼロであれば、算定上は退職金がゼロとなるケースもあり得ます。
ただし、退職直前の報酬が「特殊事情による一時的な変動(例:職務内容の変更、病気療養、役員構成の変更など)」である場合に、最終月額報酬だけを機械的に用いると、金額の妥当性が認められない可能性があります。状況によっては、他の算定方法も含めて合理的な根拠を用意しておくことが大切です。
また、毎月支払っている報酬よりも多い金額を退職直前に支払って退職金を増額した場合は、たとえ功績倍率法の計算式に従って計算していたとしても、増額によって増えた部分について損金算入が認められない可能性があります。
勤続年数の考え方と端数処理
功績倍率法で使用する勤続年数は、役員として登記されていた期間のことです。一般の従業員から役員に昇格した場合、従業員としては退職して役員に就任することになります。
そのため、役員になってから退職するまでの期間が対象です。勤続年数は年単位でぴったりにならないこともあるでしょう。
勤続年数の端数処理は、切り上げ・切り捨て・四捨五入など、会社の考え方や実態に応じて取り扱われることがあります。
ただし、端数の扱いによって支給額が変わるため、社内規程であらかじめ方法を定め、継続して運用することが重要です。都度の恣意的な変更は避け、合理的な根拠を説明できる形にしておきましょう。
功績倍率は「同業類似法人の水準から乖離しない」ことが重要
功績倍率は、地域や業種、退職時期、売上規模、退職事由、所得金額、在籍期間などを考慮して同業類似法人を抽出し、その水準を参考にします(複数社を抽出する場合は平均を用いるケースもあります)。
税務署も同様の観点で過大かどうかを判断するため、同業類似法人の支給状況から著しく乖離しない範囲で、算定根拠を説明できるようにしておくことが重要です。
ただし、同業類似法人のデータを収集することは容易ではありません。民間の調査会社などから入手する方法もありますが、税務署が参照するデータベースと同一とは限らないため、比較対象の選定根拠や算定過程を整理しておきましょう。
算定方法② 1年当たり平均額法
役員退職金を算定する方法としては、功績倍率法以外に1年当たり平均額法が挙げられます。
1年当たり平均額法は、同業類似法人の役員退職金の支給実態を参考に「1年当たりの退職金水準」を置き、そこから自社の勤続年数等に当てはめて検討する考え方です。
この方法では、個々の役員報酬の違いによる影響を受けにくい一方で、会社規模等の差を反映しにくいことや、同業類似法人データの収集が難しいことなどがデメリットになります。
まずは、功績倍率法を中心に、算定根拠(比較対象・計算過程)を説明できる状態にしておくことが重要です。
損金不算入にならないための注意事項
役員退職金が損金不算入にならないようにするためには、主に4つの点に注意する必要があります。
4つの注意点
- 同業他社と比較して突出して高い金額を支給しないこと
- 役員退職金の決定に関する株主決議に関する議事録をしっかり残しておくこと
- 退職慰労金規定を整備すること
- みなし役員について
注意点① 同業他社と比較して突出させない
1つ目は、同業他社と比較して突出して高い金額を支給しないことです。税法上、いくら以上は過大な退職金であるという明確な規定は存在しません。
そのため、会社として過大な支給額ではないと判断しても、税務署から過大だと認識されるリスクは残ります。
税務署は、提出された法人税申告書等から抽出した同業他社データなどを基に判断します。平均値からかけ離れた退職金を支給した場合は、税務署としても慎重に調査する可能性があります。
特に、功績倍率は独り歩きしやすいポイントです。同業類似法人の水準から著しく乖離している場合は、乖離部分が「不相当に高額」と判断されるリスクがあります。比較対象の選定根拠と算定過程を説明できるようにしておきましょう。
注意点② 決定手続(株主総会・議事録)を残す
注意点の2つ目は、役員退職金の決定に関する株主総会決議と、その議事録をしっかり残しておくことです。
役員退職金の決定は、株主総会の決定事項です。オーナー社長がほとんどの株式を所有している場合は、株主総会が形骸化している可能性があると見られ、正式な手続きを踏まずに支給しているのではないかと疑われることがあります。
正当な手続きを踏んで決定された役員退職金であることを説明するためにも、株主総会を開催して議決したことを議事録として残しておくことが重要です。
注意点③ 退職慰労金規程の整備と運用
3つ目は、退職慰労金規程を整備することです。
役員退職金の算定方法などを規程として残しておくことによって、恣意的に高い退職金を支給しているわけではないことを説明しやすくなります。
ポイントは、退職金の支給直前に規程を作ったり変更したりしないことです。直前の作成や変更は、退職金を不当に高くする目的で行われたとみなされる可能性があります。
「必要になったときに作成すればよい」という考え方は避け、早めに整備しておくことが大切です。
注意点④ みなし役員に注意
4つ目の注意点は、みなし役員についてです。役員退職金は、実際に役員を退任した場合に支給するのが一般的です。
ただし、例外として役員にとどまったままでも退職金として取り扱える場合があります。法人税法では一定の要件を満たすと、みなし役員退職給与として損金算入できる場合があります。
代表例は次のとおりです。
- 常勤役員が非常勤役員になった
- 取締役が監査役になった
- 職務分掌変更後の給与が概ね50%以上減少した
ただし、代表権を有する場合や、分掌変更後も経営上主要な地位にあると認められる場合などは、退職金として扱えないことがあります。実態が伴うかどうかを含めて検討しましょう。
また、会社法上の役員でなくても、実質的に経営に影響を与えている役員の親族や大株主の従業員については、みなし役員として役員同等の取扱いとなる場合があります。
正しい知識で活用すれば税務上のメリットにつながる
役員退職金は、原則として損金算入が認められる一方、不相当に高額な部分は損金算入できません。
そのため、支給にあたっては、金額の妥当性(同業類似法人との比較等)と決定手続(株主総会決議・議事録)、規程と運用の整合性を押さえて準備することが大切です。
税務署は、同業類似法人の支給状況等も参考にしながら過大かどうかを判断します。功績倍率を含め、比較水準からの乖離が大きくならないよう注意しましょう。
役員退職金規程の整備や株主総会議事録の保存など、支給前に根拠資料をそろえ、必要に応じて税理士等にも確認したうえで進めることで、追徴課税などの想定外の税負担増加を防ぎやすくなります。
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス

- 法人保険を経営に活用したい
- いま加入している保険を見直したい
- 退職金制度や福利厚生を導入したい
- 事業承継や相続について考えたい
- 税金対策や財務戦略を相談したい
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて
"無料"で貴社に最適な保険プランを提案します。