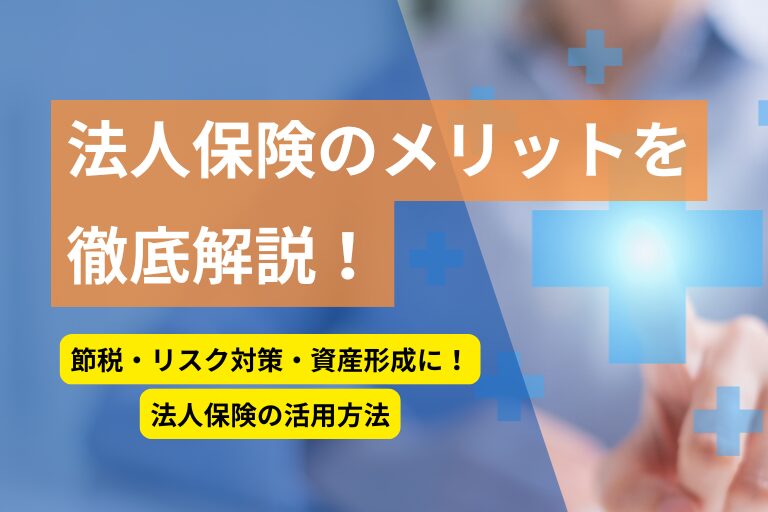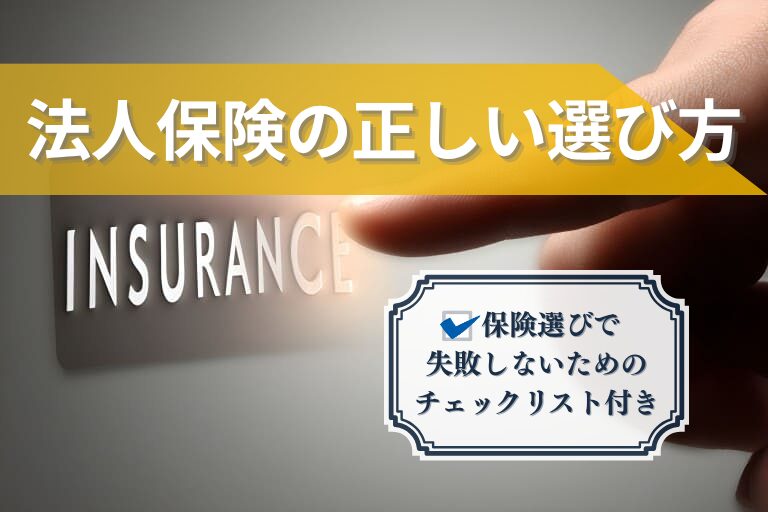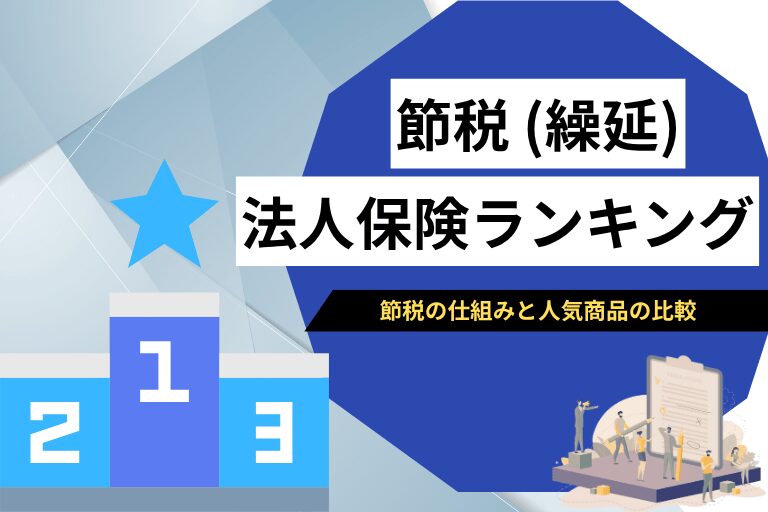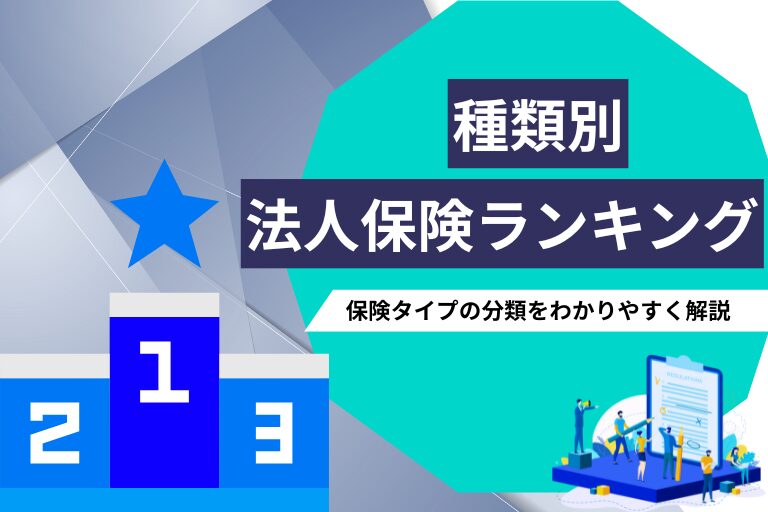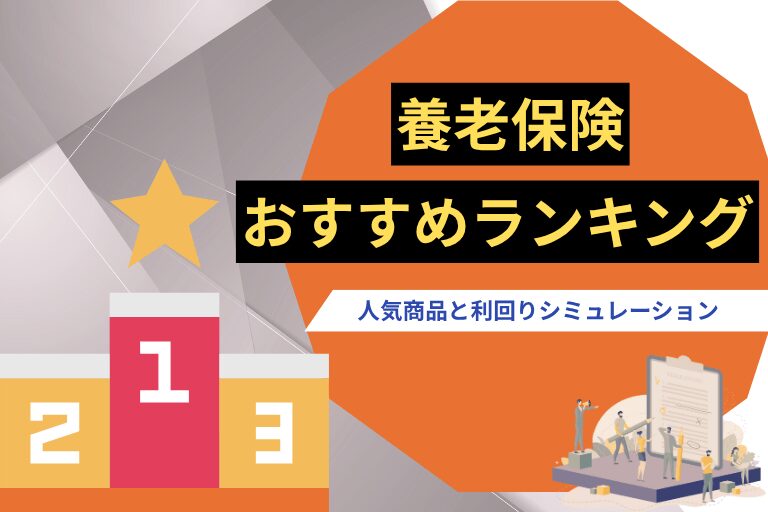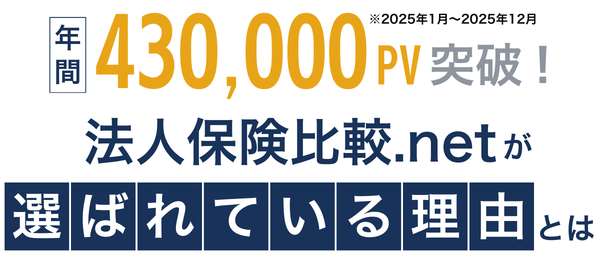
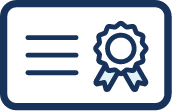
FP監修!法人保険専門コンテンツで最新の情報がわかる
FPの資格を持った専門家の監修のもと、100を超えるコンテンツを公開しています。

法人保険を取り扱う保険代理店と提携!
法人保険のプロが、経営者の皆様に最適な生命保険・損害保険を無料でご提案いたします。

法人保険による決算対策・税務処理などのご相談にも対応
法人保険で決算対策・法人税対策をしたいという経営者の方はぜひお問い合わせください。
様々な目的に応じた
法人保険を徹底解説!
自社に最適な法人保険選びに、ぜひお役立てください
法人保険は、加入する目的によって最適なものを選ばなければ意味がありません。
法人税対策、事業保障、福利厚生、退職金の貯蓄…目的は様々ありますが、自分自身で最適な保険商品を選ぶのは大変です。
それもそのはず、法人保険の商品は数百種類以上あり、仕組みも複雑。知識がなければ、どんな観点で保険商品を比較すればいいのかよくわからないのです。
そこで当サイトでは、ファイナンシャルプランナーが執筆・監修した記事を中心に、法人保険選びに必要不可欠な専門情報をご紹介しています。おすすめの保険商品ランキングや、法人保険の基礎知識、目的に応じた法人保険の選び方・活用方法など、経営者の方に役立つ法人保険の知識をお届けします。
当記事の内容は、2019年の法人保険に関する税制改正後の基準に従います。
税制改正の流れについては、当サイト「【節税保険が販売停止】国税庁の新ルールを解説」で詳しく解説していますので、こちらもぜひご覧ください。
税制は今後も改正される可能性があります。最新の情報は、国税庁・金融庁・各保険会社が公表する内容もご確認ください。
企業のタイプに合った法人保険の活用方法
オーナー企業では、経営者に万が一のことがあった際に、経営が立ち行かなくなる可能性も。早めの事業保障の備えが重要です。
ニ代目に引き継ぐ際には、相続税など様々な税金が発生するため、事前の対策が必要です。 計画的に事業承継の準備をしましょう。
中小企業は、事業継続の資金作りや社内制度の整備などが課題になります。法人保険だけでなく「共済」という選択肢もあるため、会社の規模に合った備えをしましょう。
創業期だからこそ、リスクヘッジが重要。事業の立ち上げに集中するだけでなく、先を見通して事業保障の備えをしておくことが必要です。
Ranking─保険商品の比較と紹介─
法人保険は国内だけでも100種類以上。それぞれ特徴が異なるこそ、1つずつ比較することが重要です。
様々な観点からおすすめ保険商品を厳選し、ランキング形式で紹介。各商品のメリットを比較しているので、ぜひ「自社に最適な保険商品」を選ぶための参考にしてください。
法人保険の基礎知識とおすすめランキング【2025年】
ここからは、「まずは法人保険の基本的な情報や仕組みを知りたい」という方に向け、法人保険のメリットや比較するときのポイントなどを順に説明していきます。
また、当サイト厳選のおすすめ法人保険も紹介するので、ぜひ保険選びの参考にしてください。

当記事の監修者:金子 賢司
- CFP
- 住宅ローンアドバイザー
- 生命保険協会認定FP(TLC)
- 損保プランナー
東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。
以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。
趣味はジャザサイズ。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・情報発信しています。
法人保険とは?
法人保険とは、契約者を法人、被保険者を役員や従業員にして契約する保険を指します。
被保険者の死亡時に保険金を受け取れる手厚い保障が備わっているものや、貯蓄性の高いものなど、種類はさまざまです。
法人保険に加入する目的として挙げられる内容は、主に以下のようなものがあります。
- 1. 事業継続・リスク管理
- 経営者や役員の死亡・病気に備える(死亡保険金で事業を維持)、賠償リスク・災害・自己への備え
- 2. 退職金・弔慰金の準備
- 役員・従業員の退職金準備、弔慰金の支払い
- 3. 節税・財務対策
- 保険料の経費計上による税金対策
- 4. 事業承継対策
- 事業承継時の資金確保(相続税や贈与税対策)
- 5. 従業員の福利厚生
- 団体保険の提供(医療保険や死亡保険)、従業員の健康増進(医療・がん保険の加入)
企業によって加入目的はさまざまですが、共通しているのは「お金のリスクに備える」ということ。
経営者が病気になってしまった時、取引先が倒産してしまった時、事業で賠償責任を負わなければならなくなった時…会社になにかが起こったときには、必ず大きなお金が必要になります。
常日頃からきちんと資金を運用することは、企業の成長や安定には不可欠です。お金のリスクに備えられる法人保険は、経営の舵取りを支える重要なファクターと言えます。
法人保険のメリット4つ
法人保険に加入するメリットは、大きく分けて4つあります。
- 非常事態の予備資金を貯蓄できる
- 保険料を損金算入できる
- 社長・役員に対する保障を得られる
- 従業員の福利厚生として利用できる
自社の状況やニーズに合っているか確認してみましょう。
① 非常事態の予備資金を貯蓄できる
法人向けの生命保険では、解約したときに「解約返戻金」という名目で資金が手元に戻ってくる場合があります。自分が支払った保険料を積み立てておくイメージで、会社の帳簿外に返戻金という形で資産を作れるのです。
「取引先が倒産して利益の見込みが立たない」「事業のトラブルで賠償金を支払う必要がある」など、突発的な資金需要への備えとして活用できます。
② 保険料を損金として計上できる
法人保険の保険料は損金として計上できるため、企業の課税所得を減らし、法人税を減らす効果があります。年払いで契約すれば、決算直前の税金対策としても有効です。
ただし、生命保険や医療保険は損金の計上方法にルールがあるため、注意が必要です。また、損金の計上で減少した税金は、解約返戻金や保険金を受け取ったときに同等の金額が課されるため、あくまで課税の繰延であることに留意しましょう。
③ 社長・役員に対する保障を得られる
法人向けの生命保険の場合、資金の積立てを行いつつ不足の事態に備えた死亡保障を得られます。
中小企業や家族経営の企業などは、経営における社長や役員の影響が大きく、個人に不測の事態があっただけで事業継続が難しくなる場合があります。そんな時に、法人保険の死亡保険金を事業の存続資金に利用すれば、スムーズな安定化が可能です。
また、医療保険ならケガや病気の保障を受けられるので、働けないときの収入確保や事業の運転資金として活用できます。
④ 従業員の福利厚生として利用できる
法人保険の中には、従業員を対象として加入する保険もあります。
養老保険や医療保険、がん保険などを法人契約すれば、従業員の死亡・病気のリスクに備えられます。これらの保障を会社で用意すれば、従業員のモチベーション向上につながり、人材の採用や定着に役立つでしょう。
法人保険は節税になる?損金算入ルールについて
先にも少し触れましたが、法人保険に加入し保険料を損金に計上することで法人税の節税につながるケースがあります。
以前は法人保険の保険料の全額や1/2を損金として計上でき、大きな節税効果を期待できました。そのため、「法人保険といえば節税」という考えも主流だった時代があります。
しかし、2019年に国税庁によって法人保険に関する税制改正が行われ、保険料の損金計上に関するルールが変わりました。損金として計上できる保険料の割合は限定的となり、以前よりも節税効果が小さくなってしまったのが現状です。
このような背景があるため、現在は法人保険の税制上のメリットをあくまで副次的なものとして捉える流れになっています。
とは言うものの、法人保険の保険料をまったく損金に計上できなくなってしまったわけではありません。ルールに則って、一定の割合を損金にすることが可能です。
法人保険が節税になる仕組み
法人保険が節税になる仕組みは、保険料の損金算入により課税所得を減らすことにあります。
ご存知かと思いますが、法人税は1年間の益金から損金を差し引いた課税所得に対して課されます。計算式は以下の通りです。
・益金:利益や雑収入など。保険の解約返戻金も益金として扱われる。
・損金:会社にかかる経費。法人保険の保険料も損金にできる。
・税率:法人税の税率は原則23.2%。ただし、資本金1億円以下の中小法人は課税所得800万円の部分まで15%。
・控除額:源泉徴収された所得税額など。
これらの計算式を見れば、保険料を損金にすることで課税所得を減らし、ひいては法人税額も減らせるとわかります。これが法人保険による節税の仕組みです。
ただし、保険金や解約返戻金を受け取ったときは、これらを益金として計上する必要があります。つまり、保険料の損金算入で減らした税額は将来的に支払うことになるため、トータルの負担は変わりません。
このように、法人保険の節税はあくまで課税の繰延(繰延型の節税)であり、法人税額を恒久的に減らす効果はないことに注意が必要です。
2019年の税制改正での変更ポイント
法人保険による節税が課税の繰延であることは今も昔も変わりませんが、かつては保険料の半額や全額を損金算入できたため、繰延の効果も大きなものでした。
しかし、2019年の税制改正では損金算入の割合が変更され、最高解約返戻率が高い保険ほど損金算入できる割合が少なくなりました。
改正後の損金算入ルールは以下のとおりです。損金算入できない部分は資産計上する必要があるため、課税所得の軽減幅は小さくなります。
| 最高解約 返戻率 |
資産計上期間 | 資産計上額 | 取り崩し期間※1 |
|---|---|---|---|
| 50%以下 | 全額損金算入 | ||
| 50%超~ 70%以下※2 |
保険期間の当初40%の期間 | 支払保険料×40% (支払保険料×60%は損金計上) |
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上 |
| 70%超~ 85%以下 |
保険期間の当初40%の期間 | 支払保険料×60% (支払保険料×40%は損金計上) |
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上 |
| 85%超 |
①保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間等の終了日まで ②1の期間経過後において、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで |
保険期間開始日から10年経過日までは、保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上 11年目以降は、支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上 |
解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し |
| 最高解約返戻率:50%以下 | |
|---|---|
| 全額損金計上 | |
| 最高解約返戻率:50%超~70%以下※2 | |
| 資産計上期間 | 保険期間の当初40%の期間 |
| 資産計上額 | 支払保険料×40% (支払保険料×60%は損金計上) |
| 取り崩し期間※1 | 保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上 |
| 最高解約返戻率:70%超~85%以下 | |
| 資産計上期間 | 保険期間の当初40%の期間 |
| 資産計上額 | 支払保険料×60% (支払保険料×40%は損金計上) |
| 取り崩し期間 | 保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上 |
| 最高解約返戻率:85%超 | |
| 資産計上期間 |
①保険期間の開始日から最高解約返戻率となる期間等の終了日まで ②1の期間経過後において、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで |
| 資産計上額 |
保険期間開始日から10年経過日までは、 11年目以降は、 |
| 取り崩し期間 | 解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し |
※年間保険料が1人当たり30万円以下の保険など、一部の条件を満たした場合に全額損金算入ができる場合もあります。
たとえば、解約返戻率が85%を超える定期生命保険は、当初10年間は支払保険料×ピーク返戻率×0.9という大部分を資産に計上。これでは、契約初期に損金として計上できる割合は15%~25%ほどになってしまいます。
このように解約返戻金が高い=貯蓄性の高い法人保険ほど、契約してから一定の期間の間は損金として計上できる割合を少なくしているのが、新ルールのポイントです。
法人保険の主な活用方法
法人保険による節税(課税の繰延)は限定的になりましたが、そもそも保険本来の目的はリスクに対する保障です。加えて、法人保険の場合は解約返戻金による貯蓄効果や、福利厚生といったメリットもあります。
法人保険の主な活用方法をまとめると、以下のとおりです。
- 退職金準備
- 事業保障(万が一に備えた資金準備)
- 事業承継(相続税対策など)
- 福利厚生(従業員の保障など)
上記のような活用方法も合わせてメリットを検討しましょう。
経営者の生命保険は法人契約と個人契約どちらがお得?
「自分や家族のために生命保険に加入しようと思っているけど、法人契約と個人契約どちらが良いかわからない」と考える経営者の方もいるでしょう。
経営者が生命保険に加入する場合、法人契約と個人契約のどちらが適しているかは、目的や税務上のメリット・デメリットを考慮する必要があります。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 法人契約 | 保険料の損金算入ができない 保険料の支払いが個人負担 | 契約変更が困難 解約返戻金の受取時に法人税がかかる 税務処理が複雑 |
| 個人契約 | 自由に受取人を設定できる 家族の相続対策になる 事業に関係なく個人の資産形成として活用できる、解約時の課税処理がシンプル | 事業保障や事業承継に役立てられる 保険料の損金産算入ができる 財務戦略の一環として利用できる |
法人の税金対策や財務戦略なら法人契約、家族への資産継承や自由な資産運用なら個人契約と、使い分けると良いでしょう。また、療法を上手に組み立てて、法人と個人の両方でメリットを最大化することも可能です。
主な法人保険の種類
ここからは、法人保険の中でも代表的な種類をいくつか紹介します。
それぞれの特徴を把握し、保険選びに役立てましょう。
逓増定期保険
逓増定期保険(ていぞうていきほけん)は、一定期間の死亡保障を提供する定期保険の一種です。契約後、段階的に保険金額が増加(逓増)していく特徴があり、一般的には最大5倍まで上がります。
解約返戻率のピークが契約後5~10年と早いため、短期間の保障や資金準備をしたい場合に向いています。
| 主な補償内容 | 死亡、高度障害 |
|---|---|
| 保険料 | 一定 |
| 保険期間 | 10年~30年程度もしくは満90歳程度まで |
| 保険金 | 最大5億円程度 |
| 解約返戻金 | あり |
| 満期返戻金 | なし |
| おすすめの活用方法 | 退職金準備、事業保障、事業承継 |
長期平準定期保険
長期平準定期保険は、100歳近くまでの長期間にわたり死亡保障を提供する法人保険です。解約返戻率が高めで、85%~95%ほどのものもあります。
解約返戻金のピークが20~30年程度と遅めな代わりに、高いまま維持している期間も長く、長期的な保障や資金準備に向いている保険です。
| 主な補償内容 | 死亡、高度障害 |
|---|---|
| 保険料 | 一定 |
| 保険期間 | 満100歳前後 |
| 保険金 | 最大1億円程度 |
| 解約返戻金 | あり |
| 満期返戻金 | なし |
| おすすめの活用方法 | 退職金準備、事業保障、事業承継 |
養老保険
養老保険とは、一定期間の死亡保障と、満期を迎えた際に受け取れる満期保険金を兼ね備えた保険です。満期まで生存すれば、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができます。
貯蓄性が高いため、退職金準備や福利厚生制度に適しています。また、一定条件(従業員の全員加入など)を満たせば、保険料の全額もしくは半額を損金として算入可能です。
- 保険期間が5年以上であること
- 契約者が法人であること
- 被保険者が役員または従業員であること
- 保険金受取人が法人であること
- 解約返戻金のある定期付き養老保険でないこと
- 税務上の取り扱いを示す通達に準拠していること
| 主な補償内容 | 死亡、高度障害 |
|---|---|
| 保険料 | 一定 |
| 保険期間 | 10年~30年程度もしくは満90歳程度まで |
| 保険金 | 数千万円程度 |
| 解約返戻金 | あり |
| 満期返戻金 | あり |
| おすすめの活用方法 | 事業承継、福利厚生 |
医療保険
医療保険は、病気やケガで入院・手術をした際に給付金を受け取れる保険です。特約の付加により入院の一時金、特定疾病の一時金、先進医療なども保障できます。
法人で医療保険に加入すると、役員や従業員の健康リスクに備えたり、見舞金や経営資金に充てたりといった活用方法があります。
| 主な補償内容 | ケガや病気 |
|---|---|
| 保険料 | 一定 |
| 保険期間 | 一生涯 |
| 保険金 | 治療給付金20万円、入院給付金1万円/1日など |
| 解約返戻金 | なし |
| 満期返戻金 | なし |
| おすすめの活用方法 | 事業保障、福利厚生 |
がん保険
がん保険は、がんと診断された際に、一時金や入院給付金が支払われる保険です。医療保険の中でも、がんに特化した保障が受けられます。
医療保険と同様、事業保障や福利厚生としての活用方法がメインとなります。
| 主な補償内容 | がんによる入院・検査・手術 |
|---|---|
| 保険料 | 一定 |
| 保険期間 | 一生涯 |
| 保険金 | 治療給付金20万円、入院給付金1万円/1日など |
| 解約返戻金 | なし |
| 満期返戻金 | なし |
| おすすめの活用方法 | 事業保障、福利厚生 |
法人保険を比較するときのポイント
法人保険を比較するときは、基準を明確に持つことが大切です。
ここからは、法人保険選びで考えるべきポイントをいくつかご紹介します。
目的に適した保険を考える
法人保険を選ぶ際、最初に考えるべきなのが「何のために加入するのか」という目的です。法人保険の加入目的には、経営者の万が一に備える保障目的のものから、退職金や事業承継対策、課税の繰延による税金対策まで、さまざまな種類があります。
例えば、経営者の死亡リスクに備えるなら定期保険、従業員の福利厚生のためなら養老保険や医療保険が候補になります。まずは自社にとって必要な目的を明確にし、それに合った法人保険を選ぶことが重要です。
キャッシュフローを考える
法人保険の保険料は経費として計上できる場合があるものの、長期間にわたる支払いが必要になります。そのため、加入前にキャッシュフローへの影響を慎重に検討することが重要です。
今は支払いに問題がなくても、業績が悪化すれば資金繰りに悪影響をおよぼす可能性があります。必要な保障を吟味し、将来にわたって保険料の支払いができるかシミュレーションしましょう。
出口戦略を考える
法人保険に加入する際は、解約や保険金の受け取り方など、将来の出口戦略も考えておきましょう。法人保険は長期契約になることが多いため、途中で方針を変更する可能性も考慮しつつ、事前に出口戦略を想定しておくことが必要です。
例えば、解約返戻金を退職金として活用する計画がある場合は、退職時期と解約返戻率のピークを合わせる必要があります。また、事業承継時に保険金を活用する場合も、スムーズな資産移転には適切なプラン設計が大切です。
保険以外のサービスもチェックする
法人保険には、さまざまなサービスが付帯する場合があります。例えば、以下のようなサービスが含まれているケースがあります。
- 経営コンサルティング
- 健康診断やメンタルヘルスの相談窓口
- 事故や災害時の対応サポート
保障内容だけでなく、これらの付加価値も比較検討することで、より自社に適した法人保険を選ぶことができます。
【2025年版】経営者におすすめの法人保険ランキングTOP12
ここからは、法人保険の商品を当サイト独自のランキング形式で紹介します。どの商品も法人向けのサービスが充実しているので、保険選びの候補に加えてみましょう。
なお、関連記事では保険の種類別に人気商品を紹介しているので、こちらもよろしければ参考にしてください。
※契約条件によって解約返戻率などのデータが変わる場合があります。詳しくは保険代理店などにお問い合わせください。
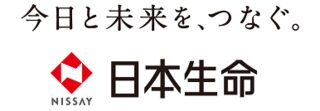
| 保険の種類 | 長期平準定期保険 |
|---|---|
| 解約返戻率 | 要確認 |
| 加入可能年齢 | 18歳~79歳 |
| 保険期間 | 満100歳まで |
ニッセイ(日本生命保険相互会社)の長期定期保険は、長期の死亡保障および高度障害保障を受けられる保険です。契約貸付制度の利用や、保険料払込済の終身保険(払済保険)への変更ができます。リビング・ニーズ特約が自動付加され、余命6か月以内と診断されたときは死亡保険金を全額または一部を受け取れます。
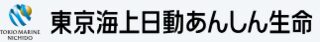
| 保険の種類 | 長期平準定期保険 |
|---|---|
| 解約返戻率 | 最高100.5%※低解約返戻金期間は70% |
| 加入可能年齢 | 要確認 |
| 保険期間 | 満99歳まで |
東京海上日動あんしん生命の長割り定期は、低解約返戻金期間(解約返戻率の低い期間)を定めることで保険料を割安に抑えた長期保険です。低解約返戻金期間は、55歳、60歳、65歳、または全期間から選択できます。事業保障から退職金準備、勇退時の事業承継資金など、幅広く活用できる保険です。
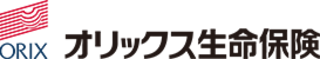
| 保険の種類 | 長期平準定期保険 |
|---|---|
| 解約返戻率 | 最高84.8% |
| 加入可能年齢 | 要確認 |
| 保険期間 | 満99歳まで |
オリックス生命のプライム定期は、経営者向けに設計された大型かつ長期の保障が魅力です。保険金額が高額であるほど保険料が割り引かれる「高額割引制度」を採用しており、コストを抑えて保障を確保できます。災害割引特約や傷害特約など、経営者のニーズに合わせた特約を付加することも可能です。

| 保険の種類 | 長期平準定期保険 |
|---|---|
| 解約返戻率 | 最高81.1% |
| 加入可能年齢 | 15歳~80歳 |
| 保険期間 | 満100歳まで |
エヌエヌ生命の定期保険Qualityは、最高9億円の大型保障を確保できる生命保険です。保険期間は最短5年~最長100年まで選べるので、ニーズに合わせて柔軟に設定できます。保険料払込免除の制度があり、所定の身体障害などになると保障を維持したまま保険料の払込が免除されます。

| 保険の種類 | 長期平準定期保険 |
|---|---|
| 解約返戻率 | 最高104.7%※低解約返戻金期間は70% |
| 加入可能年齢 | 5歳~75歳 |
| 保険期間 | 満98歳まで |
アクサ生命のLTTPフェアウインドは、98歳までの長期保証を割安な保険料で準備できる保険です。解約返戻率は100%を超えるため、資産運用としての活用もできます。リビング・ニーズ特約や傷害特約など幅広いオプションを取り揃えており、特に年金払移行特約を利用すると、保障を年金に変更することができます。

| 保険の種類 | 災害保障期間設定型定期保険 |
|---|---|
| 解約返戻率 | 最高96.6% |
| 加入可能年齢 | 要確認 |
| 保険期間 | 要確認 |
三井住友海上あいおい生命のオーナーズロードは、災害による死亡や高度障害に備える保険です。第1保険期間と第2保険期間に区分されており、第2保険期間に入ると災害以外の死亡・高度障害保障も手厚くなります。契約にあたって医師の診査は不要で、簡単な手続きで契約できます。
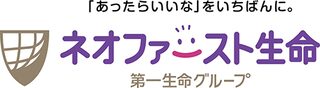
| 保険の種類 | 災害保障期間設定型定期保険、逓増定期保険 |
|---|---|
| 解約返戻率 | 最高95.1% |
| 加入可能年齢 | 20歳~80歳 |
| 保険期間 | 満99歳まで |
ネオファースト生命のネオdeきぎょうは、基本タイプと逓増タイプの2種類を選べる保険です。選択したタイプによって、保険金額の契約条件や保障内容が変わります。契約時は健康状態に関する4つの告知で申し込めるため、忙しい経営者でもスムーズに加入が可能です。
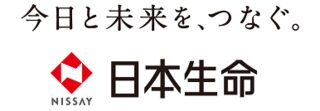
| 保険の種類 | 逓増定期保険 |
|---|---|
| 解約返戻率 | 要確認 |
| 加入可能年齢 | 18歳~77歳 |
| 保険期間 | 要確認 |
日本生命の逓増定期保険は、低解約期間後に毎年50%の割合で保険金額が増えていき、最大で5倍まで増加します。保険金額が増えても保険料は一定です。また、リビング・ニーズ特約が自動で付帯します。契約者貸付制度や払済保険への変更ができるので、資金需要に合わせて柔軟に活用できます。
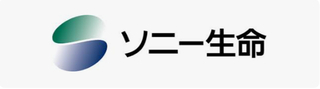
| 保険の種類 | 養老保険 |
|---|---|
| 解約返戻率 | 要確認 |
| 加入可能年齢 | 0歳~78歳 |
| 保険期間 | 要確認 |
ソニー生命の特殊養老保険は、死亡・高度障害に加えて満期保険金がある保険です。保険期間の満了時、基本保険金の2倍の金額を受け取れるため、退職金準備に向いています。リビング・ニーズ特約や傷害特約、がん特約など豊富なオプションがあるため、ニーズに合わせたプランを組み立てられます。
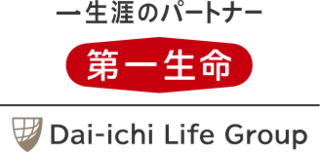
| 保険の種類 | 逓増定期保険 |
|---|---|
| 解約返戻率 | 要確認 |
| 加入可能年齢 | 20歳~80歳 |
| 保険期間 | 満99歳まで |
第一生命のマジェスティは、保険金額が毎年5%複利で増えていく逓増定期保険です。最大で5倍まで増加し、以降の保険金額は一定となります。3大疾病(所定のがん・急性心筋梗塞・脳卒中)や要介護状態などになったとき、保険料負担が免除される「保険料払込免除特約」を付加可能です。
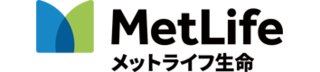
| 保険の種類 | 医療保険 |
|---|---|
| 解約返戻率 | なし |
| 加入可能年齢 | 要確認 |
| 保険期間 | 終身 |
メットライフ生命のMy Flexは、基本保障を3つのタイプから選んだうえで、がんや3大疾病の保障を組み合わせる医療保険です。選んだ基本保障によって、入院給付金(入院日数に応じて支払われる保険金)と入院一時金(日数にかかわらず一回の入院で支払われる保険金)のどちらを重視するか選べます。

| 保険の種類 | がん保険 |
|---|---|
| 解約返戻率 | なし |
| 加入可能年齢 | 0歳~85歳 |
| 保険期間 | 終身 |
アフラックの「生きる」を創るがん保険 WINGSは、法人向けに特化したがん保険です。経営者が入院したときの事業保障や、従業員にがんが発覚したときの見舞金として活用できます。がんと診断されたときや、検査・入院・通院・手術などさまざまな段階で保険金を受け取れます。
今回こちらでご紹介した保険商品以外にも、法人保険は各種様々な商品があります。最適な法人保険とは、皆さんの加入目的や、会社の状況などによっても変わります。ご自身の目的に応じて、法人保険の種類や保険商品をチェックしてみてください。
どの保険商品に加入するのが良いのか分からない場合には、自分で悩むよりも様々な保険商品を知り尽くした法人保険や財務戦略のプロに相談することも一つの手です。
月間33万PVを誇る当サイト、法人保険比較.NETでは、税務上のルールに則った正しい法人保険の活用方法や、目先の節税だけではなく10年先を見据えた財務戦略のアドバイスを行うコンサルタントの無料紹介を行なっています。相談や紹介料は完全無料なので、法人保険について詳しく知りたい方はぜひお気軽にご登録ください。

10年先を見据えた
法人保険の無料相談サービス
法人保険比較.netでは、法人保険の専門家と連携し、企業のリスク分析や保険の加入・見直しを無料で相談できるサービスを提供しています。
法人保険加入
生命保険・損害保険の新規加入、見直しに関して、お見積りや最適な保険商品のご提案を致します。
リスク分析
事業内容や財務状況から、企業が抱えているリスクを分析。法人保険を活用した対策のお手伝いを致します。
退職金制度・福利厚生
保険を活用した退職金制度や福利厚生の導入により、企業の信頼性と競争力を向上します。
法人保険のプロが、経営者の皆様のお悩みを無料でお伺いします。
法人保険比較.netの相談サービスでは、このような悩みを解決するプロをご紹介します。
- 保険プランのご提案・見積もり
- 保険による節税対策の最適化
- 経営者の個人資産の最大化
- 事業承継対策
- 退職金準備
- キャッシュフロー最適化
- 従業員向け保険制度の導入
- 企業年金制度の整備
無料紹介サービスのメリット1
経験豊富な法人保険・財務戦略の専門家をご紹介

金融・保険業界で長く業務経験を積んだ法人保険の専門家を無料でご紹介します。
各種法人保険を活用した節税、財務強化、効率のよい退職金の貯蓄、また損害保険を活用した企業リスクの備えなど、プロだからこそわかる「皆様の会社に最適な法人保険や財務戦略」をプロが提案してくれます。
無料紹介サービスのメリット2
30社以上の保険会社から、経営者の皆様に最適な保険プランをご提案
30社以上の生命保険・損害保険会社から最適な保険プランをご提案可能。
どの保険会社にも偏らない立場だからこそ、経営者の皆様の状況に本当に合った保険商品の活用方法をアドバイスすることが可能です。

法人保険相談サービス
無料登録からご利用の流れ
-

登録
Web問い合わせフォームからご登録ください。ご利用は完全無料です。
-

コンサルタントより
ご連絡ご登録いただきますと、1日~1週間以内にコンサルタントよりご連絡させていただきます。その際に御社の課題や目標についてヒアリングさせていただきます。
-

ご提案
いただいた内容をもとにコンサルタントが御社に最適な法人保険やソリューションをご提案いたします。ご希望に合わせて対面やオンライン打ち合わせが可能です。
-

各種サポート
ご提案したプランにご納得いただけた場合、保険加入などのお手続き等のサポートをさせていただきます。
法人保険比較.netのお約束
-

ご相談は無料です。安心してご利用下さい。
-

複数の保険会社から、最適な保険商品・プランをご提案。
中立な立場で、経営者の皆様に寄り添ったアドバイスをさせていただきます。 -

無理な勧誘等は一切行いません。
ご提案の内容に必ずご加入・ご契約いただく必要はありませんので、まずはお気軽にご相談ください。