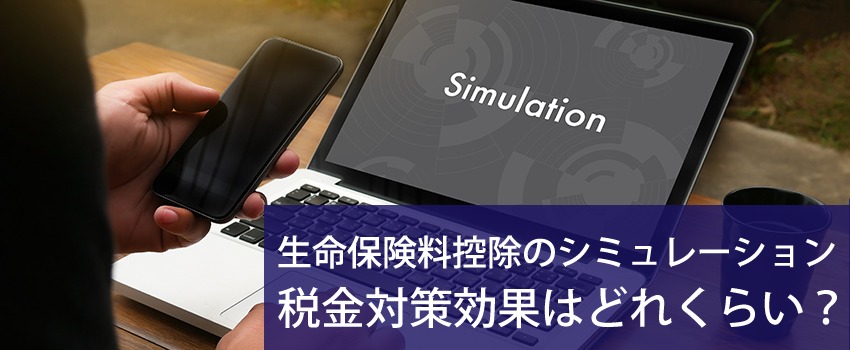法人保険では、支払った保険料を支払った年に損金算入できない場合があります。その例外ルールとして規定されているのが「30万円特例」です。
30万円特例が適用されると、「その年の支払保険料=当該年度の損金」として経理処理が可能です。
法人保険の30万円特例をうまく活用すれば、企業は効率的な節税(課税繰延)が可能になり、経営・財務戦略において大きなメリットをもたらします。
本記事では、法人保険の30万円特例が適用される条件や損金算入ルールを解説。特例活用時の注意点も併せてお伝えします。
法人保険を使った税金対策をお考えの方や、複雑な損金算入ルールをきちんと理解したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
「法人保険の30万円特例」とは全額損金算入を認める例外ルール
「法人保険の30万円特例」とは、保険料の全額損金算入(支払った保険料全額を当期に損金算入)を認める例外ルールです。
以下は、前提となる損金算入の原則ルールと、特例の内容をまとめたものです。

| 特例対象の法人保険 | 前提となる損金算入の原則ルール | 特例内容 |
|---|---|---|
| ①解約返戻金がない(またはごく少額)定期保険や第三分野保険 | 保険料は期間経過に応じて損金算入する(払った年に全額損金化するのではなく、契約期間に合わせて少しずつ経費にする) | 短期払いかつ年間支払保険料が被保険者1人あたり30万円以下の場合、その全額を当期に損金算入できる →詳しい解説部分にジャンプ |
| ②高額な解約返戻金がある定期保険や第三分野保険 | 解約返戻率が50%超のものは、最高解約返戻率が高いほど「資産計上」が必要になり、損金算入が先送りされる | 最高解約返戻率が70%以下かつ年換算保険料が被保険者1人あたり30万円以下の場合、資産計上が不要となり、全額を当期に損金算入できる →詳しい解説部分にジャンプ |
※①…法人税基本通達9-3-5、②…法人税基本通達9-3-5の2
原則通りに経理処理をすると、支払った保険料全額を当該年度に損金化できない場合があります。
そこで例外的に全額損金算入を認められたのが「法人保険の30万円特例」です。
【用語解説】
解約返戻金…保険を解約した際、保険会社から払い戻されるお金。解約返戻金を受け取った場合、そのときまでに支払った保険料累計額に対して何割になるかを解約返戻率という。
定期保険…生命保険のうち、保険期間に期限があるもの。
第三分野…生命保険や損害保険に当てはまらない保険。医療保険・がん保険・就業不能保険など。
年間支払保険料…その年度に実際に支払った保険料の金額
年換算保険料…契約全体の総払込保険料を、保険期間の年数で割って「1年あたりに換算した額」

「法人保険の30万円特例」と呼ばれる規定は2種類ある
「法人保険の30万円特例」と一括りにしていますが、実際は2種類の規定があり、それぞれ異なる例外規定です。
2つの例外規定(法人保険の30万円特例)
- ① 解約返戻金がない(またはごく少額)定期保険や第三分野保険
- 短期払いかつ年間支払保険料が被保険者1人あたり30万円以下の場合、その全額を当期に損金算入できる
- ② 高額な解約返戻金がある定期保険や第三分野保険
- 最高解約返戻率が70%以下かつ年換算保険料が被保険者1人あたり30万円以下の場合、その全額を当期に損金算入できる
インターネット上ではどちらか片方のみ(あるいは混同して)説明しているケースもあるため注意しましょう。
具体的にどのような条件で、どのような効果があるのか、詳しく解説します。
① 「解約返戻金がない(ごく少額)定期保険や第三分野保険」での30万円特例
「解約返戻金がない(ごく少額)定期保険や第三分野保険」では、短期払いかつ年間支払保険料が30万円以下の場合、その事業年度に全額損金算入が認められます。
※短期払い…保険期間より短い期間で保険料全額を支払う方法。
本来、解約返戻金がない(ごく少額)定期保険や第三分野保険は期間経過に応じて損金算入します。この原則を遵守すると、事業年度をまたがる形で保険料を支払ったとき、支払った年度に支払額の全額を損金化できない場合があります。
これに対し、30万円特例が適用されると「その年に支払った保険料」を当該年度に全額損金算入できるため、実際の支出に即した経理処理ができます。
「ごく少額」はいくら?
「解約返戻金がない(ごく少額)」のうち、「ごく少額」について国税庁による具体的な定義は示されていません。一般的には支払保険料の数%未満なら安全圏とされますが、詳しくは専門家に相談しましょう。
② 「高額な解約返戻金がある定期保険や第三分野保険」での30万円特例
「高額な解約金がある定期保険や第三分野保険」では、最高解約返戻率が70%以下かつ年換算保険料が30万円の場合、その事業年度に全額損金算入が認められます。
前提として、高額な解約返戻金がある定期保険や第三分野保険は一定の資産計上期間が設けられ、損金算入が制限されます。
| 最高解約返戻率 | 資産計上期間 | 期間中の経理処理 |
|---|---|---|
| 50%以下 | なし | 資産計上なし(支払った保険料を全額損金算入) |
| 50%超~70%以下 | 保険期間の当初4割 | 支払った保険料の40%を資産計上(60%を損金算入) |
| 70%超~85%以下 | 保険期間の当初4割 | 支払った保険料の60%資産計上(40%を損金算入) |
| 85%超 | 保険期間の開始~最高解約返戻率の期間が終了するまで(終了後、「(前年の解約返戻金-当年の解約返戻金÷年換算保険料)≧70%」となる場合は、その期間が終了するまで) | 10年目までは「支払った保険料×最高解約返戻率×90%」、11年目以降は「支払った保険料×最高解約返戻率×70%」を資産計上(10%or30%を損金算入) |
※資産計上した分は、契約期間の後半に取り崩し(分割して損金算入)を行います。また、保険金や解約返戻金の受取時、資産計上した分が残っていれば相殺して課税関係を精算します。
上記の通り、最高解約返戻率が50%超の場合、支払った保険料を当該年度に全額損金算入できません。
しかし、30万円特例が適用されると資産計上が不要となり、支払保険料全額をその年に損金算入できます。
特例適用による損金算入の違い
ここでは、特例の有無でどのような違いが生まれるのか、損金算入のシミュレーションを比較して解説します。
解約返戻金がない(ごく少額)法人保険の場合
定期保険で保険期間10年、年間保険料が15万円、短期払い契約により「5年間で毎年30万円を支払う」とします。
もし30万円特例がなく原則の「期間の経過」で損金算入を行う場合、「10年間で毎年30万円」の損金算入となります。実際のキャッシュアウトより少額で損金化しなければいけません。
経理処理の例(原則ルールの場合)
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 支払保険料 150,000円 前払保険料 150,000円 |
現金・預金 300,000円 |
実際の支出は30万円だが、経理処理は「支払保険料(損金算入)が15万円、前払保険料(資産計上)が15万円」。
※6年目以降、実際の支出はなくなるが、毎年15万円を支払保険料として損金算入。
しかし、特例により年間30万円の損金算入が可能なので、実際に支払った金額(30万円)を当該年度に全額損金化できます。
経理処理の例(30万特例の場合)
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 支払保険料 300,000円 | 現金・預金 300,000円 |
実際の支出(30万円)を全額損金として経理処理。
※6年目以降は資産計上も損金算入もなし。
高解約返戻金がある法人保険の場合
定期保険で保険期間10年、年換算保険料が30万円、最高解約返戻率が70%とします。
30万円特例がなく原則通りの場合、最高解約返戻率が70%だと「保険期間の当初4割は保険料の40%を資産計上」となります。
経理処理の例(原則ルールの場合)
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 支払保険料 180,000円 前払保険料 120,000円 |
現金・預金 300,000円 |
実際の支出は30万円だが、経理処理は「支払保険料(損金算入)が18万円、前払保険料(資産計上)が12万円」。
※5年以降は支払保険料30万円で損金算入。後半の取り崩し期間に入ったら、「資産計上した額÷残存期間」を損金として毎年上乗せ(取り崩し期間も最高解約返戻率によって異なる)。
しかし、30万円特例を適用すれば、支払った保険料を当該年度に全額損金算入できます。
経理処理の例(30万特例の場合)
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 支払保険料 300,000円 | 現金・預金 300,000円 |
資産計上が不要となり、「その年に支払った保険料=その年の損金」というシンプルな図式になる。
法人保険の30万円特例を活用するメリット
法人保険の30万円特例について詳しく解説しましたが、企業としては「具体的にどのようなメリットがあるのか?」が気になるところでしょう。
具体的なメリットとして、2つの効果を解説します。
メリット1.無駄のない節税(繰延)ができる
法人保険の節税効果は、「保険料の損金算入によって当期の課税所得を圧縮する」という仕組みです。
そのため、支払った保険料のうち何割を損金算入できるかは、支出に対する節税効率の高さにつながります。当然、100%損金算入できたほうが効率は高くなります。
「支出(保険料)を無駄なく節税につなげたい」と考える場合、法人保険の30万円特例は積極的に活用したい制度です。
注:保険料を損金算入することで当該年度の課税所得を圧縮できますが、将来的に受け取る保険金や解約返戻金は益金として課税されます。そのため、法人保険による節税は「課税を繰り延べる」というものであり、課税額を恒久的になくせるわけではないので注意しましょう。
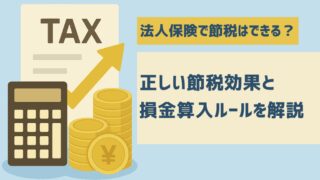
メリット2.経理処理をシンプルにできる
法人保険の損金算入ルールは複雑であり、経理処理にかかる業務負担も多くなります。
その中で30万円特例は、支払った保険料をその年に損金算入するというシンプルな処理が可能です。
「節税(繰延)したいけど難しい経理処理は避けたい」という場合も、30万円特例はわかりやすい手法としておすすめです。
特例と損金算入に関する注意点
法人保険の30万円特例を上手に活用すれば経営上のプラスになりますが、いくつかの注意点もあります。
加入してから後悔しないよう、事前知識としてしっかり押さえておきましょう。
年間保険料は契約している保険を合計して算出する
30万円特例の適用基準である「1人あたりの年間支払保険料(もしくは年換算保険料)30万円以下」は、すべての契約を合算して判定します。
例えば、同じ被保険者で複数の法人保険を契約していた場合、それらすべての保険料を足して30万円以下である必要があります。
合算した保険料が30万円を超えた場合、30万円を超えた部分だけでなく全額が30万円特例を適用できなくなるため、注意しましょう。
ただし、同時に複数契約の判定は「契約者ベース」でもあります。そのため、被保険者が同一人物でも契約者となる法人が別々であれば、それぞれに30万円特例を適用できます。
「過度な節税目的の活用」はリスクがある
30万円特例に限らず、節税目的で法人保険に加入する企業・経営者は少なくありません。
しかし、法人保険の本質は保障や資産形成であり、損金算入による節税(繰延)はあくまで副次的なメリットです。
国税庁は過度な節税に目を光らせており、不自然な法人保険による損金算入は否認される恐れがあります。
追徴課税などのトラブルを避けるためには、合理的な保障プランにもとづいて加入することが大切です。保険代理店やFP、税理士などの専門家に相談し、適切な範囲で法人保険を活用しましょう。
まとめ
今回は、法人保険の30万円特例について解説しました。
- 「解約返戻金がない(またはごく少額)定期保険や第三分野保険」で、短期払いかつ年間支払保険料が被保険者1人あたり30万円以下の場合、その全額を当期に損金算入できる
- 「高額な解約返戻金がある定期保険や第三分野保険」で解約返戻率が50%超でも、最高解約返戻率が70%以下かつ年換算保険料が被保険者1人あたり30万円以下の場合、その全額を当期に損金算入できる
2019年の税制改正以降、法人保険の経理処理方法は複雑になっています。
しかし、今回説明した30万円特例のような手法もあるため、賢く活用すれば戦略的に節税(繰延)が可能です。
当サイトが紹介している法人保険の専門家なら、30万円特例も含めて「的確な法人保険の活用方法」を提案できます。「自社に最適な法人保険の活用方法」を知りたい方は、ぜひ無料相談をご活用ください。
【こちらの記事もおすすめ!】
節税(繰延)効果が高い法人保険は?おすすめ商品をランキング
今のままで大丈夫?法人保険の見直し時期や注意点について
法人保険の見積もり・見直しは専門家へ!保険代理店の選び方
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス

- 法人保険を経営に活用したい
- いま加入している保険を見直したい
- 退職金制度や福利厚生を導入したい
- 事業承継や相続について考えたい
- 税金対策や財務戦略を相談したい
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて
"無料"で貴社に最適な保険プランを提案します。