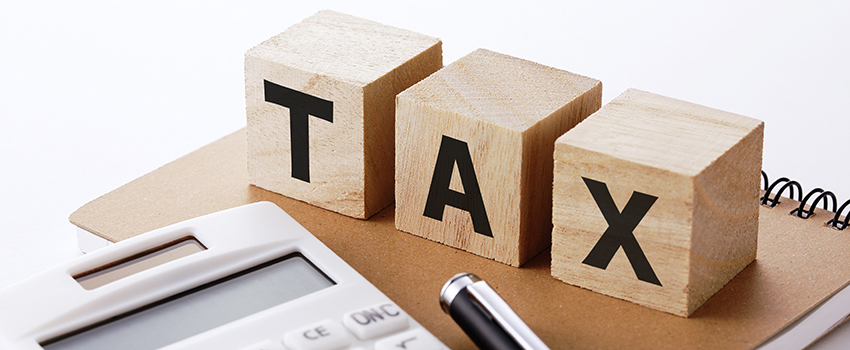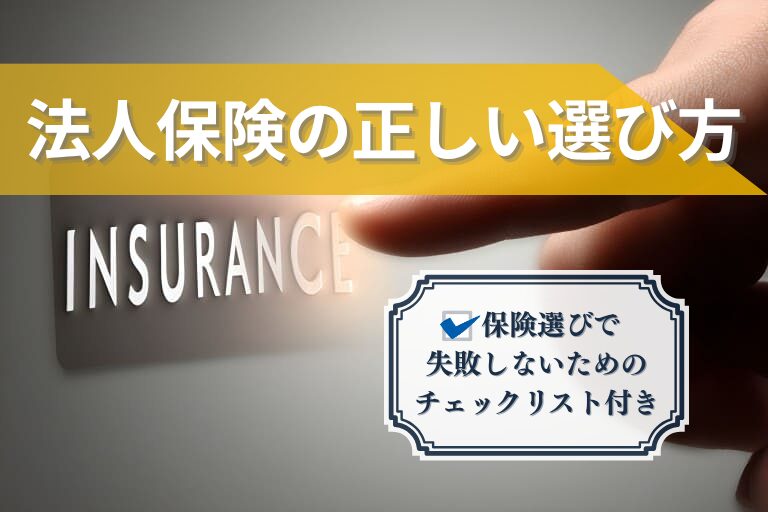相続税や贈与税をはじめ、事業承継にはさまざまな費用がかかります。
これらの節税対策として使えたのが、一般社団法人の設立による節税スキームです。
現在、税制改正により以前のような節税はできませんが、それでも一定の効果はあります。
この記事では、一般社団法人を使った節税の仕組みと、税制改正による影響について解説します。
一般社団法人を使った節税を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
一般社団法人を使った節税対策では「相続税の回避」が可能だった

一般社団法人を使った節税は、「社団節税」ともいわれます。
一般社団法人に資産を移動することで、半永久的に相続税が課税されないというものです。
具体的にどのような仕組みだったのか、一般社団法人の特徴とあわせて解説します。
一般社団法人とは
一般社団法人とは、非営利性を保ちながら、柔軟な事業活動を行える法人形態のことです。
持分がない(=オーナーがいない)ことが特徴で、株式会社で例えると「株主のいない法人」といえます。
一般社団法人における「非営利性」とは、余剰利益を分配しないことを指し、役員・従業員に報酬や給与を支給することは可能です。事業で余剰利益が出た際には、次年度に繰り越して事業に再投資します。
なお、設立には最低社員2人と理事1人が必要で、登記と定款作成が必要です。
一般社団法人を使った具体的な節税スキーム
一般社団法人を使った節税スキームは、「個人の財産を一般社団法人に移す」という仕組みです。
一般社団法人は持分がないため、保有する財産も特定の個人に帰属しません。そのため、相続財産を法人へ移せば、個人が対象である相続税を回避できます。
相続人が一般社団法人の代表理事になれば、法人に移転した財産を実質的に支配可能です。事業主として必要な財産(株式など)を移転すれば、事業承継時の節税も可能です。
2018年の税法改正により相続税の回避は規制された

相続や事業承継の節税対策として活用できた一般社団法人ですが、行き過ぎた節税に国が動くこととなり、2018年の税制改正で規制が強化されます。
具体的には、「特定一般社団法人」という概念が生まれ、相続税の課税対象になるようルールが変更されました。
特定一般社団法人とは、一般社団法人のうち次のいずれかの要件を満たすものです。
- 相続開始直前の同族役員数が役員総数の2分の1を超えている
- 相続開始前の5年間で、同族役員数が役員総数の2分の1を超える期間が3年以上ある
同族役員とは、以下のいずれかに該当する人を指します。
- 被相続人(死亡した本人)
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の3親等内の親族
- 被相続人と特別な関係にある人(被相続人が会社役員となっている会社の従業員など)
この規制により、相続税の計算上「財産は被相続人から一般社団法人に遺贈された」とみなされ、「一般社団法人の純資産額 ÷ 被相続人を含む同族理事の人数」の金額で相続税が課税されるようになりました。
仮に税制改正前に一般社団法人を設立していたとしても、被相続人が2021年4月以後に死亡した場合は相続税が課せられます。
改正後も一定の節税効果はあり

税制改正によって一般社団法人の節税効果は縮小しましたが、全くなくなったわけではありません。
例えば、役員に占める親族の割合を3分の1以下にするなど、一定の要件を満たせば相続税の対象から外れます。
また、「課税対象額 = 一般社団法人の純資産額 ÷ 被相続人を含む同族理事の人数」という計算上、通常の相続税より課税額が少なくなる可能性もあります。
以前より条件は厳しくなりましたが、節税対策として無意味というわけではなく、状況次第では効果的な手法となります。
相続税以外で一般社団法人を設立するメリットは?

一般財団法人を設立するときは、相続税以外でのメリットにも着目しましょう。
非営利型の一般社団法人に該当すれば、非収益事業から生じた所得が非課税になります。
例えば公益事業や共益事業による所得は、法人税の課税対象外ということです。当然、収益事業をまったく行わない法人であれば、所得にかかる税金を支払う必要はありません。
また、非営利型法人の要件を満たす一般社団法人であれば、寄付金も非課税になります。これは、収益事業から生じた所得のみが課税対象となるためです。
節税が目的の場合、上記のようなメリットも考慮し、総合的な視点でリターンを検討しましょう。
まとめ

一般社団法人は相続税の節税対策として有効でしたが、2018年の税制改正により節税効果が大幅に減少しています。
ただし、改正前ほどではないものの、現在も一定の節税効果は期待できるため、検討の価値はあるでしょう。
一般社団法人の税務は複雑なので、設立を検討している方は専門家のアドバイスを受けながら進めることをおすすめします。
【こちらの記事もおすすめ!】
法人税の節税はどうやる?具体的な対策方法を解説!
法人・富裕層に人気の税金対策とは?
法人保険は節税になる?仕組みと活用方法について
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス

- 法人保険を経営に役立てたい
- いま加入している保険を見直したい
- 退職金制度や福利厚生を導入したい
- 事業継承や相続について考えてたい
- 税金対策や財務戦略を相談したい
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて"無料"で最適な保険プランを提案します。