
法人が株式投資を行うと、長期的な視点で見て節税につながる可能性があります。
ただし、株式投資にはリスクもあるため、始める際はいくつかの注意点も押さえておくことが大切です。
この記事では、法人が節税目的で株式投資をするメリットとデメリットを詳しく解説します。
節税目的での投資にどのような効果があるのか、経営者の方はぜひご確認ください。
法人が節税目的で株式投資をするメリット

法人が節税目的で株式投資をするメリットは、次の通りです。
- 損益通算ができる
- 10年間の損失繰越が使える
- 経費として計上できる費用が多い
損益通算や損失繰越など、利益の圧縮による節税が期待できます。
損益通算ができる
法人が株式投資を行えば、損益通算で利益を圧迫して節税につながります。
損益通算とは、同年分の利益と損失を合算することです。
法人は個人と違って、所得種類に区分が設けられていません。
そのため、株式投資で損失が出ても、事業で利益が出ていれば相殺して課税対象額を少なくできます。反対に、事業の損失を株式投資の利益と相殺することも可能です。
10年間の損失繰越が使える
法人は、株式投資で分配金や売却益が赤字になった場合でも、10年間の損失繰越が認められています。
条件は、赤字を出した年を含めて青色申告を行なっていることです。
例えば、500万円の株を売って300万円の損失が発生し、翌年200万円の利益が出たとしましょう。この場合、「200万円 – 300万円 = -100万円」となり、翌年以降に100万円の赤字を繰り越すことが可能です。
経費として計上できる費用が多い
法人として株式投資を行えば、株式投資関連の出費を経費計上することで法人税を軽減できます。
以下は、経費計上できる費用の一例です。
- 書籍代
- パソコン・ソフトウェアの購入費
- セミナー費用
- セミナー会場までの交通費
- 光熱費
- 生命保険料
- 経営セーフティ共済の掛金
これらの経費をしっかり計上すれば、法人の利益が圧縮されて節税になります。
法人が節税目的で株式投資をするデメリット
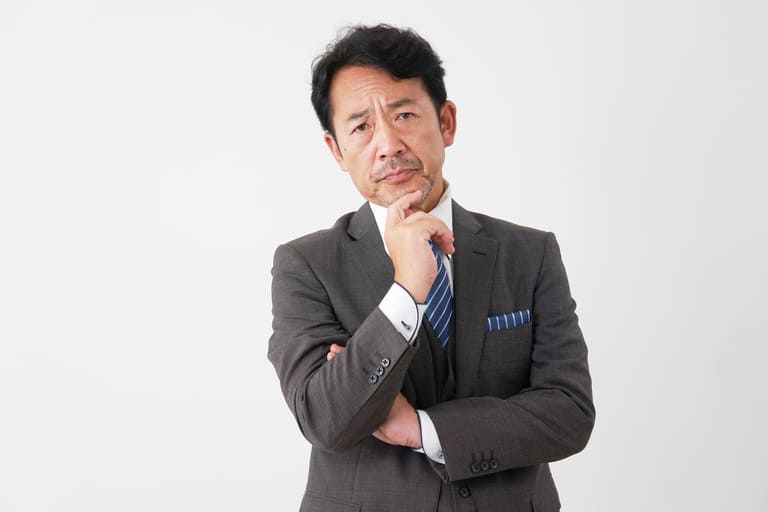
法人が節税目的で株式投資をするデメリットは、次の通りです。
- 税率が個人より高い
- 特定口座を使えない
- 含み益に課税される場合がある
法人特有のデメリットがあるので、個人投資との違いをしっかり把握しておきましょう。
税率が個人より高い
法人の税率は個人より高いのがデメリットです。
個人投資の利益は他の所得と分離して課税され、税率は一律20.315%となります。
一方、法人の株式投資は他の所得と合算され、地方税などを合わせた実効税率は約30%です(中小法人であれば年800万までの所得部分まで税率15%)。
さらに、法人はNISAなどの優遇措置も受けられません。総合的に見ると、税率面で法人は不利といえます。
特定口座を使えない
法人は特定口座が使えないため、一般口座を開設します。
特定口座とは、金融機関が株式投資の損益などを計算し、簡単な手続きで納税申告が行える口座のことです。
一般口座はすべての損益を自分で計算・納税する必要があり、時間と手間がかかります。
申告ミスを防ぐためには、会社に投資管理者を置いたり、税理士に依頼したりして、取引状況を判断できる状態にしておくことが重要です。
含み益に課税される
法人が株式を保有していると、含み益に課税される可能性があります。含み益とは保有する有価証券が取得価額を上回り、売却すると利益が出る状態のことです。
課税対象となるのは、「売買目的有価証券」とみなされる場合です。売買目的有価証券とは、売買の差額で利益を得ることを目的に保有している有価証券を指します。
例えば取得価額10,000円の株式を1,000株保有し、決算日の時価が11,000円だった場合、含み益は以下のように計算します。
ただし、満期日まで保有する場合など、場合によっては含み益に課税されない場合もあります。
適切な仕訳には専門知識が必要なので、詳しくは税理士などに相談してみましょう。
節税目的での株式投資が向いている例

ここでは、どのような法人が節税目的での株式投資に向いているか解説します。
自社の状況と照らし合わせて、実際に株式投資を始めるか検討してみましょう。
本業の利益が継続的に出ている法人
利益が安定して出ており、内部留保が積み上がっている法人は、株式投資を検討する価値があるでしょう。
銀行預金で寝かせているだけだとわずかな利息しか得られませんし、インフレ時には実質的な資産価値が減ってしまいます。株式投資を始めれば、損が出たときは節税、得すれば利益になるためバランスの取れた財務戦略が可能です。
具体的な例としては、高い利益率でキャッシュがあるコンサル・IT系企業や、設備投資が少ない業種(士業、広告代理業など)が向いているといえます。
退職金準備や事業承継対策を考えている法人
退職金や事業承継対策の一環として、株式投資は効果的な方法です。
会社に残りすぎた資産は、事業承継時に相続税・贈与税の負担を増やす原因になります。そこで、法人で株式投資を行い、最終的に退職金として個人へ移転することで、損金処理しながら資産を移すという流れが使えます。
「引退が数年後に控えている」「家族などに事業を引き継ぎたい」といった経営者は、株式投資による節税を検討してみましょう。
個人事業主の投資家は法人化するべき?

これまで解説してきた通り、法人化することで所得を損益通算できたり経費の適用範囲が広がったりと高い節税効果を得られます。
ただし、個人事業主の投資家が法人化する場合は、会社の設立・運用にコストがかかることを理解しておきましょう。
例えば会社を設立するには定款認証印紙代や登録免許税などで、およそ25万円かかります。また運用コストとして、社会保険料や顧問税理士への報酬、法人住民税なども必要です。
状況が揃えば法人化もおすすめですが、焦って進めてしまうと節税になるどころか、かえってキャッシュフローが悪化してしまいます。
今すぐ法人化しなくても、投資を続けていれば「絶対に法人化したほうが良い」という場面があるかもしれません。そのときすぐ法人化できるように、法人の知見も広めておきましょう。
まとめ

今回は、法人が節税目的で株式投資をするメリット・デメリットを解説しました。
メリットとしては、以下の3つがあります。
- 損益通算ができる
- 10年間の損失繰越が使える
- 経費として計上できる費用が多い
実際に株式投資が節税につながるかどうかは、法人の状況によって異なります。
他にもさまざまな節税方法があるので、まずは専門家に相談し、自社に最適なやり方をアドバイスしてもらうのがおすすめです。
【こちらの記事もおすすめ!】
法人税の節税対策とは?具体的な方法と選び方をわかりやすく解説
法人・富裕層にこそおすすめしたい節税商品を紹介!
法人保険に節税効果はある?ない?活用のポイントを解説
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス

- 法人保険を経営に活用したい
- いま加入している保険を見直したい
- 退職金制度や福利厚生を導入したい
- 事業承継や相続について考えたい
- 税金対策や財務戦略を相談したい
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて
"無料"で貴社に最適な保険プランを提案します。



















