
法人による不動産投資は、融資を活用しやすく、節税効果が大きいといわれています。
不動産投資に関連する支出の多くは経費として計上できるため、法人の利益調整にも役立ちます。
本記事では、法人が使える不動産を使った節税の裏ワザを徹底解説。具体的な手法を紹介します。
制度を合法的に活用し、手元に多くの資金を残しましょう。
法人が不動産を所有するメリットは?

法人名義で不動産を保有することで、さまざまな節税効果が期待できます。
具体的なメリットを詳しく見ていきましょう。
不動産投資の費用を経費にできる
法人の不動産投資は「事業の一環」として認められるため、多くの支出を経費として計上できます。
経費として認められる主な項目は、以下の通りです。
- ローンの金利
- 火災保険・地震保険の保険料
- 管理会社への管理委託料
- 固定資産税・不動産取得税などの税金
- 不動産経営に関わる交通費・交際費(業務に関連するもの)
- 司法書士や税理士への報酬
- 減価償却費
法人は、本業の所得と不動産所得を合算し、不動産投資で赤字が出た場合でも事業の黒字と相殺可能です。
課税所得を抑えられるため、不動産投資には大きな節税効果が期待できます。
任意償却で利益を調節しやすい
建物や設備には耐用年数が定められており、その期間に応じて購入費用を経費計上する「減価償却」を行います。
例えば、耐用年数が20年の建物を5,000万円で購入した場合、250万円を20年間にわたり計上します。
減価償却自体も経費計上を平準化できる(長期にわたって少しずつ計上できる)というメリットがありますが、法人の場合はさらに「任意償却」が可能です。
任意償却とは、本来なら耐用年数で分けて計上すべき費用を、法人が好きなタイミングで計上する方法です。事業の黒字が多いときに多く計上したり、赤字が多いときに少なく計上したりと、経営状況に合わせて調節できます。
ただし、過度な任意償却は税務署から目をつけられたり、銀行からの評価が下がったりする場合があるので注意が必要です。任意償却を行うときは、税理士などに相談しつつ適切な範囲で実行しましょう。
法人による不動産節税の裏ワザ5選

本記事で紹介する法人が不動産で節税する裏ワザは、以下の5つです。
- 裏ワザ① 買うときは借入金を使う
- 裏ワザ② 資産計上は細かく分ける
- 裏ワザ③ 売却損を繰り越す
- 裏ワザ④ 役員や従業員の自宅を社宅にする
- 裏ワザ⑤ 不動産事業を法人化して相続性を節税する
各裏ワザのポイントを解説するので、自社で活用できるかしっかり検討してみましょう。
裏ワザ① 買うときは借入金を使う
不動産を購入するときは、借入金を使うことで節税効果を高められます。
自己資金のみで購入すると一括で支出が発生するため、資金繰りが厳しくなります。一方、借入金を使えば支出を分割できる上、自己資金だけでは購入できない不動産の取得も可能です。
また、建物の場合は減価償却ができるので、長期的に課税所得を抑えられます。
ただし、高額・高金利の借入はリスクが大きいため、無理のない範囲に抑えめることが大切です。
裏ワザ② 資産計上は細かく分ける
建物の購入や修繕を行う際は、附属設備や器具等の資産計上を細かく分けることで節税効果を高められます。
建物全体を一括で減価償却するよりも、各資産ごとの耐用年数に応じて償却する方が、年間の経費計上額を増やせるからです。
【例】木造事務所の外装工事を実施した場合
- 建物:600万円
- 建物付属設備:200万円
- 器具・備品:100万円
| 資産 | 取得額 | 耐用年数 | 減価償却費(1年目) | |
|---|---|---|---|---|
| 一括計上した場合 | 建物 | 900万円 | 22年 | 40.9万円 |
| 資産ごとに分けた場合 | 建物 | 600万円 | 22年 | 27.3万円 |
| 建物付属設備 | 200万円 | 15年 | 13.3万円 | |
| 器具・備品 | 100万円 | 8年 | 12.5万円 | |
| 合計 | 900万円 | – | 53.1万円 |
このように、資産ごとに分けることで年間の経費計上額が増え、節税につながります。
裏ワザ③ 売却損を繰り越す
不動産売却で損失が出た場合、損失額を繰り越すことで翌年以降の黒字と相殺が可能です。これを「繰越欠損金の控除」といいます。
法人の場合、繰越欠損金の控除は最長10年間なので、経営状況に合わせて柔軟に課税所得を減らせます。
ただし、繰越欠損金の控除を利用するためには、以下の条件を満たさなければいけません。
- 売却損が生じた事業年度に青色申告で確定申告をしている
- 売却損が生じた事業年度以降も連続して確定申告をしている
- 帳簿などの書類を適切に保存している
なお、中小企業(資本金1億円以下)は年間所得の全額を控除できますが、大企業(資本金1億円超)は最大50%までとなります。
裏ワザ④ 役員や従業員の自宅を社宅にする
法人名義で社宅を契約し、入居者(役員・従業員)から一部賃料を徴収することで、差額の経費計上が可能です。
法人の節税だけでなく、入居者側も家賃負担を抑えられるため、双方にとってメリットがあります。
ただし、賃料を経費計上するためには、入居者の負担割合を50%以上にしたり、社宅規定を作成したりする必要があります。また、過度に豪華な社宅は認められない場合があるので注意しましょう。
裏ワザ⑤ 不動産事業を法人化する
法人が本業とは別に不動産投資を行う場合、別法人を立てるという裏ワザもあります。
法人化による節税の例
- 2つの法人に分けて所得を分散することで、中小法人の軽減税率(800万円以下の部分まで15%)を2法人分受ける。
- 商業施設やオフィス賃貸を購入し、不動産購入時の消費税還付を受ける
法人の節税だけでなく、事業分離によるリスク分散や事業承継対策、個人の相続対策としても有効なので、不動産投資の規模がある程度大きくなったら検討してみましょう。
まとめ
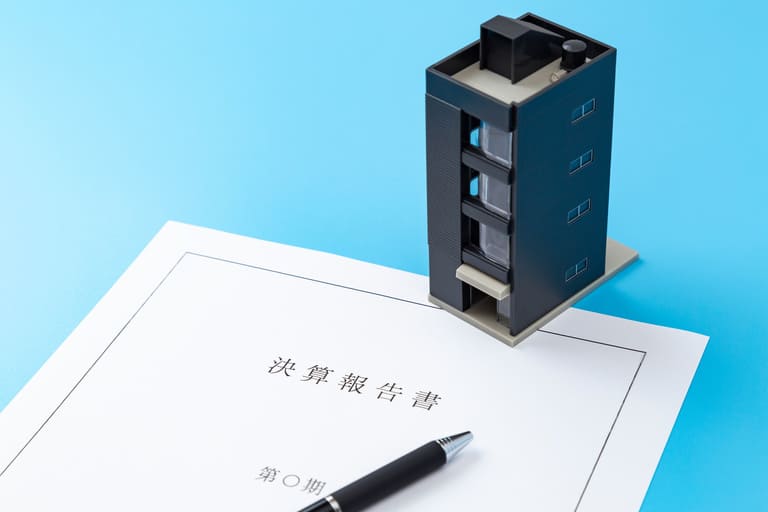
不動産を使った法人の節税方法は、経費にできる項目が多く、減価償却費で利益調整がしやすいといったメリットがあります。
ただし、過度な経費計上は税務調査の対象となり、追徴課税などの恐れもあります。
不動産に限らず、節税対策は税理士などの専門家と相談しつつ、適切な範囲で行うようにしましょう。
【こちらの記事もおすすめ!】
法人の節税対策を徹底解説!幅広い選択肢からベストな方法を選ぼう
法人・富裕層は要チェック!おすすめ節税商品を紹介
法人保険による節税効果とは?仕組みと活用ポイントを解説
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス

- 法人保険を経営に活用したい
- いま加入している保険を見直したい
- 退職金制度や福利厚生を導入したい
- 事業承継や相続について考えたい
- 税金対策や財務戦略を相談したい
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて
"無料"で貴社に最適な保険プランを提案します。



















