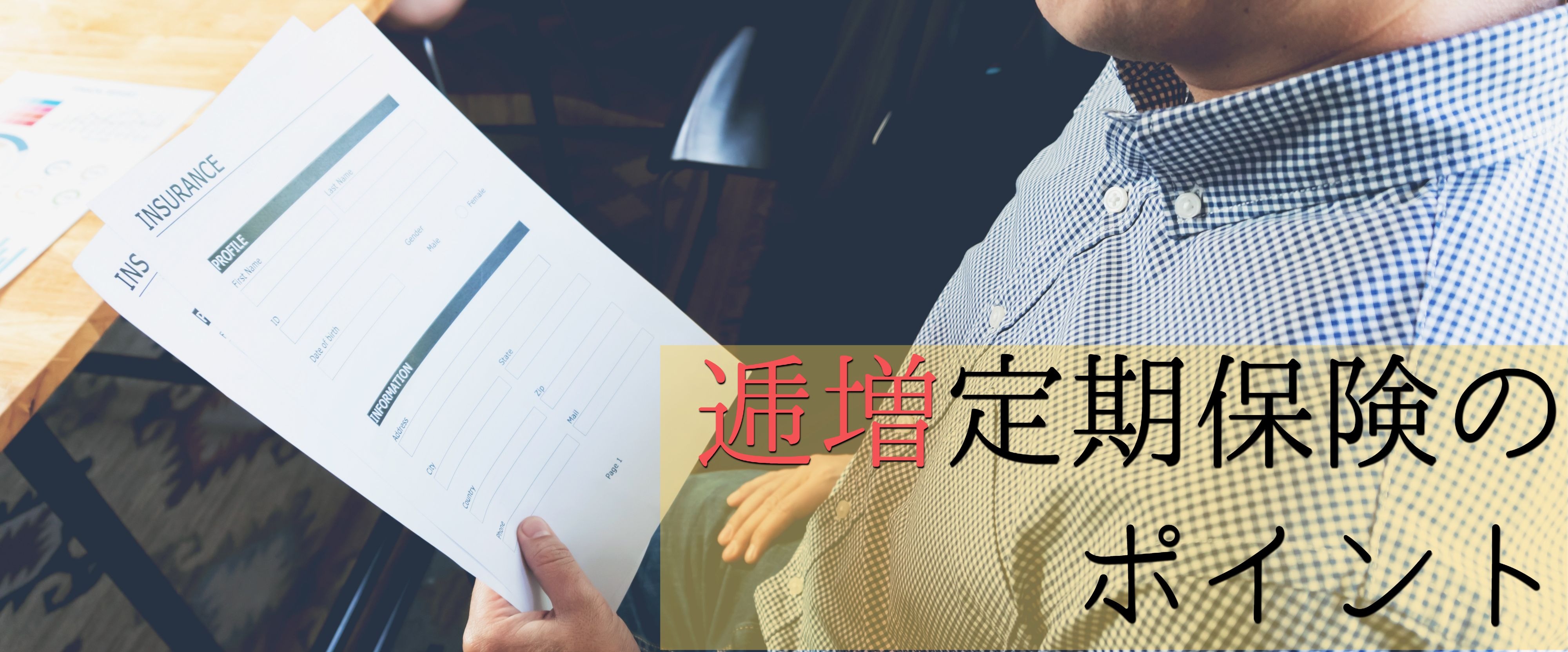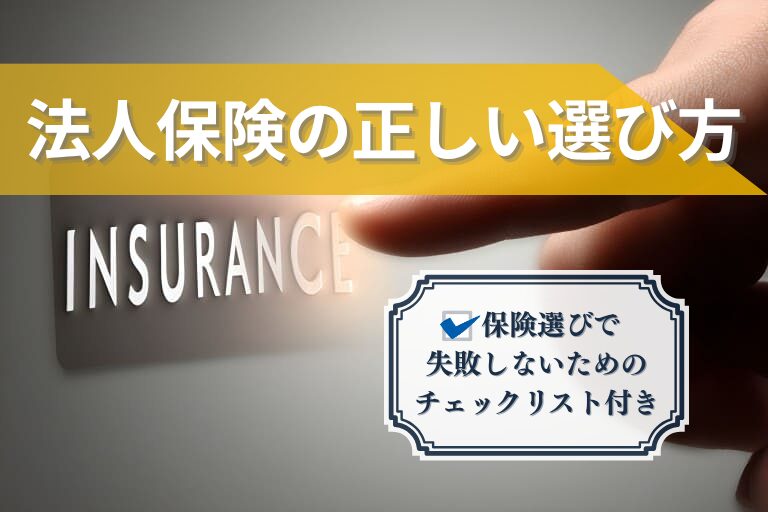経営者や経理・総務担当者の中には、
「法人が生命保険に入るメリットは?」
「どんな基準で保険を選べばいい?」
と悩んでいる方も多いでしょう。
法人向けの生命保険には多くの種類があり、それぞれ特徴や活用目的に大きな違いがあります。
事業保障や従業員の福利厚生など、目的に合わせた保険を選ぶことが大切です。会社によって最適な保険は異なるため、慎重な検討が求められます。
この記事では、法人生命保険の基本的な仕組みから、主な保険の種類、具体的な活用方法まで解説します。
法人向け生命保険とは?基本的な仕組みを解説

ここでは、法人保険と個人保険の違いや、法人向け生命保険の基本的な仕組みについて解説します。
法人保険と個人保険の違い
法人向け生命保険と個人向け生命保険の最も大きな違いは、契約者が法人か個人かという点です。
契約者以外の点では保険の仕組みはほぼ同じですが、法人が契約することで、事業の継続や財務管理の一環として役立てやすくなります。
違いをまとめると以下のようになります。
| 項目 | 個人保険 | 法人保険 |
|---|---|---|
| 契約者 | 個人 | 法人 |
| 被保険者 | 個人 | 役員・従業員 |
| 保険金受取人 | 個人(家族など) | 原則として法人 |
たとえば、個人の生命保険では、死亡した際に家族が保険金を受け取ります。一方、法人向け生命保険では法人が保険金を受け取り、事業の継続資金として用いることが一般的です。
法人向け生命保険の具体的な活用方法
法人向け生命保険は、企業のリスク対策として役立ちます。主な用途は以下のとおりです。
| 事業継続資金の確保 | 経営者の急な不在時に、事業を続けるための資金を確保する。 |
|---|---|
| 退職金の準備 | 役員・経営者の退職時に、解約返戻金(解約時に払い戻されるお金)を退職金として活用する。 |
| 事業承継対策 | 次世代経営者への円滑な引き継ぎ資金を確保する。 |
| 福利厚生の充実 | 従業員向けの保障制度として活用し、働きやすい環境を整える。 |
このように、法人向け生命保険は企業の安定した運営を支える手段の一つとなります。
万が一の事態に備え、事業の継続や従業員の福利厚生に役立てることが可能です。
法人向け生命保険のメリット

法人が生命保険に加入することには、主に次の3つのメリットがあります。
- 会社の事業継続に役立つ
- 経営者の退職金の準備ができる
- 社員の福利厚生を充実させられる
法人向け生命保険は、会社の安定経営を支える重要な手段です。それぞれの活用方法について詳しく見ていきましょう。
会社の事業保障として活用できる
法人が生命保険に加入すると、経営者に万が一のことがあった際の事業リスクを抑えられます。
経営者が突然亡くなったり、長期間仕事ができなくなったりすると、会社の経営に大きな影響を与えます。たとえば、取引先への支払いが滞ったり、借入金の支払いができなくなったりといった事態です。
その際に法人向け生命保険に加入していれば、保険金を活用して事業資金を確保できるため、経営の混乱を最小限に抑えられます。
さらに、資金を確保できれば、取引先や金融機関からの信頼を維持しやすくなります。
経営者に万が一のことがあっても、会社が安定して運営できる仕組みを整えておくことは、非常に重要です。
経営者の退職金の用意に利用できる
法人向け生命保険は、経営者や役員の退職金準備にも役立ちます。
経営者が長年会社を経営し、退職する際には、多額の退職金が必要になる場合があります。しかし、会社の財務状況によっては、すぐに用意するのが難しいこともあるでしょう。
法人向けの生命保険では、保険料を一定期間支払い続けると、解約時にまとまった返戻金を受け取れます。この資金を退職金に充当すれば、会社の負担を抑えつつ、経営者はスムーズに引退可能です。
ただし、解約返戻金には課税が発生するため、節税目的ではなく、計画的な資金準備の手段として考えるようにしましょう。
法人向け生命保険を適切に利用すれば、経営者の退職後の資金計画を安定させられます。
社員の福利厚生の充実に役立つ
法人向け生命保険は、社員の福利厚生を充実させるためにも活用できます。
生命保険の中には、社員が病気や事故で亡くなった場合の弔慰金や、入院時の保障が含まれるものがあります。こうした保険に加入しておけば、社員が安心して働ける環境となり、離職率の低下や魅力的な人材採用にもつながるでしょう。
また、特定の条件を満たした保険に加入すれば、保険料を経費として計上でき、一時的な節税(課税の繰延)もできます。
このように、法人向け生命保険を活用することで、社員の安心と企業の安定を両立できます。
法人向け生命保険のデメリット・注意点

法人向け生命保険には、事業を守るためのメリットが多くありますが、注意すべきデメリットも存在します。ここでは、特に重要な3つのポイントについて説明します。
- 資金繰りの負担や元本割れのリスクがある
- 解約返戻金に税金がかかる
- 税制改正で損をするリスクがある
法人保険を検討する際は、これらの点を理解したうえで判断することが大切です。
資金繰りの負担や元本割れのリスクがある
法人保険の保険料は、会社の資金繰りに影響を与える可能性があります。
契約後は長期間にわたって支払いが続くため、業績が悪化すると負担が大きくなり、経営を圧迫するかもしれません。
たとえば、利益が多い時期に節税対策として法人保険に加入したものの、翌年に業績が落ち込み、保険料の支払いが重荷になるケースが考えられます。
また、解約のタイミングによっては、支払った保険料よりも解約返戻金が少なくなることがあります。特に短期間で解約すると、ほとんど返戻金が受け取れない恐れがあるでしょう。
これらのリスクを避けるためには、長期間にわたって無理なく支払える保険料かどうか、慎重に検討することが重要です。
解約返戻金に税金がかかる
法人保険を解約すると返戻金を受け取れますが、その金額には税金がかかるため注意が必要です。
税負担が想定以上に増えると、会社の資金繰りが悪化することもあるため、慎重に対応する必要があります。
対策としては、退職金支払いや設備投資など支出がある時期に合わせて、解約返戻金を受け取る方法があります。利益と損失を相殺できるため、当年の税負担を軽減可能です。
法人保険を契約する際は、解約時の税金についても理解し、どのように受け取るか事前に計画しておくようにしましょう。
法人保険は税制改正の影響を受ける
法人保険に関する税制はこれまで何度も改正されており、契約時に想定していた節税効果が得られなくなるケースもあります。
たとえば、2019年の改正では法人保険の損金算入のルールが厳しくなり、保険料の一部を資産計上することが求められるようになりました。 その結果、それまで節税目的で活用されていた保険の多くが、想定通りの効果を発揮しなくなってしまいました。
さらに、2021年には、法人契約の保険を個人へ名義変更する際の評価方法が見直され、過去に契約した保険でも、名義変更時に想定以上の税負担が発生する事態が起きました。
特に、退職する経営者が法人から保険契約を引き継ぐケースでは、以前よりも高い金額で保険を個人に譲渡したとみなされ、結果的に負担が増えることにつながっています。
現在問題なく節税に活用できる法人保険であっても、今後の税制改正によって条件が変わり、結果的に損をするリスクがある点は知っておいたほうがよいでしょう。
法人向け生命保険の種類

法人向け生命保険は、主に下記の8種類が挙げられます。
- 逓増定期保険(ていぞうていきほけん)
- 平準定期保険
- 長期平準定期保険
- 養老保険
- 医療保険
- がん保険
- 生活障害保障定期保険
- 収入保障保険
これらの保険は、それぞれ異なる特徴と役割を持っています。それぞれの保険について詳しく見ていきましょう。
①逓増定期保険(ていぞうていきほけん)
逓増定期保険は、保障額が時間の経過とともに増加する生命保険です。一般的には、最大で5倍まで増加します。
ほかの定期保険(期間の定めがある生命保険)と比べると短い期間(5~10年程度)でピークになるため、短期間で資金を積み立てたいときにも向いています。
事業の成長や経営者の責任の増加に合わせて、将来の退職金や事業承継資金を計画的に準備するためにおすすめの保険です。
②平準定期保険
平準定期保険は、契約期間全体を通じて保険金額が一定の生命保険です。
解約返戻金がほとんどない一方、保険料は低めに抑えられるため、一定期間のリスクに備えたい場合に向いています。
主に、経営者の死亡時に備えた資金を確保するために利用され、万一の際に事業継続資金や従業員の給与支払いなどに充てられます。
③長期平準定期保険
長期平準定期保険は、平準定期保険より保険期間が長く設定されている生命保険です。被保険者の年齢が、保険満了日時点で90歳から100歳程度に設定されます。
保険期間が長いことで解約返戻金が高くなっており、解約返戻率(支払った保険料に対する解約返戻金の割合)は最高で80%~95%程度になります。
長期間かつ高額の保障と、資産の積み立て(比較的高めの解約返戻金)の両立が可能な生命保険です。
④養老保険
養老保険は、一定期間保険料を払い続けると、満期時に支払った保険料の一部またはそれ以上の金額を受け取れる生命保険です。
死亡時の保障を用意しつつ、満期時の払い戻しによる貯蓄も両立できます。
役員や従業員の退職金準備や福利厚生として採用されることが多く、死亡時には死亡保険金としても機能します。
⑤医療保険
医療保険は、入院、手術、治療といった医療リスクに備える生命保険です。
急な病気や怪我による医療費の負担を軽減し、従業員の福利厚生として機能します。
また、経営者を被保険者にして、保険金を経営資金や見舞金に充てることも可能です。
⑥がん保険
がん保険は、がんと診断された際に所定の保険金が支払われる生命保険です。
近年は、保険診療だけでなく、先進医療や自由診療などにも対応できるプランが増えています。
医療保険と同様、従業員の福利厚生や経営者の万が一に備える対策として活用できる保険です。
⑦生活障害保障定期保険
生活障害保障定期保険は、死亡保障に加え、高障害状態や要介護になったときの保障もカバーする生命保険です。
経営者や従業員が働けなくなった場合に、定期的な保険金が経済的な支援となり、日常生活の維持や事業運営の継続に役立ちます。
解約返戻金もありますが、ピーク時でおおむね70〜80%程度なので、貯蓄より保障を重視したい法人におすすめです。
⑧収入保障保険
収入保障保険は、被保険者が働けなくなった場合に毎月一定額の収入が支給される生命保険です。
基本は年金形式での受取になりますが、場合によっては一時金として受け取ることも可能なので、自社の状況に合わせて柔軟に選択できます。
保険期間の経過に伴い保険金額は下がっていきますが、一方で保険料は低水準なので、保険料負担を抑えつつ保障の確保が可能です。
法人向け生命保険を選ぶ際のポイント

企業の備えとして効果的な法人保険ですが、実際に加入するときはいくつかチェックすべき点もあります。
無駄な保険に加入してしまわないよう、ポイントをしっかり確認しておきましょう。
保険加入の目的を明確にする
まず、生命保険に加入する目的をはっきりさせることが大切です。企業が直面するリスクや経営目標によって、必要な保障内容は異なります。
たとえば、従業員の福利厚生を目的とする場合と、事業承継のための資金準備を目的とする場合では、必要な保険の種類が大きく変わります。
目的を明確にすることで、企業にとって本当に必要な保険を選べます。ここが保険選びのスタート地点になるので、しっかりと検討するようにしましょう。
保険料支払いが会社の資金に与える影響を確認する
次に、保険料の支払いが企業の資金計画にどのような影響を与えるかを評価しましょう。
長期間にわたる支払いは、キャッシュフローに負担をかける可能性があります。毎月の保険料が高額であると、他の重要な経営活動に必要な資金が不足し、経営を圧迫するかもしれません。
保険加入時には、無理のない支払い計画を立て、企業の資金繰りに支障がないかを事前に確認しましょう。
解約返戻金の計算方法を把握しておく
解約返戻金の計算方法を正しく理解することも大切です。計算方法を知らないと、大きな損失となるかもしれません。
たとえば、養老保険や貯蓄型の終身保険などでは、契約後の早い段階で解約すると、多くの場合元本割れする恐れがあります。
多くの法人向け生命保険では、契約期間が進むにつれて返戻率は上がり、100%やそれに近い数値になります。
このような仕組みを理解し、解約時期を慎重に計画することで、より効果的に資金計画へ組み込むことができるでしょう。
節税効果の限界を確認する
節税目的で法人向け生命保険に加入する場合、節税効果には限界があることを理解しておきましょう。
かつては、企業が加入する生命保険の保険料は全額または半額が損金として認められていました。そのため、支払った保険料を経費にできることで税負担を軽減し、契約満期や解約時に返戻金を受け取ることで、有効な節税手段とされていたのです。
しかし、2019年10月の通達改正以降、保険期間が3年以上の定期保険で最高解約返戻率が50%を超える場合、損金算入できる割合が大幅に制限され、従来のような節税効果は得られにくくなっています。
現在は以前よりも、法人向け生命保険による節税が難しくなっているため、事業保障や退職金準備といった目的をメインに考えることが大切です。
まとめ

今回は、法人向け生命保険の基本的な仕組みや個人保険との違い、そして企業経営における活用方法について解説しました。
法人が契約者となる生命保険は、事業継続資金や退職金、福利厚生の充実といった多様なメリットをもたらし、企業のリスク管理や財務戦略を支える重要なツールとなります。
それぞれの保険の特徴や運用方法を正しく理解し、自社の経営状況に合わせた最適な選択をすることが、企業の安定運営には欠かせません。
この記事を参考に、法人向け生命保険を経営戦略の一環として効果的に活用していきましょう。
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス

- 法人保険を経営に活用したい
- いま加入している保険を見直したい
- 退職金制度や福利厚生を導入したい
- 事業承継や相続について考えたい
- 税金対策や財務戦略を相談したい
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて
"無料"で貴社に最適な保険プランを提案します。