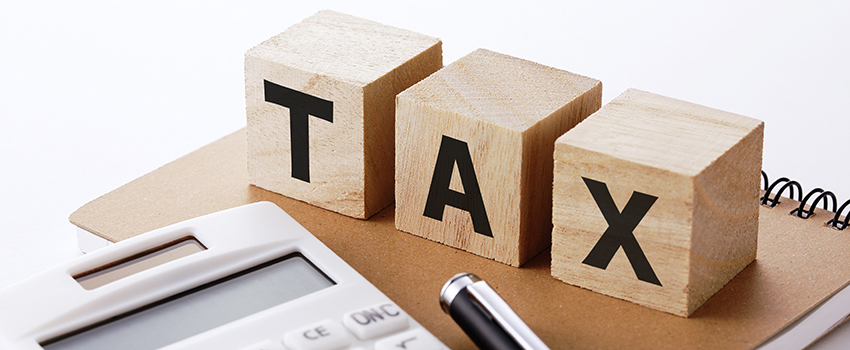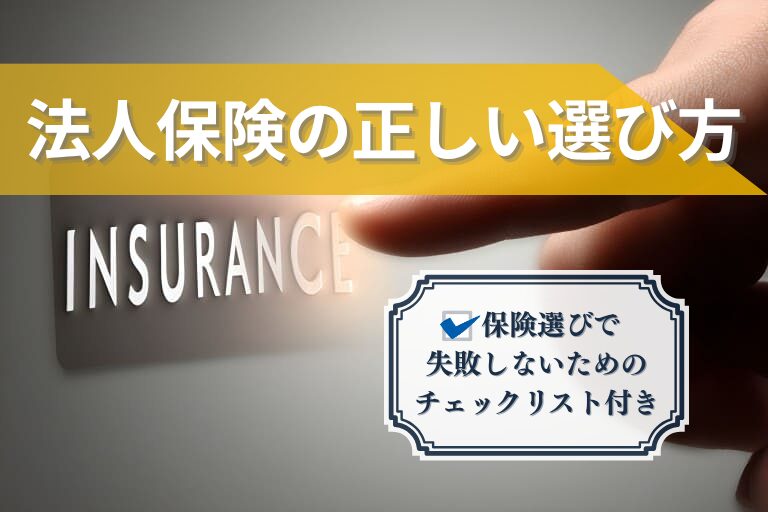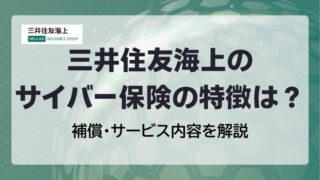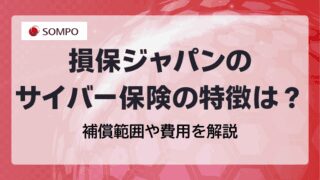「1人社長は節税できるって本当?」「法人化のメリットや注意点は?」
個人事業主やフリーランスで活動している方々の中には、上記のような疑問をお持ちの方も多いでしょう。
法人設立による1人社長化は、適切なタイミングで行えば大幅な節税が可能です。ただし、法人化に伴うリスクやコストもあるため、売上など事業の状況を踏まえて慎重に検討する必要があります。
本記事では、1人社長が節税できる理由や、法人化を検討すべき年収の目安、さらには注意点について詳しく解説します。
節税に頭を悩ませている個人事業主やフリーランスの方は、ぜひ最後までご覧ください。
1人社長になることで得られる節税メリット6選

法人化は、以下のような税制上のメリットが得られます。
- 所得税の計算が変わる
- 給与所得の控除が使える
- 経費計上できる幅が広がる
- 赤字繰越や消費税免税などの制度的優遇がある
- 保険等の法人契約で将来の備えと税金対策を両立できる
- 消費税の免税措置がある
これらのメリットを最大限活用することが、1人社長による節税の秘訣です。
それぞれ詳しく解説します。
メリット1.所得税の税率が変わる
法人と個人事業主では税金の種類が変わり、所得額によっては法人のほうが低い税率になります。
個人事業主の場合、事業で得た所得には所得税が累進課税方式で課され、所得が増えれば増えるほど税率も段階的に上昇します。税率は最大で45%す。
一方、法人化すると法人所得税の対象となり、定率課税方式が適用されます。税率は原則23.2%ですが、中小法人(資本金1億円の法人)なら年800万円以下の部分まで15%です。
詳しくは後述しますが、おおむね年収800万円〜900万円以上の個人事業主であれば、法人化して1人社長になったほうが節税になる可能性があります。
メリット2.給与所得控除が使える
法人化すると、法人から事業主自身に給与(役員報酬)を支払う形になるため、給与所得控除が適用されます。個人事業主には「給与」という形の収入が存在しないため、この給与所得控除は適用されません。
給与所得控除の内容は以下の通りで、最低でも年間55万円の控除が受けられます。
| 給与収入(年収) | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 1,625,000円まで | 550,000円 |
| 1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
| 1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
参照:国税庁|給与所得控除
※収入金額が660万円未満の場合、より詳細に設定された所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)を参照します。
メリット3.経費計上できる幅が広がる
法人は個人事業主より経費として認められる項目が増加するため、課税所得を減らしやすくなります。適切な範囲で経費を増やせば、大幅な節税につながります。
法人化することで経費計上が可能になる主な項目は、以下の通りです。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 役員報酬 | 法人では社長自身に支払う報酬を「給与」として経費処理できる。個人事業では自分への報酬は経費にできない。 |
| 社宅費用(法人契約) | 会社名義で賃貸契約を結び、社宅として役員に貸与することで、家賃を経費処理可能。 |
| 出張日当(旅費日当) | 実費の交通費とは別に、日当として一定額を非課税で支給でき、その支給額を法人の経費にできる(規定に基づく必要あり)。 |
| 役員退職金 | 一定の条件下で役員退職時に支給する退職金は法人の経費とできる。個人事業主には退職金の概念が存在しない。 |
| 法人契約の保険料(定期保険など) | 一部の生命保険や医療保険などは法人契約にすることで、保険料の全部または一部を損金(経費)算入できる。 |
| 福利厚生費(一定条件) | 会社として役員・従業員に対して提供する福利厚生(例:健康診断、慶弔見舞金、忘年会など)は経費処理可能。1人社長でも条件を満たせば適用可能。 |
| 法人設立に関する費用の一部(設立費用の償却) | 登記費用・定款認証費用などの設立費用を繰延資産として償却処理できる。個人事業には設立費用の概念がない。 |
メリット4.長期間の赤字繰越ができる
法人の場合、赤字(欠損金)の繰越控除期間が最大10年間と、個人事業主の3年間に比べて長いという利点があります。
例えば、赤字を出した翌年すぐに黒字になるとは限らず、事業が安定するまで数年かかるかもしれません。繰越期間が長ければ、黒字になったときに「過去の赤字」と相殺して節税できる可能性が高くなります。
また、「今年中に黒字出さないと繰り越した赤字が無駄になる」といった焦りがなくなります。余裕を持った経営戦略で、計画的に利益をコントロール可能です。
メリット5.保険等の法人契約で将来の備えと税金対策を両立できる
法人名義で加入した保険や共済は、保険料を損金算入(経費計上)できます。損害賠償リスクに備える保険のほか、1人社長本人を被保険者とした生命保険も経費計上が可能です。
| 保険や共済の種類 | 説明 | 損金算入 |
|---|---|---|
| 生命保険 | 法人を契約者、役員や従業員を被保険者にすることで損金算入が可能。 | 一部または全額可能(契約内容による) |
| がん保険・医療保険 | 法人で契約し、役員・従業員の医療保障として活用。福利厚生費として処理可能。 | 一部または全額可能(契約内容による) |
| 損害保険 | 事業に起因する損害賠償などの補償。 | 一部または全額可能(契約内容による) |
| 中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済) | 取引先倒産時の連鎖倒産や経営難に備える共済。掛金月額5,000円〜20万円、最大800万円まで積立可能。 | 全額可能 |
※解約返戻金がある保険は、返戻金受取時に課税されるため、恒久的な節税効果はありません。あくまで課税の繰延(繰延型節税)になります。
ただし、保険商品の種類や契約内容によっては、全額が経費として認められない場合もあるため、事前の確認が必要です。
法人に特化したファイナンシャルプランナーなど、専門家に相談しつつプランを組み立てましょう。
メリット6.消費税の免税措置がある
課税売上高が1,000万円を超える事業者は消費税の課税事業者になりますが、個人事業主から法人になることで、最長2年間の免税措置を受けられます。
課税事業者になる条件は、前々年度(法人は前々事業年度)および前年度の前半6か月間で課税売上高が1,000万円を超えることです。設立したばかりの法人は、その期間に売上がないことになるため、免税事業者となります。
ただし、資本金1,000万円以上で法人化した場合や、インボイス制度の事業者登録をした場合は、免税措置を利用できません。
また、免税措置を2年間適用するためには、以下のいずれかを満たすことも必要です。
- 2期目前半6か月間の課税売上高が1,000万円以下であること
- 2期目前半6か月間の給与等支払総額が1,000万円以下であること
年収いくらから法人化を検討すべき?【ボーダーラインを解説】
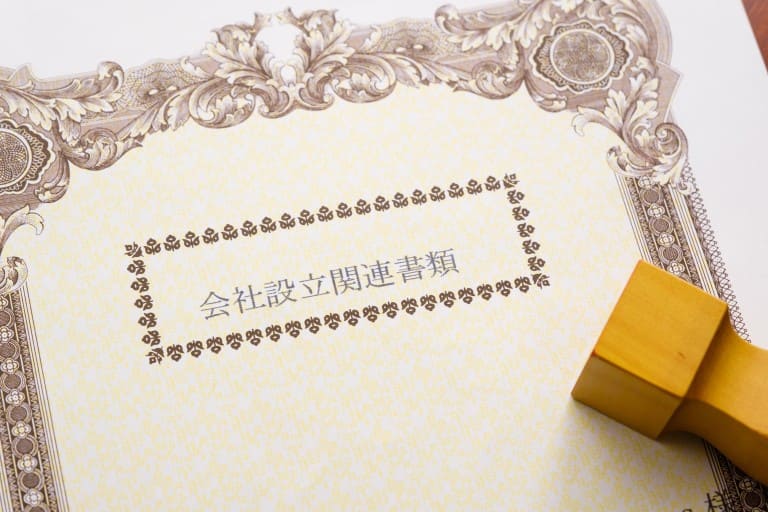
1人社長になることでさまざまなメリットがありますが、いざ検討するとなると、「いつ法人化すべきか?」は重要な問題です。タイミングを間違えると、手間が増えるだけで十分な節税効果を得られない可能性もあります。
節税を重視した場合、法人化の適切なタイミングは事業の利益水準が基準です。以下に、個人事業主と法人の税負担の違いを踏まえた検討ポイントを解説します。
個人事業主と法人の税負担を比較
個人事業主の所得税は累進課税制度が適用され、所得が増加するにつれて税率も高くなります。一方、法人税は23.20%以上にはなりません。
以下は、個人事業主に課される所得税と、法人(普通法人)に課される法人所得税の税率です。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
参照:国税庁|所得税の税率
| 法人の種類 | 税率 |
|---|---|
| 資本金1億円超の法人 | 23.2% |
| 資本金1億円以下の法人 | 課税所得のうち800万円以下の部分:15% 上記を超える部分:23.2% |
参照:国税庁|法人税の税率
※協同組合や公益法人など、法人の種類によって税率が異なります。
上記の表を比較すると、課税所得が900万円を超えた時点で、所得税(23%)と法人所得税(23.2%)の税率が逆転しているとわかります。
法人化の目安は年収800万円〜900万円
一定の課税所得で税率が逆転するとわかったところで、実際に課税額をシミュレーションしてみます。
| 課税所得 | 個人事業主の場合(所得税) | 法人の場合(法人所得税) |
|---|---|---|
| 600万円 | (600万 × 20%) − 427,500円 = 772,500円 | 600万 × 15% = 900,000円 |
| 700万円 | (700万 × 23%) − 636,000円 = 974,000円 | 700万 × 15% = 1,050,000円 |
| 800万円 | (800万 × 23%) − 636,000円 = 1,204,000円 | 800万 × 15% = 1,200,000円 |
| 900万円 | (900万 × 33%) − 1,536,000円 = 1,434,000円 | (800万 × 15%) + (100万 × 23.2%) = 1,432,000円 |
シミュレーションを比較すると、課税所得800万円から課税額は低くなります。
個々の状況によって多少前後しますが、大まかな目安として「年収800万円〜900万円」が法人化を検討するボーダーラインと覚えておきましょう。
より節税効果を高めるための工夫
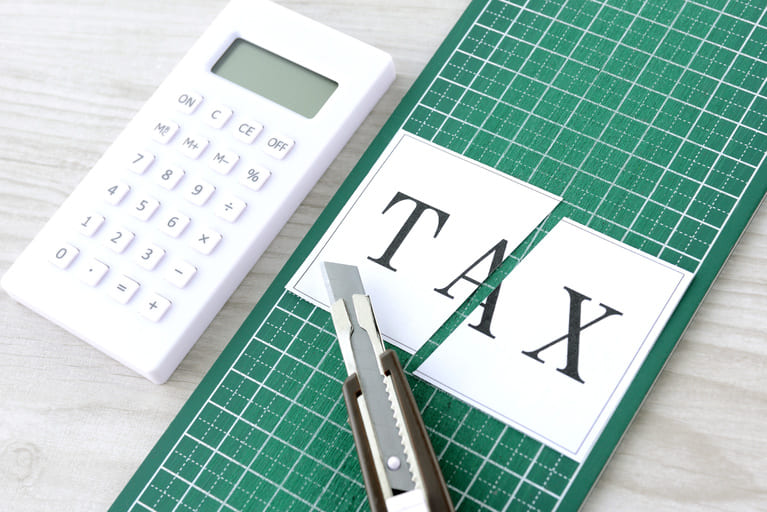
法人化による節税は、基本的な手法を実行するだけでも効果がありますが、さらに一歩踏み込んだ工夫でより節税につなげることが可能です。
ここでは、具体的な方法として2つの工夫を紹介します。
家族を役員にする
家族を法人の役員として登用し、報酬を分散させることで、世帯全体の課税総額を節税できます。
例えば、1人で1,000万円の役員報酬を得ると45%の税率が適用されますが、夫婦で500万円ずつ分ければ、それぞれ20%の税率まで減らせます。シミュレーションすると、約60万円も節税が可能です。
| 課税所得と人数 | 所得税 |
|---|---|
| 1,000万円×1人 | (1,000万 × 33%) − 1,536,000円 = 1,764,000円 |
| 500万円×2人 | { (500万 × 20%) − 427,500円 } × 2人= 1,145,000円 |
また、配偶者や親族を登用することで、給与所得控除や社宅制度、退職金制度を家族全体で活用できます。
ただし、業務実態のない役員(いわゆる名ばかり役員)に報酬を支払うと、税務調査で否認されるリスクがあるため、実際に会社の業務を担ってもらうことが前提です。役員登用には登記や定款変更なども必要になるため、事前に専門家へ相談すると良いでしょう。
マイクロ法人と個人事業主の「二刀流」にする
近年注目を集めているのが、「マイクロ法人(1人社長と同義)」と個人事業主を併用する、いわゆる“二刀流スキーム”です。
事業を法人と個人事業主の2つに分けて行うことで、それぞれの課税所得を減らせます。
ただし、法人と個人で経理処理を切り分ける必要があるため、日々の業務や確定申告などの手続きは煩雑になります。不自然な利益操作は税務調査のリスクもあるため注意が必要です。
1人社長の節税で注意すべきポイント

法人化によって得られる節税メリットは確かに大きいですが、その一方で見落とされがちなデメリットやリスクも存在します。
法人化による負担が思わぬストレスやコスト増につながることもあるため、事前に注意点を押さえておきましょう。
法人化に伴いコストが増える
法人は、設立から維持までさまざまな手続きが必要です。法人税の申告や決算報告、取締役会議事録の作成など、1人社長ですべてをこなすのは非常に手間がかかります。
これらの作業をすべて自分で行うのは現実的ではなく、通常は会計ソフトの導入や税理士への依頼が必要となります。それらのコストを計算すると、法人化による節税効果を超えてしまうケースも少なくありません。
節税目的の場合、法人化に伴うコストとのトータルバランスを見極めることが重要です。
赤字でも法人住民税が課税される
法人化の意外な落とし穴の一つが、赤字でも法人住民税の均等割が課税される点です。
均等割とは、法人の従業員数や資本金額を基準に税額を計算する方法です。法人住民税は、均等割で計算した金額と、法人税額を基準に計算する「法人税割」の合算で課税されます。
均等割は法人の売上に関係なく算出するため、赤字の年でも課されます。課税額の基準は自治体によって異なりますが、多くは数万円~数十万円程度です。
事業の立ち上げ期や一時的な赤字が続いた時期は、精神的にも金銭的にも負担となるため、事前に把握しておきましょう。
まとめ

1人社長として法人化することで、節税につながる選択肢は大きく広がります。
役員報酬の活用、社宅制度、共済や保険の損金算入など、多くの手法を組み合わせれば手取りを最大化することも可能です。一方で、事務的な負担や税務リスク、社会保険料の増加といった見えにくいコストやリスクも存在します。
重要なのは、「節税額」だけに目を奪われず、実際の手取りやライフスタイルに合った形で法人運営を行うことです。そして、制度や税制は毎年変化していくため、都度専門家と連携しながら、柔軟な運営を続けていくことが、1人社長として成功するための鍵となるでしょう。
【こちらの記事もおすすめ!】
法人税の節税対策を徹底網羅!各方法をわかりやすく解説
法人や富裕層なら税金対策は必須!おすすめの節税商品は?
法人保険で節税できる?税務上の仕組みと活用のポイント
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス

- 法人保険を経営に役立てたい
- いま加入している保険を見直したい
- 退職金制度や福利厚生を導入したい
- 事業継承や相続について考えてたい
- 税金対策や財務戦略を相談したい
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて"無料"で最適な保険プランを提案します。