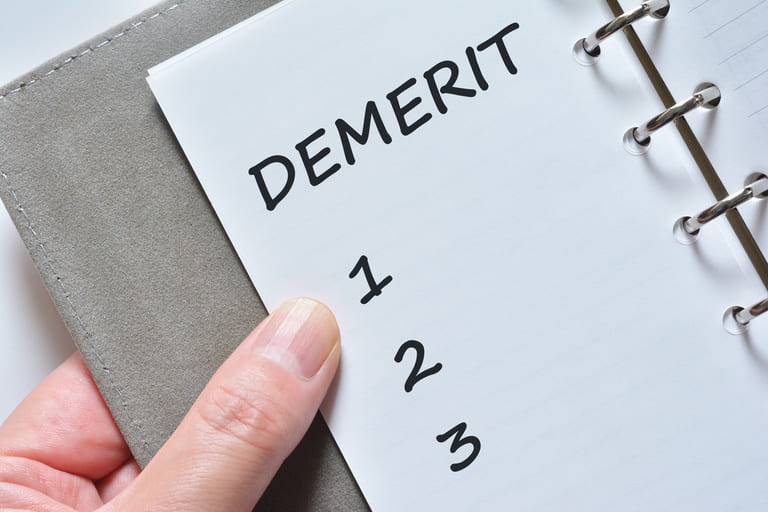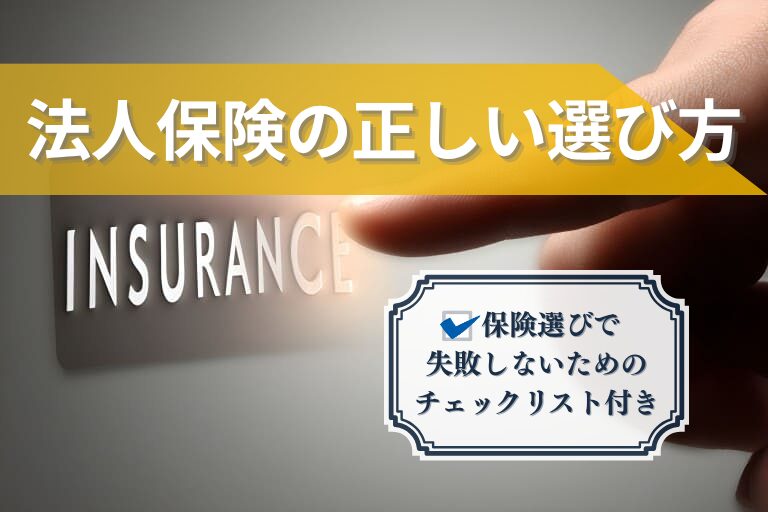法人保険は、企業のリスク対策や節税、退職金準備など、さまざまな目的で活用できる経営ツールです。一方で、加入時には注意すべきデメリットも複数あります。
たとえば、契約内容によってはキャッシュフローを圧迫したり、税務調査で指摘を受けたりなどのリスクがあります。これらのリスクを正しく理解しないまま契約すると、企業経営に深刻な影響を及ぼしかねません。
本記事では、法人保険における代表的な5つのデメリットと、そのリスクを回避するための実践的なポイントを詳しく解説。企業が法人保険に加入するとき、知っておくべき事前知識をお伝えします。
法人保険の加入・見直しを検討している経営者や企業担当者様は、ぜひ最後までご覧ください。
法人保険の5つの主なデメリット

法人保険とは、企業が法人名義で加入する生命保険や医療保険などを指し、主に役員や従業員を被保険者として契約します。企業が保険料を負担することで節税(課税の繰延)効果も発生し、リスク対策に留まらずさまざまな目的で活用されているのが特徴です。
ただし、法人保険加入時には以下のようなデメリットにも注意が必要です。
- デメリット1. キャッシュフローを圧迫する
- デメリット2. 解約返戻金が総支払保険料を下回る場合がある
- デメリット3. 税制改正により節税効果が縮小された
- デメリット4. 契約形態によっては税務調査で否認される
- デメリット5. 社内に不公平感が出ると分断が生じる
法人保険に加入するときは、上記のようなデメリットを把握したうえで、適切にプラン設計。運用することが重要です。
この項目では、各デメリットをわかりやすく解説します。
デメリット1. キャッシュフローを圧迫する
法人保険は、企業のキャッシュフローに大きな影響を与える可能性がデメリットとして挙げられます。
契約内容によって月額数十万円から数百万円の保険料が発生することもあり、とくに資金力に余裕のない中小企業では、毎月の保険料支払いが重くのしかかります。本業の運転資金や急な支出への対応力を低下させる原因となりかねません。
また、法人保険は中長期での運用が前提とされる商品が多く、途中解約をしても十分な解約返戻金が得られないケースが多いため、簡単に解約して資金を回収することもできません。
導入を検討する際は、現在の資金繰り状況や将来的なキャッシュフローを予測し、無理のない保険料設計をすることが不可欠です。具体的には、キャッシュフロー表やPL予測を使いながら、保険料による財務への影響を事前にシミュレーションすることをおすすめします。
デメリット2. 解約返戻金が総支払保険料を下回る場合がある
法人保険によっては、解約時に返戻金(保険会社から払い戻されるお金)を受け取れる場合があります。保険料の損金算入によって法人税の軽減(課税繰延)をしつつ、解約返戻金を退職金や事業投資の原資に充てるスキームが、基本的な法人保険の活用方法です。
しかし、解約返戻金は「それまで支払った保険料総額」を上回るとは限らず、多くの商品は下回るよう設計されています。つまり、「貯蓄代わり」という観点のみで考えると、トータルの損益はマイナスになる可能性があります。
また、解約返戻率(総支払保険料に対する解約返戻金の割合)は一定ではなく、契約から徐々に高くなり、ピークから契約終了に向けて下がるのが一般的です。この設計により、解約時期を誤ると大きな損失につながるかもしれません。
法人保険に加入するときは、解約返戻金で受け取れる金額と、保障や節税効果とのコストバランスを考える必要があります。また、返戻率の推移を把握し、ピークと資金需要の時期が重なるよう計画的に契約することが大切です。
デメリット3. 税制改正により節税効果が縮小された
節税目的で法人保険を活用する企業も多いですが、税制改正により以前ほどの効果を得られなくなったというデメリットがあります。
かつての法人保険は保険料全額を損金算入できたため、課税所得を大幅に圧縮するスキームが可能でした。
しかし、2019年に税制改正が行われ、貯蓄効果がある(解約返戻金や満期保険金がある)保険の損金算入割合が制限されます。
- 改正前:多くの商品で、保険料全額を支払った当年に損金算入できた。
- 改正後:解約返戻率に応じて損金算入割合が制限。保険期間の前半、4割や6割などが上限になる(残りは資産として計上し、保険期間の後半に損金算入する。その頃には解約返戻金が下がるため資金回収が難しくなる)。
※「30万円特例」や「福利厚生プラン」など、例外的なケースもあります。
現在も大きな節税効果は見込めますが、改正前のイメージで活用するのは難しいと考えましょう。
デメリット4. 契約形態によっては税務調査で否認される
法人保険の損金処理は複雑なルールが定められているため、適切な契約形態を取り、ルールに従った処理をしないと、税務調査で指摘されるリスクがあります。
たとえば、保険金の受取人が誰になっているかで、勘定科目や損金算入割合が異なります。また、「退職金準備」や「福利厚生目的」として損金算入していても、実際には役員や特定の従業員にのみ利益を供与しているとみなされると、税務署から「形式と実態の不一致」を指摘されるかもしれません。
前述の法改正も含めて、国税庁は法人保険の税務について監視を強めています。追徴課税を受けないためには、契約目的と実態の整合性を保ち、社内に運用ルールや規定を整備しておくことが重要です。
デメリット5. 社内に不公平感が出ると分断が生じる
法人保険は、経営者や役員向けに加入するケースと、従業員の福利厚生として導入するケースがあります。仮に経営者や役員向けにのみ加入すると、従業員の間に不公平感が生まれる可能性があります。
たとえば、役員には死亡保険金が数千万円単位で設定されている一方、従業員には何の保障も用意されていないという状況は、「保険料を会社が負担しているのに一部の上層部にしか恩恵がない」との不満が社内に広がるかもしれません。結果として、職場のモチベーション低下や従業員の離職につながるケースも考えられます。
さらに、損金処理の根拠として「福利厚生目的」を掲げているにもかかわらず、実態としては一部にしか恩恵がない状況は、税務署から否認されるリスクがあります。
制度として社内に公平性をもたせるためには、社内規定の整備や従業員向けの制度導入など、バランスの取れた設計が求められます。
法人保険のデメリットを回避するには?検討時の5つのポイント

法人保険に加入するうえでリスクやデメリットを回避するためには、契約前の入念な準備と、契約後の適切な管理が欠かせません。
以下の5つのポイントを押さえることで、不要な損失や税務リスクを防ぎつつ、目的に応じた合理的な保険活用が可能になります。
① 契約目的を明確化する
契約前に最も重要なのは「何のために法人保険を導入するのか」という目的を明確にすることです。たとえば、退職金準備、事業承継対策、万が一の死亡保障など、目的によって最適な保険種類や設計が大きく異なります。
目的が曖昧なまま契約してしまうと、結果的に保険が有効に活用されないだけでなく、損金処理や税務面での正当性も問われかねません。また、目的を明文化しておくことで、社内での合意形成もスムーズになります。
契約書・保険設計書には目的を明記し、必要に応じて取締役会議事録などの社内文書にも記録を残しておくと、税務調査時の対応にも有効です。
② 解約タイミングの見通しを持つ
法人保険の価値を最大限に引き出すには、解約返戻率のピークや税負担の最小化を意識した「解約タイミング」の見極めが極めて重要です。
ピークを過ぎると返戻率が急落するケースも多く、うっかり時期を逃すと本来得られたはずの資金が減少してしまうことがあります。また、受け取った返戻金が課税対象となることも踏まえ、解約時期は決算期や損益状況と合わせて検討すべきです。
定期的に解約シミュレーションを行い、会社の成長フェーズや資金需要に応じて柔軟に対応できる体制を整えておくとよいでしょう。
③ 複数保険の組み合わせを検討
法人保険は1本の契約にすべてを依存するのではなく、複数の保険商品を組み合わせることで、リスク分散と機能強化の両立が可能になります。
たとえば、退職金準備用に逓増定期保険を活用しつつ、万が一の死亡保障には定期保険を別に設定するという形で、それぞれの目的に特化した保険設計を行うことが有効です。
また、返戻率や損金算入の扱いが商品ごとに異なるため、複数契約によって法人税対策の選択肢を広げられます。これにより、特定の契約で税制変更や返戻率の低下があった場合でも、他の契約でリスクを補えるため、経営への影響を最小限に抑えられます。
ただし、複数契約には管理の手間もかかるため、加入目的・契約内容をしっかり整理し、台帳や管理表で一元管理することが不可欠です。複雑な設計になるほど、専門家のアドバイスを取り入れて精緻な運用計画を立てましょう。
④ 事業計画に連動させる
法人保険は単なる保険商品ではなく、企業の中長期的な経営戦略と密接に関わる金融ツールです。そのため、導入にあたっては会社の事業計画や将来の資金需要と連動させて設計する必要があります。
たとえば、3年後に設備投資を予定している、あるいは5年後に役員の退職が控えているといった具体的な計画がある場合、それに合わせて解約返戻金がピークを迎えるように設計することで、最大の効果を発揮できます。
逆に、事業計画との整合性が取れていない保険契約は、資金繰りの面でも税務の面でも非効率になりがちです。保険料負担が事業の成長を阻害することのないよう、予算管理とセットで設計を進めるべきです。
事業フェーズごとに必要な保障内容や資金戦略も異なるため、定期的な見直しと再設計を行い、常に最適な保障内容を維持しましょう。
⑤ FPや税理士と連携する
法人保険の導入・運用において、税務や財務の観点を踏まえたアドバイスが不可欠です。
税制改正や損金処理の適正性、会計処理の方法など、経営者だけでは判断が難しい部分も多数あります。そのため、ファイナンシャルプランナー(FP)や税理士との連携が重要となります。
とくに、契約設計時には「損金にできる範囲」や「解約返戻金の課税タイミング」など、将来の資金計画に関わる要素を含めて確認する必要があります。これを誤ると、当初の想定と大きく異なる結果になりかねません。
また、解約や出口戦略を検討する際にも、決算期とのバランスや資金用途との整合性を踏まえて最適なタイミングを見極める必要があるため、専門家の助言はリスク回避に直結します。
保険選びや財務戦略についてはFPに、具体的な税務や会計実務については税理士にと、分野ごとに専門家を使い分けましょう。
まとめ

法人保険は、退職金準備や事業承継、リスク対策といった経営上の多様なニーズに対応できる便利な金融ツールです。その一方で、キャッシュフローの圧迫や税制改正による節税効果の縮小、税務調査リスクなど、見落とされがちなデメリットが存在します。
とくに「節税になるから」と安易に契約してしまうと、返って経営に悪影響を及ぼす可能性があるため、導入時には慎重な検討が求められます。
保険は経営戦略の一部であるという認識を持ち、事業計画との連動を意識した活用が不可欠です。
これから保険に加入する場合は中長期的な計画設計を、すでに加入している場合でも適宜見直しを行いましょう。専門家のアドバイスも利用し、自社にとって最適な保障体制を常に維持することが大切です。
法人保険のデメリットを正しく理解し、自社の事業計画と連動させて、真の価値を発揮させましょう。
法人保険比較.netの
専門家マッチングサービス

- 法人保険を経営に活用したい
- いま加入している保険を見直したい
- 退職金制度や福利厚生を導入したい
- 事業承継や相続について考えたい
- 税金対策や財務戦略を相談したい
法人領域を専門とするコンサルタントが、業界の傾向や各種法規も踏まえて
"無料"で貴社に最適な保険プランを提案します。