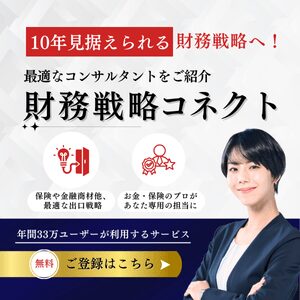2019年2月、国税庁が「法人保険の課税方法を見直す」と告知したことで、保険業界は一時騒然となりました。
いわゆる「バレンタインショック」と呼ばれるこの改正では、法人向け定期保険、ならびに第三分野の保険(医療保険・がん保険)の保険料の取り扱いが変更されました。
保険料の取り扱いが変わったことにより、経営者の間で流行していた「保険料を損金計上して節税する」という手法は大きな影響を受けます。
この記事では、2019年の国税庁による税制改正通達で変更となった「法人保険の保険料取扱いルール」をわかりやすく解説。また、税制改正後の法人保険による節税についてもお伝えします。
法人保険の節税効果について知りたい経営者の方は、ぜひ参考にしてください。
国税庁が法人保険の税制改正に踏み切った背景とは?

2019年2月、国税庁が法人保険を扱う生保会社に対し、法人保険の保険料取り扱いに関して見直しを検討していることを発表。見直しの内容は、法人保険の保険料取り扱い(損金計上などの経理処理)について新たなルールを設ける、というものです。
国税庁からこの税制改正通達が公布された背景には、本来の法人保険の趣旨から外れた「保険による節税」が行き過ぎたという事実があります。
改正以前、節税効果のある保険は経営者の間で人気を集め、保険会社も次々と新商品を開発・販売。競争が過熱し、過度に節税効果を強調した保険商品が乱立する事態となりました。
国税庁は商品ごとに個別の通達・指導を行っていましたが、規制をかいくぐる新たな保険商品も次々開発され、イタチごっこが続きます。
この状況を問題視した国税庁が、法人保険に関する税制のルール改正を発表。税法の適用指針である「法人税基本通達」の改正というかたちで、統一的なルールを設けるに至ります。
改正による保険料取り扱い変更点の概要
国税庁による税制改正は、2019年4月に公募されたパブリックコメントを経て、確定された新ルールが2019年6月末に発表されました。(法人税基本通達9-3-5)
税制改正の対象となった法人保険は、「法人向け定期生命保険」と「第三分野の法人保険(医療保険・がん保険等)」の2つです。
特に法人向け定期生命保険は、保険料の取り扱い(損金計上・資産計上)について細かな区分を設けた新ルールが定められました。
簡単に言えば、「解約返戻金のある保険は、最高解約返戻率に応じて保険料の損金・資産の計上割合が決められる」というルールになります。
- 法人保険の最高解約返戻率(ピーク時の解約返戻率)に応じて、保険料の損金計上・資産計上の割合を分ける
- なお、資産計上しなければいけない期間は、法人保険に契約してから所定の期間のみ
- 資産計上の期間についても、法人保険の最高解約返戻率に応じてそれぞれ決められる
最高解約返戻率が高い法人保険ほど、資産に計上しなければいけない保険料の割合が高く、なおかつ資産計上期間も長くなります。
次の項目から、改正後の具体的なルールを紹介していきます。
法人向け定期生命保険の改正内容

定期生命保険とは、期間に定めがある(終身ではない)保険商品です。逓増定期保険や長期平準定期保険などが該当します。
法人向け定期生命保険は、最高解約返戻率に応じて下記の表の通りの区分に分けられ、それぞれ決められた期間と割合で支払保険料の資産計上をする必要があります。
| 最高解約返戻率 | 資産計上期間 | 資産計上額 | 取り崩し期間(※1) |
|---|---|---|---|
| 50%以下 | 全額損金算入 | ||
| 50%超~70%以下※2 | 保険期間の当初40%の期間 | 支払保険料×40% (支払保険料×60%は損金計上) |
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上 |
| 70%超~85%以下 | 保険期間の当初40%の期間 | 支払保険料×60% (支払保険料×40%は損金計上) |
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上 |
| 85%超 |
①保険期間の開始日から最高解約返戻額を迎える期間の終了日まで ②1の期間経過後、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで |
保険期間開始日から10年経過日までは、保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上 11年目以降は、支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上 |
解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し |
| 最高解約返戻率:50%以下 | |
|---|---|
| 全額損金計上 | |
| 最高解約返戻率:50%超~70%以下※2 | |
|
資産計上 期間 |
保険期間の当初40%の期間 |
|
資産 計上額 |
支払保険料×40% (支払保険料×60%は損金計上) |
|
取り崩し 期間 |
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上 |
| 最高解約返戻率:70%超~85%以下 | |
|
資産計上 期間 |
保険期間の当初40%の期間 |
|
資産 計上額 |
支払保険料×60% (支払保険料×40%は損金計上) |
|
取り崩し 期間 |
保険期間の75%相当経過後、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩して損金計上 |
| 最高解約返戻率:85%超 | |
|
資産計上 期間 |
①保険期間の開始日から最高解約返戻額を迎える期間の終了日まで ②1の期間経過後において、年換算保険料に対する解約払戻金の増加割合が0.7を超える期間があれば、その期間の終わりまで |
|
資産 計上額 |
保険期間開始日から10年経過日までは、 11年目以降は、 |
|
取り崩し 期間 |
解約返戻金が最高金額になったあと、保険期間終了日までの期間で均等に取り崩し |
※1 取り崩し:残りの保険契約期間の年数に応じて、均等に分けること。
※2 解約返戻率が50%超~70%以下で、なおかつ被保険者1人当たりの年換算保険料合計額が30万円以下の場合は、保険料の全額を損金に算入することが可能。
①最高解約返戻率が50%以下の定期保険
最高解約返戻率が50%以下の定期保険は、保険期間が満了するまで保険料の全額を損金に計上できます。
②最高解約返戻率が50%超~70%以下の定期保険
最高解約返戻率が50%超~70%以下の定期保険では、保険期間の当初40%の期間を、支払保険料のうち40%を資産計上、残り60%を損金計上の処理を行います。
当初40%期間が過ぎれば、その後は保険料全額を損金計上。そして、最初に資産計上分は、保険期間の75%が過ぎたあとに取り崩します。
経理処理の例
【条件】
保険期間:30年
年間保険料:500万円の法人保険
| 資産計上期間 | 資産・損金 計上額 |
資産計上分を 取り崩す期間 |
|---|---|---|
| 1年~12年目まで | 資産:200万円 損金:300万円 (13年目以降は全額損金) |
23年目から |
③最高解約返戻率が70%超~85%以下の定期保険
最高解約返戻率が70%超~85%以下の定期保険では、保険期間の当初40%の期間を、支払保険料のうち60%を資産計上、残り40%を損金計上の処理を行います。
当初40%期間が過ぎれば、その後は保険料全額を損金計上。そして、最初に資産計上分は、保険期間の75%が過ぎたあとに取り崩します。
経理処理の例
【条件】
保険期間:30年
年間保険料:500万円の法人保険
| 資産計上期間 | 資産・損金 計上額 |
資産計上分を 取り崩す期間 |
|---|---|---|
| 1年~12年目まで | 資産:300万円 損金:200万円 (13年目以降は全額損金) |
23年目から |
④最高解約返戻率が85%超の定期保険
最高解約返戻率が85%を超える定期保険では、保険料の取り扱いが複雑になります。
まず、資産計上する期間は、保険期間開始から解約返戻金が最高額となる日まで。
資産計上する割合は、保険期間開始日から10年経過日までは、保険料×90%。11年目以降は、支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上。いずれも、残りの割合が損金計上です。
資産計上した保険料は、最高解約返戻金となる日を迎えた後に取り崩します。
経理処理の例
【条件】
保険期間:30年
年間保険料:500万円の法人保険
最高解約返戻率:87%、15年目に最高解約返戻金額になる
| 資産計上期間 | 資産・損金 計上額 |
資産計上分を 取り崩す期間 |
|---|---|---|
| ①1~10年目 | 資産:391.5万円 損金:108.5万円 |
23年目から |
| ②11年目~15年目 | 資産:304.5万円 損金:195.5万円 (15年目以降は全額損金) |
【第三分野保険(医療保険・がん保険)】税制改正による変更点

2019年の国税庁による税制改正通達では、第三分野の法人保険についても見直しのメスが入りました。
第三分野の法人保険では、税制改正通達で定められた経理処理のルールは
- 定期、もしくは終身タイプのの第三分野保険 保険料全期払いの場合
- 終身タイプの第三分野保険 保険料短期払いの場合(※)
の2つに分けられます。
※短期払い:
法人保険の保険料の支払期間を保険期間よりも短く設定し、保険料を短期間で払い込むこと。一年あたりの支払保険料額が大きくなるため損金計上できる額も大きくなり、税制改正前は第三分野の法人保険で節税する経営者が多く見られました。
①定期/終身タイプの第三分野保険(保険料全期払い)
こちらは、法人向け定期生命保険と同様の経理処理となります。
②終身タイプの第三分野保険(保険料短期払い)
1.被保険者一人あたりの年間支払保険料の合計が30万円以下
支払保険料の全額を損金として計上。
注意点として、一人で複数の医療保険やがん保険に加入していた場合、すべての支払保険料を合算する必要があります。
2.被保険者一人あたりの年間支払保険料の合計が30万円を超える場合
【保険料の払込期間中の経理処理】
下記の計算式で、損金計上する金額を求めます。
年間保険料 × 保険料払込期間 ÷ (116歳 – 被保険者の加入時年齢)
残りは、資産として計上。
【保険料の払込期間後の経理処理】
保険料払込期間中に損金計上していた金額と同じだけの金額を、被保険者が116歳になるまで引き続き損金として計上。
さらに、保険料払込期間中に資産として計上していた分を、116歳になるまで毎年取り崩して損金に計上します。
経理処理例
【条件】
終身型医療保険、保険料を5年間で払い込む。
年間支払保険料:80万円
保険料払込期間:5年
被保険者の加入時年齢:45歳
保険料払込期間中
【損金計上額】
800,000円 × 5年 ÷ (116歳 – 45歳)
= 56,338円
よって、損金計上できる金額は約5.6万円
【資産計上額】
800,000円 – 56,338円 = 743,662円
よって、資産計上する金額は約74.3万円
保険料払込期間終了後(被保険者50歳)
【損金計上額】
引き続き、毎年5.6万円を損金計上
【資産取り崩し額】
743,662円 × 5年 ÷ (116歳 – 50歳)
= 56,338円
よって、取り崩して損金に計上する金額は約5.6万円
国税庁の新ルールが適用されるのは通達後の契約から

国税庁による税制改正通達は、2019年6月末に発表されました。しかし、すぐさま税制改正の新ルールが適用されるわけではありません。
国税庁の通達によると、税制改正後の新ルールが適用されるのは、法人向けの生命保険に関しては「2019年7月8日以降に契約したもの」、そして第三分野の法人保険については「2019年10月8日以降に契約したもの」となります。
税制改正通達後のルールが適用されるのは…
- 法人向け生命保険:2019年7月8日以降の契約
- 第三分野の法人保険:2019年10月8日以降の契約
それ以前に契約した法人保険は、税制改正通達以前の経理処理をする。
したがって、2019年7月8日以前に加入している法人保険商品については、税制改正通達以前の従来通りのルールで税務処理が可能です。
改正以降「法人保険による節税効果」はどうなる?
国税庁による税制改正通達で、経営者の方が最も気にしているのは法人保険による節税についてではないでしょうか。
結論を言えば、支払い保険料の資産計上割合が増えたことにより、以前ほど節税効果は見込めなくなっています。また、そもそも解約返戻金の受取時に益金として課税されるため、永続的な節税目的には向いていません。
しかし、改正後も「課税の繰延」という効果は期待できます。課税を先延ばしにしつつ、万が一に備えた保障や資産形成を確保するなら、法人保険は優れた商品です。
また、解約返戻率50%以下の定期保険や、養老保険のハーフタックスプランなど、条件を満たせば保険料の半額もしくは全額を損金算入できるケースもあります。
今後の法人保険は、最新の税制や市場動向、自社が抱えるリスクなどから適切なプランを選ぶことがカギとなります。専門的な知識が重要となるため、法人コンサルティングに強いファイナンシャルプランナーなどにアドバイスを貰いましょう。
国税庁による法人保険の税制改正変更点まとめ

本記事では、2019年の国税庁による税制改正通達の内容について解説してきました。
国税庁の税制改正通達によって、特に法人向け定期保険の経理処理方法は非常に複雑になっています。
税制改正以前に契約した法人保険まで遡及されることはないものの、見直しや新規加入の際には新ルールが適用されるため注意が必要です。
また、法人保険を選ぶ際は、企業ごとの個別状況を考慮して考えなければいけません。法人保険を検討中の方は、専門家に相談して最適な保険プランを選びましょう。
【こちらの記事もおすすめ!】
解約返戻金の経理処理|出口戦略の考え方も解説
法人保険の税制上のメリットとは?改正後の活用ポイントを解説
法人の節税対策を徹底解説!保険以外の方法も紹介
財務戦略コネクトで最適なコンサルタントを無料で
ご紹介!
財務戦略コネクトは月間33万ユーザーが利用する法人保険.NETが提供する経営者に無料で財務戦略のプロをご紹介するサービス。
- 適正納税の範囲で安定した財務を確保したい
- 損害保険や生命保険など万が一のリスクに備えた法人保険に加入したい
- 財務対策として最適な法人保険をプロの目線から提案してほしい
- 退職金準備や事業継承など出口戦略をそろそろ考えていきたい
世の中には節税や税金対策を謳う単に会社にプールするお金を減らすリスクの高いサービスがたくさんあります。
しかし法人保険の2019年の税制改正により全額損金参入が難しくなったように、今求められるのはルールの範囲内で適正納税をしつつ、
法人に1円でも多くのお金を残し、会社の成長のために最適な資金投下を行う「財務戦略」。
これらを全て知り尽くした財務戦略のプロを"無料"で経営者の方にご紹介します。
ぜひお気軽にご登録ください。