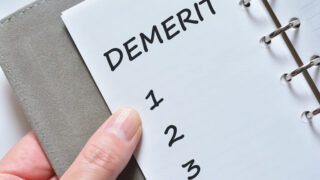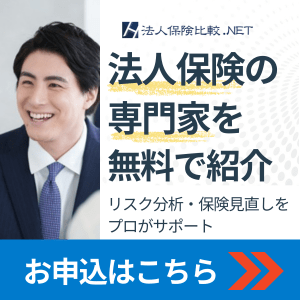法人保険の中には、企業が持つ社用車に対して補償をかけられる法人向けの自動車保険があります。
営業用の車などを購入した際、法人向けの自動車保険を検討する方も多いでしょう。
その際に気をつけておきたいポイントは、個人名義の自動車保険との違いです。
実は、法人保険としての自動車保険は、個人向けとは少し契約内容が異なるのです。
また、自動車の台数が多い場合にはよりお得に契約できるなど、メリットも数多くあります。
そこで今回は、法人向け自動車保険の契約内容とメリット、そして代表的な法人向け自動車保険の紹介をしていきます。
「とりあえず法人向けの自動車保険について知りたい」
「法人向けの自動車保険に加入したいから具体的な保険商品が知りたい」
という方は、こちらの記事でお悩みが解決します。ぜひご一読ください。

記事監修した保険のプロ:
40代/男性
- AFP
- トータル・ライフ・コンサルタント(生保協会認定FP)
- 個人情報保護士
外資系大手保険会社での営業経験を活かし、生保・損保問わず企業向けに保険提案を行っている。保険商品だけでなく、金融商品・税金に関する知識は幅広く、お客様からの紹介が後を絶たない。
自動車法人保険とは
法人が業務上利用するタクシーやトラック、営業車などは個人の自動車保険には加入できず、自動車法人保険へ加入する必要があります。
自動車法人保険は、個人向けの自動車保険と基本的な補償内容は同じですが、法人保険ならではの補償や特約などがあります。
また原則として、自動車法人保険は「契約者」「記名被保険者」「所有者」がすべて同一の法人名義であることが条件となり、業務上利用しているリース自動車も契約することが可能です。
自動車法人保険の主な補償内容
自動車法人保険の主な補償内容について下表にまとめてみました。
| 補償名 | 補償内容 |
|---|---|
| 対人賠償保険 | 自動車事故により相手がケガを負ったり死亡したりした場合の損害賠償責任を補償。治療費や精神的損害、休業損害などが支払われる。 |
| 対物賠償保険 | 自動車事故により相手の自動車などを壊してしまった場合の損害賠償責任を補償。自動車の修理費用や代車費用、壊したものの修理費用などが支払われる。 |
| 人身傷害保険 | 自動車事故により運転者や同乗者がケガ・死亡した場合を補償 |
| 車両保険 | 自動車の損害を補償。修理費用などが支払われる。 |
このように、個人向けの自動車保険と同様の補償内容となっています。
自動車法人保険特約やサービス
保険会社によっては、自動車法人保険ならではの特約やサービスを付けられるプランがあります。主な特約・サービスについて下表にまとめました。
| 特約・サービス名 | 内容 |
|---|---|
| 対人賠償使用人災害特約 | 業務中の従業員を死傷させてしまった場合を補償(対人賠償では補償対象外) |
| 対物賠償非所有管理財物特約 | 他人から借りている建物などの財物を破損してしまった場合の補償(対物賠償では補償対象外) |
| 事業用積載動産特約 | 自動車に積載中の商品や備品などの損害を補償(対物賠償や車両保険では補償対象外) |
| 運送業者受託貨物賠償特約 | 受託貨物に偶然の事故で損害が生じ、貨物の所有者等に法律上・契約上の損害賠償責任を負った場合を補償 |
| ロードアシスタンスサービス | レッカー牽引・搬送などのトラブルに対するサポート。大型トラックの場合、レッカー代は高額になるケースがあるため保険会社によっては補償を拡張できる特約がある |
| ドライブレコーダー特約 | 事故時の通報サービスや事故映像を用いた事故対応サービスを受けられる |
このように、法人自動車保険ならではの特約を選択できるため、業務内容に合わせて加入を検討すると良いでしょう。
法人向け自動車保険のメリット

社用車に保険をかける場合、法人保険(法人名義での加入)ではなく個人向けの自動車保険に個人名義で加入することも可能です。
しかし法人名義で加入する自動車保険では、個人向けの自動車保険を選択するよりもメリットが大きい場合があるため、法人向けを選んだ方が良いことがほとんど。
法人保険としての自動車保険には、以下の3つのメリットが挙げられます。
- 複数台(10台以上)契約した時に保険料がお得
- 減税効果を期待できる
- 法人保険だけにつけられる特約がある
1つずつ見ていきましょう。
複数台(10台以上)契約した時に保険料がお得
規模の大きい法人の場合は、社用車を複数台所有していることも多いでしょう。
特に10台以上の自動車を所有している法人は、法人向けの自動車保険を契約するのがおすすめ。
というのも、法人向けの「フリート契約」で契約することで、個人契約よりも保険料が安くなるからです。
保険料を安い価格に抑えたい場合、フリート契約がおすすめです。
フリート契約とは
10台以上の車に一気に自動車保険をかけることを、フリート契約と言います。
法人向けのフリート契約には、以下の3つのメリットがあります。
- 運転者の年齢で保険料が左右されない
- 通常の契約よりも保険料が割引になる
- 保険証券を1枚で管理できる
フリート契約は、車両1台ごとに管理されるものではなく、契約者単位で管理されます。
そのため、法人名義で契約した場合、運転者の年齢による保険料区分がありません。
若い人が運転した場合でも、保険料が割増になることがないのです。
また、契約者単位で割引率が適用されるため、法人が1つの名義で契約している全自動車の保険料に対して、割増引が適用されるというメリットもあります。
さらに、保険証券を1枚で管理できるため、書類の保管や保険更新など、事務的な手続きによる負担もありません。
なお、フリート契約の場合、通販型には取扱いがないため注意しましょう。
フリート契約の割引率
通常、自動車保険は等級などによって保険料の割増引率が決められ、負担する保険料の金額が増減します。
割引率が大きくなれば、自動車保険料のコスト削減にもつながります。
しかし、フリート契約には等級がありません。その代わりに、3つの要素によって割増引率が決められています。
①総契約台数
総契約台数とは、法人として自動車保険に加入している合計台数のことです。総契約台数が多くなるほど、保険料の割引率が高くなる傾向があります。
保険商品によっては、最大70~80%の割引が適用されるものもあります。
詳細に関しては、保険会社によって異なりますのでお問い合わせください。
②損害率
損害率とは、契約者が支払った全契約の保険料に対して、保険会社が支払った保険金がどれぐらいあるかという割合のことです。
契約者である法人が事故を起こしていなければ、損害率は低くなります。損害率が低いほど、割引されやすくなるため、事故を起こさないことが重要です。
なお、損害率は下の式で求めることができます。
③前年度のフリート割増引率
次年度の割増引率は、前年度の優良割引率を基盤として決められます。
優良割引率とは、損害率の良好な者に対して適用する割引です。前年がノンフリート契約だった場合は、平均無事故率が適用されます。
このように、割増引率には3つの要素がありますが、保険料を少しでも抑えるためには、いかに損害率を低くするかというのがポイントです。
フリート契約では、一括で管理ができることはメリットですが、一台の事故がすべての契約車両の損害率に影響します。
そのため、改めて社用車を利用する社員の安全運転、利用ルールを徹底しておく必要があるでしょう。
ミニフリート契約もある
フリート契約は10台以上を対象としたものですが、2台~9台の台数に対して一気に保険をかけられる「ミニフリート契約」という方法もあります。
こちらは、フリート契約のように1枚の保険証券で複数の車を一括で契約できる一方、割引率に関してはノンフリート契約の率を適用するというものです。
10台とはいかないものの、複数台の車を所有している法人におすすめです。
減税効果を期待できる

法人保険としての自動車保険に加入する2つ目のメリットは、減税効果です。
法人名義で自動車保険に加入した場合、保険料を損金として計上することができ、その分会社の利益が減ることになります。
つまり、法人税の課税対象となる利益が減るため、減税効果を期待できるのです。
ただし、減税効果を得るためには条件があるので、要注意。具体的には、下記の2つがポイントです。
- 法人名義で自動車保険の契約をすること
- 自動車保険は、会社で使用する目的で契約すること
これらの条件を満たさなければ、自動車保険による税制上のメリットは望めないため、注意しましょう。
法人保険だけにつけられる特約がある
法人保険としての自動車保険には、個人向けにはない特約が用意されていることがあります。
たとえば、保険契約をした自動車の積荷が事故により破損した場合に補償される「積載事業用動産特約」などの特約が挙げられます。
このような、法人特有の業務上の事故に対応した特約を付けられる点が法人保険としての自動車保険のメリットです。
また、タクシーやトラックなど、個人向けの自動車保険で契約ができない場合も、法人向けの自動車保険なら加入できます。
デメリットはフリート契約の事故の影響

さて、ここまでは法人保険としての自動車保険に契約するメリットを説明してきました。
一方で、法人向けの自動車保険は、特にフリート契約をしている場合に大きなデメリットが発生する可能性があります。
フリート契約の場合、保険契約している車のうち一台でも事故を起こすと、その影響がすべての契約車両に及び、全車両の損害率が高くなります。
よって、一度事故を起こしてしまうと、翌年から一気に保険料が上がってしまう可能性があるのです。
法人保険の保険料を抑えたくてフリート契約にしたのに、結局高額な保険料を支払うことになってしまうことにもなりかねないので、注意が必要です。
個人名義の契約を法人保険に切り替える際のポイント

個人事業主が法人成りをするようなケースでは、個人契約で契約していた自動車保険を法人名義に切り替えることもあるでしょう。
この時、場合によっては個人契約の等級を引き継いで切り替えることが可能です。
6等級からスタートして1年ごとに1等級アップ、最大で20等級までランクが上がる仕組みの等級は、上がれば上がるほど保険料が割引されます。
そのため、法人保険に切り替えた際にも等級を引き継ぐことができれば、企業の保険料負担を抑えることに繋がります。
個人契約から法人保険へ等級を引継ぐには、下記の2つの条件を満たす必要があります。
- 個人事業と法人成りしたあとの事業が同じ
- 法人名義に引き継いだ後も、被保険者が同じ
一方、法人保険としての自動車保険から個人契約に切り替える際に自動車の等級を引き継ぐためには、下記の4つを満たす必要があります。
- 法人名義の自動車保険をノンフリート契約で契約していた(フリート契約の場合は等級がないため)
- 法人保険から個人名義に切り替えたあとも、被保険者が同じ
- 個人事業主となる
- 法人時と同じ事業を継続して行っていく
条件を満たさなければ等級の引き継ぎはできず、保険料割引のメリットも享受できなくなってしまうので、よく確認しておくことが重要です。
法人向けの自動車保険、比較してみました

さて、法人保険としての自動車保険について、メリットとデメリットをご理解いただけたでしょうか?
ここからは、自動車に関する法人保険の中でもおすすめの商品を5つご紹介していこうと思います。
表にまとめましたので、下記をご覧下さい。
自動車の法人保険おすすめ一覧
| 保険会社 |
ロードサービスの付与
|
補償内容の手厚さ
|
年間の保険料
|
|---|---|---|---|
| 三井住友海上 | ◎ (全契約者に付く) |
◎ | 約12万円~ |
| 損保ジャパン | ◎ (全契約者に付く) |
◎ | 約10万 5,000円~ |
| チューリッヒ | ◎ (全契約者に付く) |
◎ | 約9万円~ |
| あいおい ニッセイ 同和損保 |
○ (特約次第で付く) |
○ | 約10万円~ |
| AIU損害保険 | ◎ (全契約者に付く) |
○ | 約9万 5,000円~ |
※1 法人で1台のみ契約した場合です。フリート契約は条件によって異なりますので、各保険会社にお問い合わせ下さい。
※2 あくまで金額は目安として認識下さい。条件などによって変動する場合があります。
法人保険の場合、気になる年間保険料は最低額がおよそ9万~10万円ちょっとが相場の額でしょうか。
三井住友海上は12万円~と少し高めな印象ですが、そのかわり補償内容が優れています。
保険料がいくら安くても、法人保険として役にたたなければ意味がありません。
そのため、ロードサービスや業務中の自動車事故に関する補償内容については非常に重要なポイントです。
おすすめはチューリッヒのスーパー自動車保険
先程紹介した自動車法人保険の中でも、チューリッヒの自動車保険「スーパー自動車保険」がおすすめ。
その理由は、充実したロードサービスにあります。
ロードサービス
チューリッヒのロードサービスは、業界最高レベルと言われる内容が無料でついています。
- レッカーけん引(100kmまで無料)
- バッテリー上がりのジャンピング
- キー閉じこみ時の鍵開け、キー紛失時の解錠作成
- パンク時のスペアタイアの交換
- 落輪対応
- ガス欠時の給油サービス
- オイル漏れの点検・補充、エンジン冷却水の補充
- 各種灯火類のバルブ交換
- ボルト増締め
- サイドブレーキの固着の解除
- 修理後搬送費用の補償
- 帰宅費用・宿泊費用サポート
- レンタカーサポート
※保険期間中に1回のみ無料など、サービスによって無料対応の回数制限が設けられています。
これらのサービスが、わざわざ特約をつけなくとも全ての車に付いているのは、非常に有用性があると言えるでしょう。
補償内容
チューリッヒの自動車保険では、対人賠償、対物賠償、搭乗者傷害保険、人身傷害保険の4つの基本補償が完備されています。
これら4つの補償に加えて、車両保険や弁護士費用特約など、必要な特約を付加させることが可能。
特約は基本補償と補償内容がかぶらないように選ぶのがポイントです。
選び方のポイントは目的と補償内容

これまで法人向けの自動車の保険について説明してきましたが、いかがでしたか?最後に、ポイントを復習してみましょう。
ポイントまとめ
- 自動車の法人保険は、節税やフリート契約などのメリットがある
- フリート契約をした際には、1台の事故が全車両に影響を与えることを忘れない
- 保険料や補償のバランスを考えて選ぶこと
法人保険として自動車保険を選ぶ際には、この3つがポイントになります。
当記事ではおすすめの法人向け自動車保険をご紹介しましたが、経営者の皆様にとって最適の保険とは必ずしも言い切れません。
あなたが何を重視しているかによって、ベストな法人保険は変わります。
補償の手厚さを求めるのか、保険料を抑えて契約したいのか、自分のニーズにあわせた法人保険を選ぶためにも、たくさんの会社を見て比較検討することが一番です。
なかなか自分に合った自動車保険が見つからないという方は、法人保険を扱う保険代理店のスタッフなど、あらゆる保険商品について知識のある法人保険のプロに相談することも1つの解決策です。
時間ばかりかかって面倒、うまく法人保険を比較できない新規契約の方など、法人保険のプロへの相談や見積りから始めてみてはいかがでしょうか?
店舗を訪ねるのはハードルが高いですが、ネット上からお気軽にお問い合わせください(↓)。
法人保険比較.netのコンサルタント無料紹介
サービス
法人保険比較.netでは、法人保険の専門家と連携した無料相談サービスを提供しています。
- 経営に生命保険や損害保険を役立てたい
- いま加入している保険を見直したい
- 退職金制度や福利厚生を導入したい
- そろそろ事業継承や相続について考えていきたい
- 税金対策や資産運用など包括的な相談がしたい
法人保険は単なるリスクヘッジだけではなく、企業の財務強化や競争力向上など様々なメリットがある経営ツールです。事実、中小企業から大企業まで多くの法人が保険を活用しています。
ただし、保険は個々に最適なプランを立てなければ効果を発揮しません。法人保険を最大限活用するためには、経営や各種法規への理解が深いコンサルティングに相談することが重要です。
当サイトでは、法人領域を専門とする保険のプロを"無料"でご紹介します。
経営者や企業担当者の方は、ぜひお気軽にご登録ください。